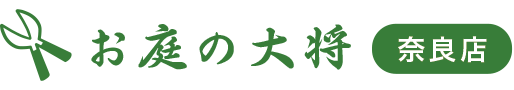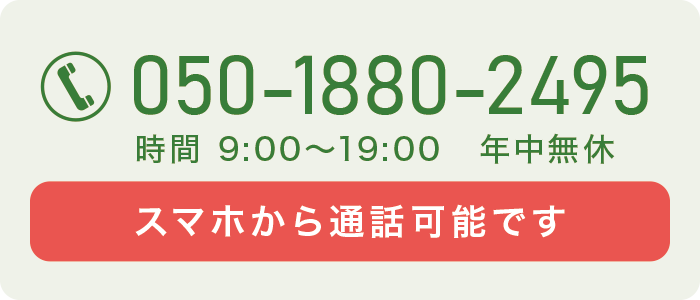しかし、剪定は正しいやり方と少しの知識さえあれば、決して難しいものではありません。木の性質や育てたい形に応じた剪定方法を理解し、必要な道具とタイミングを押さえれば、誰でも安全に、美しく仕上げられます。
この記事では、初心者でもすぐに実践できる剪定の基本的なやり方をわかりやすく解説します。
どの枝を切ればいいか、外芽の見分け方・剪定ハサミの選び方など、悩みを一つずつ解消していきましょう。
最後まで読めば、自信を持って庭木の剪定に取り組めるはずですよ。
剪定ってそもそも何?なぜ必要なの?

剪定の目的は見た目だけじゃない
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| 樹形を整える | 自然に伸びた枝を調整し、美しく整った形に保つため。 |
| 風通しと日当たりを改善する | 枝葉が密集しないようにして、病害虫の発生を防止する。 |
| 不要な枝を除去する | 枯れ枝・交差枝・内向き枝などを取り除き、全体のバランスを保つ。 |
| 養分の分配を最適化する | 健康な枝に栄養を集中させて、木全体の健やかな成長を促す。 |
| 花や実の付き方をコントロールする | 花木や果樹の品質や収穫量を調整する。 |
剪定しないとどうなる?放置のリスク
⚫︎枝が過密になり病害虫が発生しやすくなる
⚫︎樹形が乱れて景観が損なわれる
⚫︎強風で折れた枝が落下し危険になる可能性
⚫︎隣家や道路へ枝がはみ出してトラブルの原因に
⚫︎養分が分散しすぎて花や実がつきにくくなる
特に注意したいのは、害虫や病気の温床になってしまうことです。風通しが悪いと湿気がたまりやすくなり、カビや病原菌が発生しやすくなります。
またモサモサに茂った枝は害獣のすみかにもなりやすく、害獣駆除の観点からも剪定は欠かせません。
また枝が建物の壁や屋根に接触することで、建材を傷めたり、雨どいを詰まらせたりする事例も少なくありません。剪定の手間を惜しんだ結果、思わぬ修繕費用が発生してしまうこともあるのです。
剪定に適した時期を知ろう

ここでは落葉樹・常緑樹・花木といった樹種ごとに最適な剪定時期を解説し、避けるべきタイミングについても詳しく紹介します。
落葉樹は冬、常緑樹は初夏が基本
| 樹種 | 剪定の最適時期 | 理由 | 主な樹の例 |
| 落葉樹 | 冬(12月〜2月) | 落葉して休眠期に入るため、ダメージが少ない | カエデ、サクラ、モミジ |
| 常緑樹 | 初夏(5月〜6月) | 新芽の成長が落ち着いた時期で、風通しも確保できる | ツバキ、マツ、キンモクセイ |
一方、常緑樹は、気温が安定し新芽の成長がある程度落ち着いた初夏に剪定するのがポイント。病害虫のリスクも低く、木への負担も比較的少ないとされています。
花木は花が終わった後すぐに
| 花木の種類 | 剪定タイミング |
| ツツジ、サツキ | 花が終わった直後(6月頃) |
| アジサイ | 花後すぐ(7月頃まで) |
| ウメ、モモ、サクラ | 開花後1ヶ月以内 |
絶対に避けたい4〜5月の新芽時期
新芽の成長期は木が養分を使って一気に成長するタイミングであり、剪定によりダメージを受けやすくなります。以下に詳しい理由をまとめました。
⚫︎樹勢が弱まりやすい
⚫︎新芽が痛みやすくなる
⚫︎成長に必要な葉を失い、光合成が妨げられる
⚫︎結果的に木が枯れる原因になることも
やむを得ず剪定する場合は、最小限の軽い整枝にとどめておくのがよいでしょう。どうしても枝が邪魔になる場合でも、強剪定は避けましょう。
これだけは揃えたい!剪定に必要な道具

ここでは剪定の場面で活躍する、ハサミの種類と安全作業のための道具について詳しく見ていきましょう。
枝の太さで使い分ける3つのハサミ
| 道具名 | 主な用途 | 特徴・備考 |
| 剪定ばさみ | 細枝・若枝の切除 | 片手で使える軽量タイプ、切れ味重視 |
| 刈り込みばさみ |
生垣や細かい枝の整形用 |
両手で使用、刃が長く広範囲を切れる |
| 剪定ノコギリ | 太い枝や古枝の処理 | 折りたたみタイプもあり、安全で収納便利 |
剪定ノコギリは、太く硬い枝に使いますが、切り口をスムーズに仕上げるには一定のコツが必要です。どの道具も定期的なメンテナンスで切れ味を保ち、樹木へのダメージを抑えられるでしょう。
安全作業のための必須アイテム
| 道具名 | 用途・目的 | 備考 |
|---|---|---|
| 作業用手袋 | 手の保護 | 切り傷・トゲ対策に滑り止め付きが最適 |
| ヘルメット | 高所作業時の頭部保護 | 落下物や枝に頭をぶつける事故を防止 |
| 保護メガネ | 目の保護 | 飛び散る木くず・枝葉から目を守る |
| 高枝切りばさみ(ポール式) | 高い位置の剪定 | 脚立不要で安全性が高く、扱いやすい |
| 脚立(安全ロック付き) | 届かない枝の剪定時 | 平坦な地面で使用し、転倒防止措置を忘れず |
特に、高枝切りばさみや安全ロック付きの脚立は、剪定作業を効率化するうえで非常に役立つでしょう。家庭でのDIY剪定であっても、プロ並みの備えを意識して準備しておくと安心です。
どの枝を切るべき?不要な枝の見分け方

まずは切るべき不要な枝の種類と見分け方を知っておきましょう。
樹形を乱す忌み枝の種類
| 忌み枝の種類 | 特徴と剪定理由 |
| 逆さ枝 | 上から下に向かって伸びる枝で、樹形を乱す原因に |
| 交差枝 | 他の枝と交差して擦れ、傷や病害のリスクを高める |
| 内向き枝 | 幹に向かって伸びる枝で、風通しや日当たりを妨げる |
| 平行枝 | 同じ方向・高さに伸びる枝が並行し、混み合いを招く |
| 下がり枝 | 枝が垂れ下がって地面に近づき、美観や通行を妨げる |
剪定時には、樹形の美しさと風通しの確保を意識しながら、的確に見極めて除去しましょう。また剪定後の切り口には癒合剤を塗れば病気予防にもつながります。
病気や虫害のある枝は最優先で除去
| 病枝・虫害枝の特徴 | 見分け方と対応策 |
| 葉が変色・斑点状になっている | カビ・病原菌による感染の可能性。早めの除去が必要 |
| 枝の一部が枯れている | 栄養供給が断たれた可能性あり。枝の付け根から切り落とす |
| 樹皮が剥がれたり傷んでいる | 虫害や病気のサイン。患部より下の健全な部分で剪定 |
| 虫の巣・卵がある | 害虫の繁殖源になるため発見次第、すぐに取り除くことが望ましい |
剪定により病枝を取り除くことで、他の健康な枝への被害を最小限に抑えられますよ。剪定後の枝はビニール袋に入れて密閉し、自治体の規定に従って処分するのがおすすめ。可能であれば焼却処分で再感染を防げます。
剪定のやり方!切り方をマスターしよう

外芽の5〜10mm上で斜めに切る
外芽のすぐ上で切れば、木全体の形が広がりやすくなり、風通しや日当たりが良くなるでしょう。切る位置は、芽の5〜10mm上を目安にし、角度は水はけをよくするために斜めに整えてください。
芽の向きを見極め、外側を選べば、不要な内向き枝が発生しにくくなり、自然な仕上がりにつながります。また切る位置が近すぎると芽を傷つける恐れがあるため、少し余裕を持たせましょう。
太い枝は3段階で切り落とす
トラブルを防ぐには、3段階に分けて切る「3段階切り」がよいでしょう。まずは枝の下側に浅く切れ込みを入れ、次にその少し外側から上方向に切り落として枝の重さを逃がします。
最後に残った部分を幹の根元で丁寧に切れば、綺麗な切り口を作れます。3段階切りを使えば、切断時の木への負担を減らしつつ、安全に作業できますよ。
特に力がかかる太い枝では、このような安全策を取ることがプロの剪定でも常識です。
枝の分岐点で切る
分岐点で切れば、残された枝がそのまま樹形に沿って伸びやすくなり、見た目にも違和感がありません。逆に分岐から中途半端な場所で切ると、切り口から新しい枝が乱れて生えてくる可能性が。
バランスの悪い仕上がりになりがちです。また分岐点でのカットは、芽や葉の付き方をコントロールしやすく、木全体のフォルムを整えるのに向いています。
切り口は垂直に、受け刃の向きに注意
切り口が鋭角になりすぎると、水分が溜まりやすくなり、病気や腐敗の原因となる恐れがあります。
また使用する道具の「受け刃」(剪定ばさみの支え側の刃)を幹側に向けると、切断面が滑らかになり、回復も早くなりますよ。
道具の向きや圧のかけ方を意識するだけで、仕上がりの美しさと木の健康状態が大きく変わるためおすすめの方法です。
太い枝の切り口には癒合剤を塗る
癒合剤はホームセンターなどで市販されており、切り口全体をしっかり覆うように塗れば、乾燥や腐敗を防げます。
特に梅雨時期や多湿な場所に植えられた木では、癒合剤を使うかどうかが木の寿命に関わる場合も。
ただし塗りすぎは通気を妨げるため、厚くなりすぎないよう注意しましょう。必要な処置を行うのが、木を元気に保つ秘訣です。
全体の1/3程度剪定する
必要以上に切ってしまうと、木に強いストレスがかかり、回復が追いつかない可能性があります。逆に、あまり切らなければ、剪定の意味が薄れてしまい、風通しや日当たりが改善されません。
バランスよく、混み合った部分を中心に整理しつつ、剪定後に木全体を眺めて仕上げると自然な樹形に仕上がります。初めは少しずつ調整しながら進めると、失敗が少ないでしょう。
初心者が剪定でやりがちな失敗と対策

⚫︎一度に切りすぎると木が弱る
⚫︎枝の途中でブツ切りはNG
⚫︎弱っている木の剪定は見送る
それぞれの対策を押さえておくと、安全かつ美しい仕上がりが実現できます。ここ代表的な失敗例と回避策を解説します。
一度に切りすぎると木が弱る
枝葉を大量に切除することで、光合成の能力が一気に落ち、栄養をつくる力が弱まるおそれがあるためです。特に樹勢の弱い木や成長期の木には大きな負荷となります。
対策として、一度に剪定する量を全体の1/3 程度に抑えましょう。まずは混み合った部分から間引くように整理し、木全体を見ながら少しずつ切り進めていくのが無難です。
また剪定を複数回に分けて段階的に行うことで、木にかかる負荷を和らげられます。木が回復しやすく、安全性と美観を両立できる剪定を行えるでしょう。
枝の途中でブツ切りはNG
正しい対策は、分岐点や芽のすぐ上で切るのを意識する方法です。枝が分かれている場所の直上を切ると、自然な枝の構成が保たれ、余分な枝が出にくくなります。また芽のすぐ上を切れば、そこで新しい枝の誘導がしやすくなります。
切断位置に注意すれば、剪定後の樹姿が整いやすくなり、無秩序な枝が増えるのを防げます。
弱っている木の剪定は見送る
対策としては、木の健康状態の見極めから始めましょう。葉の色や樹皮の状態・根の様子などを確認し、明らかに衰えていると判断できる場合は、剪定を控えて養生期間を設けるのがおすすめ。
その後、様子を見ながら軽めの剪定を段階的に行う方法をとると、木に無理をさせずにケアできます。
弱っている木に無理をさせず、まずは体力回復を目指すのが、長期的に見て無難な方法と言えるでしょう。
剪定についてよくある質問

高さ何メートルまで自分で剪定できる?
一般的には 3〜4メートル程度までが目安です。脚立や高枝切りばさみ・ポールソー類を使ってその範囲までは比較的安全に手が届くためです。
ただし木が5メートルを超えるような高木になると、高所作業のリスクもあり危険です。足場不安定・風の影響・落下物などの危険が伴うため、自信がなければプロの業者に頼むとよいでしょう。
地域によっては自治体の許可が必要な木もあるため、高さを理由に迷うなら、まず現地調査を依頼するのが安全です。
実際に自分で行う際は、3〜4メートルを上限とし、安全装備・安定した脚立設置・風のない穏やかな日を選ぶなど、条件を整えつつ進めましょう。
年に何回剪定すればいい?
成長が遅い種類の木なら年1回でも十分なケースがありますが、成長の速い樹木や枝葉が密になりやすい木では、軽めの剪定を年2回に分けて行うのが望ましいケースもあります。
頻度を決める際には、次のような点も考慮すると失敗しません。
⚫︎樹種(常緑樹か落葉樹か、生育力の強さ)
⚫︎立地環境(日当たり・風通しの良さ)
⚫︎見た目を保つ頻度(整えたい頻度)
⚫︎過去の剪定履歴(どれくらい切られていたか)
例えば、伸びやすい生垣やシマトネリコなどは、年2回前後で軽めの透かし剪定を加えると形が乱れにくくなります。
他方、成長が穏やかな木なら、1回の剪定で十分な場合も。ポイントは過度な剪定を避け、木にストレスをかけすぎない範囲で調整をすることです。
業者に頼んだ方がいいケースは?
⚫︎高木剪定(5メートルを超える高さ)で安全性に不安がある
⚫︎ロープ作業・重機使用など技術と設備が必要な作業
⚫︎隣家や建物近接木で、枝の落下リスクが高い場合
⚫︎病気や害虫の疑いがある箇所があり、診断・処理も含めて対応したい
⚫︎剪定後の枝葉処理・片付けまで任せたい
⚫︎樹形を整えるデザイン性を重視した剪定を希望する
業者に頼むと、作業の安全性・効率性・仕上がりなどがよくなります。もちろん費用はかかりますが、失敗や後処理の手間・事故リスクを避けられることを考えれば、コスト的にも検討の余地はあるでしょう。
業者に依頼する際は、見積もり内容・保険対応や保証内容を必ず確認しておくと安心です。
剪定のやり方に悩んだらお庭の大将にお任せください!

安全第一で行う現地調査から、樹種に応じた最適な剪定プラン・片付けまで一括で対応可能です。剪定を始めるかどうか悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
無料見積もり・現地診断で、お客様の庭にぴったりな剪定方法をご提案いたします。