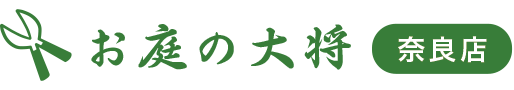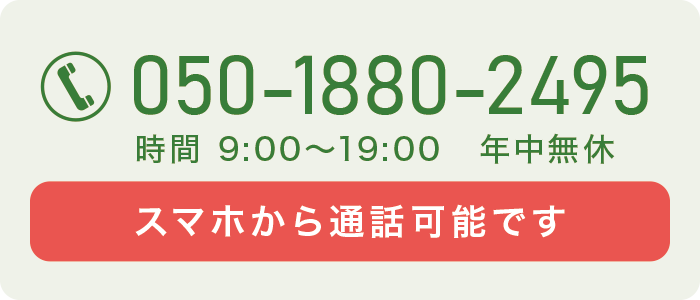失敗しない業者選びと自分でやる際の注意点


自分で切りたい気持ちも分かりますが、高さのある杉の伐採はプロの業者に任せるのが最も安全で確実な方法です。
チェーンソーや重機を使う作業は危険が伴い、誤った判断が大きな事故につながるため、専門技術と経験が欠かせません。
この記事では、杉の伐採に関する費用相場や適した時期・追加費用・業者の選び方・補助金の有無などを解説します。
国が杉の木を伐採しないのは理由がある

しかし国が伐採しないように見えるのには、複数の背景が存在します。
ここでは、採算性や環境保全・林業人材不足 の3つの観点から見ていきましょう。
木材価格の低下・採算性の問題
かつて日本は木材の自給率が低く、杉の植林が奨励されました。しかし現在は、輸入材の価格が低く安定していることから、国産材の価値が相対的に下がっています。
その結果、伐っても儲からないといった構造が表面化し、林業会社や森林組合が積極的に伐採できない状況が続いているのです。
特に杉は成長が早く大量生産向きのため、成熟した林が全国に点在していますが、伐採・搬出には人件費・重機費用・運搬費がかかるのがネック。さらに丸太価格との差が大きく、赤字になりやすい課題があります。
木材価格が低迷すると発生する問題は以下の通りです。
⚫︎伐採しても利益が出ない
⚫︎運搬コストが高く赤字化しやすい
⚫︎伐採後の造林(植え直し)に回す予算が不足
⚫︎林業企業が伐採を避けるようになる
⚫︎放置林が増加し、森林管理が困難になる
伐採の採算性は、想像以上に深刻な問題です。木材価格は1990年代と比べて半分以下に落ち込んだ時期もあり、林業従事者は伐れば伐るほど赤字といった状況に直面してきました。
そのため林業事業体は、利益の出る大型案件(山林一帯の間伐・主伐)を優先し、採算性の低い区域の伐採を後回しにせざるを得ません。
つまり国が伐採しないのではなく、伐採できない構造が長年続いているのです。そのため個人宅の高木を伐採したい場合には、民間の伐採業者に依頼するのがおすすめです。
庭木は木材として流通できないため、自治体や国が伐採を引き受けるケースは基本的にありません。
伐採業者に依頼すれば、チェーンソー・クレーン車など専門機材を使い、1日で安全に作業が完了します。
環境保全と災害防止の役割
そのため、すべての杉を伐採してしまうと、山の保水力が低下し、土砂災害が発生しやすくなる危険に注意しなければなりません。
特に日本は豪雨が多いため、森林が果たす役割は極めて重要です。国や自治体は「むやみに伐採しない」「計画的に間伐する」などの方針を取っており、伐採しないように見える理由のひとつにもなっています。
杉林が持つ環境・防災上の役割は以下の通りです。
⚫︎大雨時の土砂流出を防ぐ
⚫︎地滑りのリスクを軽減
⚫︎山の保水力を高める
⚫︎CO₂吸収による環境保護
⚫︎生態系の維持に寄与
花粉症の原因として杉が嫌われがちですが、森林が果たす防災機能は軽視できません。特に急傾斜地の多い日本では、森林が自然のダムとして働いており、短時間豪雨が多発する近年では、森林の保水能力が非常に重要です。
ただし放置された人工林は、樹木の密度が高すぎて光が入らず、根が深く張らない問題が生じます。そのため木が倒れやすく、かえって危険が増す可能性も。
本来は計画的な間伐によって木々の健全な成長を促し、森林全体を健康に保つ必要があるのです。
国が伐採しないように見える実態は、無計画では伐らないといった意味であり、森林政策としては伐採+植え直し+育林をセットで進める必要があります。
つまり伐採は単体ではなく森林管理の一部であり、単純に杉を全部切れば花粉症はなくなるわけではありません。
一方で、個人宅の大きくなりすぎた杉は、防災機能とは無関係です。倒木・落枝リスクを考えると、専門業者に伐採を依頼したほうが安全でしょう。
林業従事者不足の現状
高度な技術と危険を伴う仕事であるにもかかわらず、収入が安定しにくいため、就業者が増えにくい現状があります。
林業を支える人材が減れば、伐採・搬出・育林作業が遅れ、結果として杉が伐られない状況につながります。
林業の担い手が不足する要因は以下の通りです。
⚫︎収入の不安定さ
⚫︎作業の危険性(重機作業・チェーンソー使用)
⚫︎山林地域の高齢化
⚫︎後継者不足
⚫︎若手育成の遅れ
林業は、チェーンソー・伐倒技術・重機操作など高度な技能が必要な専門職です。危険を伴う作業が多く、天候によって仕事が中断されるケースも。そのため安定した収入が得にくく、若い世代から敬遠されがちです。
また専門技術を習得するには時間がかかり、地域ごとのノウハウが必要になる場合もあります。
そのため新規就業者が増えにくい構造が固定化し、結果として伐採の需要に作業者が追いつかない問題が発生しているのです。
国としても補助金や研修制度を設けていますが、山林の面積に対して人材が圧倒的に不足しているのが現実といえるでしょう。
背景を理解すると、個人宅の伐採が林業の仕組みとは別軸で扱われる理由も明確になります。
庭木の伐採は、伐採専門業者が担当し、林業とは異なるノウハウで作業を行うのが一般的。そのため杉が国によって伐採されない状況でも、個人が伐採業者に依頼することで迅速に対応してもらえます。
実際、庭の杉伐採で多い相談は以下のとおりです。
⚫︎高くなりすぎて不安
⚫︎台風で倒れそう
⚫︎花粉症対策として切りたい
⚫︎抜根までまとめて頼みたい
伐採の悩みは、林業ではなく伐採業者への依頼が最も早く、安全で確実な解決方法になります。
杉の伐採を依頼できる業者の種類

伐採は、チェーンソーや重機を用いる危険な作業であり、業者ごとに得意分野・料金相場・作業範囲が異なります。
ここでは杉伐採を依頼できる代表的な3種類の業者について、特徴と向いているケースをわかりやすく見ていきましょう。
伐採業者
チェーンソーや防護服・ロープワーク・クレーン車などを駆使し、作業工程ごとに危険を最小限に抑えながら進める点が大きな特徴です。
伐採後の処分費用や抜根(根の除去)までワンストップで対応するところも多いため、総合的に頼れる存在といえるでしょう。
伐採業者の特徴としては、以下が挙げられます。
⚫︎高木の伐採に慣れている
⚫︎重機(クレーン・高所作業車)を使用できる
⚫︎倒壊リスクの高い木でも対応可能
⚫︎伐採後の処分・抜根まで依頼しやすい
⚫︎見積もりが明瞭な業者が多い
伐採業者は、最も杉伐採に特化したプロフェッショナルです。特に杉は成長が早く、高さ20mを超えるケースも珍しくありません。
このような高木伐採では、倒す方向を誤ると住宅を破壊する事故につながるため、高度な伐倒技術が必要です。
伐採業者は、幹にロープをかけて倒れる方向を固定したり、上部から少しずつ切り分けて吊り下ろすつり切り作業を行う技術を持っています。
庭が狭い住宅街でも安全に作業ができるのは、この高度なスキルと重機操作技術があるためです。
また杉の伐採後に必ず発生するのが、処分費用です。杉は木材として流通できないことが多く、一般的には破砕・焼却などの処理が必要になります。
伐採業者なら処分費用も含めて一括で対応できるため、初心者でも安心して依頼できるでしょう。
特に、以下の場合は、伐採業者を選ぶのが最も安全です。
⚫︎庭の杉が10m以上
⚫︎倒木の危険がある
⚫︎隣家に枝が越境している
⚫︎抜根まで依頼したい
造園業者
伐採専門ではありませんが、日常的に樹木を扱っているため、庭木の状態を判断しながら適切な伐採方法を選べます。
特に低〜中木(5〜10m前後)の杉であれば、多くの造園業者が丁寧に対応できます。他にも依頼できる内容は以下を参考にしてください。
⚫︎庭木の剪定・管理も依頼できる
⚫︎植栽のアドバイスが可能
⚫︎中木までの伐採なら対応可能
⚫︎景観を損ないにくい作業
⚫︎抜根作業にも対応する業者がある
造園業者は庭全体のバランスを考えながら作業するため、伐採後の景観を重視したい人に向いています。
たとえば「杉を切った後に何を植えるべきか」「周囲の木とのバランスはどうなるか」といった相談にも応じてもらえます。
一方で、高木伐採になると対応できるかどうかは業者次第です。造園業者は剪定や手入れが中心のため、クレーンが必要な大規模伐採は行わないところもあります。特に20m以上の杉は、専門的な伐倒技術を持った伐採業者のほうが安全です。
また造園業者のメリットのひとつは、伐採と同時に庭全体をリニューアルできる点です。花粉症対策として「杉を切って落葉樹に植え替える」「洋風庭園に変更する」といった相談もよくあります。
そのため、以下の相談をしたい人にもおすすめです。
⚫︎杉の伐採後に庭を整えたい
⚫︎剪定・植栽の相談もしたい
⚫︎木の高さが10m前後
条件に当てはまる人は、造園業者がもっとも相性の良い方法になります。
便利屋
便利屋は伐採専門ではありませんが、比較的低い木(3〜5m程度)であれば作業を依頼できる場合があります。価格も抑えめなケースが多く、軽作業の延長として扱える点がメリットといえるでしょう。
ただし、危険が大きい高木伐採には向いておらず、重機が必要な作業は基本的に対応できません。
便利屋の特徴は以下の通りです。
⚫︎小規模伐採なら費用を抑えられる
⚫︎作業日程を調整しやすい
⚫︎不用品回収など他の作業も依頼できる
⚫︎高木伐採には向かない
⚫︎作業品質にバラつきがある
便利屋はコスト面で魅力がありますが、安全性や作業品質の面では専門業者に劣ることがあります。
特に杉はまっすぐ成長するため見た目以上に重い・倒れ方の制御が難しいなどの特徴があり、高さがある場合は便利屋では対応しきれないケースも。
また杉の伐採では防護服・チェーンソー・ロープワーク・伐倒方向の調整など専門知識が必要になるため、慣れない業者が作業すると事故につながる危険があります。
以下のような場合は便利屋への依頼は可能ですが、状況によっては伐採業者の方が総合的に安心です。
⚫︎高さ3〜5mの若い杉
⚫︎根元が細い
⚫︎隣家や道路に近くない
⚫︎切り株が残っても問題ない
便利屋は、簡易的な作業がメインであるなどの前提を理解し、少しでも危険がある場合は伐採業者を選ぶとよいでしょう。
杉の伐採にかかる費用相場の木の高さ別一覧表

杉の伐採費用相場
| 杉の高さ | 伐採費用の相場(1本) | 想定される作業内容 |
| 3〜5m | 5,000〜20,000円 | 手作業での伐採・搬出が可能 |
| 5〜8m | 15,000〜40,000円 | ロープを使った伐採、追加の処分費が必要 |
| 8〜10m | 30,000〜70,000円 | 技術者2名以上、チェーンソー使用 |
| 10〜15m |
50,000〜120,000円 | 高所作業車・足場・ロープワーク |
| 15〜20m | 100,000〜200,000円 | 部分伐採・吊り下ろし作業 |
| 20m以上 | 150,000〜300,000円以上 | クレーン車必須、危険木対応 |
たとえば10mを超える杉の場合、伐採時にそのまま倒すと家屋や隣家に接触する危険があるため、上部から少しずつ切り落として吊り下ろすなどの専門技術が使われます。
作業工程が追加されるほど、人件費・重機費が高くなり、相場も上昇するでしょう。
また、杉伐採では伐った後の処分費用も無視できません。杉は木材として価値がつきにくく、一般的にはチップ処理・焼却処分に回されます。
処分費が1本あたり数千〜1万円程度追加されるため、実際の見積もりは「伐採費+処分費+交通費」の合計となるケースが多く見られます。
さらに伐採後に抜根(根の掘り起こし)を希望する場合は、地中の根が広範囲に広がる杉では2〜5万円の追加費用がかかるケースも珍しくありません。
一覧表はあくまでも一般的な目安であり、実際の費用は「立地・危険度・重機搬入可否」によって変動する点に留意してください。
伐採費用が高くなるケース
伐採費用が上がる理由を理解しておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなるでしょう。
特に費用が高くなる主なケースとして、以下が挙げられます。
⚫︎木が10m以上の高木になっている
⚫︎家屋や電線に近く、吊り切り作業が必要
⚫︎クレーン車・高所作業車など重機を使わざるを得ない
⚫︎隣家との距離が近く、少しずつ切り下ろす必要がある
⚫︎杉の幹が太く、チェーンソーの種類が限定される
⚫︎敷地が狭く、重機の搬入が困難
⚫︎伐採後の処分費用が高い地域
⚫︎抜根(根の撤去)も同時に依頼する場合
伐採費用が上がる最大の要因は、危険度の高さです。杉はまっすぐ成長するため高さが出やすく、10mを超えると倒れる際の予測が難しくなります。
そのため専門業者はロープで方向を固定したり、幹の上部から吊りながら少しずつ切り落とす特殊伐採が基本。作業の工程が増えるほどスタッフ人数も増え、費用が上昇します。
また立地条件も大きな要因です。たとえば住宅密集地では、倒すスペースが確保できないため、クレーン車を道路に停めて吊り伐りする必要があります。
クレーン作業は1台あたり数万円の費用が追加されるため、見積もりが高めになるでしょう。
他にも杉の根は深く強いため、抜根作業には重機が必要になるケースも。地中に石やコンクリート基礎があると作業はさらに複雑になり、結果として追加費用が発生する原因になるでしょう。
最後に処分費用も見逃せません。杉はチップ化や焼却に回されることが多く、木材として売却できないことから処分費が必ず発生します。
伐採自体の費用が安くても、処分費を含めると合計額が高くなるケースがあるため、見積もりでは「伐採費+処分費+抜根費(必要なら)」を必ず確認しましょう。
杉の伐採後にかかる追加費用の内訳

特に杉は高さが出やすく、切り落とした後の木材量が多いため、処分費用・抜根・整地などの工程が必要になります。
初めて伐採業者へ依頼する方が、「なぜ見積もりが高いのか」「どこまでが基本料金なのか」と疑問を持つのは当然です。
ここでは杉伐採後にかかる主な追加費用について、それぞれの役割と費用相場を説明します。
解体処分にかかる費用
杉は一般的に木材として買い取りされるケースが少なく、丸太として売却できません。そのためチップ加工や焼却処理に回す必要があり、コストが発生します。
解体処分費の相場と特徴は以下の通りです。
⚫︎伐採物の量により 3,000〜15,000円 程度
⚫︎10m以上の杉はさらに費用が発生しやすい
⚫︎枝が多い杉は処分量が増え、コストが上がる
⚫︎トラックでの運搬費が加算される場合もある
⚫︎処分場までの距離によって料金が変動する
杉は針葉樹であるため枝が非常に多く、伐採後の廃棄物量が広葉樹に比べて多くなる傾向があります。
特に高さ10mを超える杉を切ると、軽トラック一杯分以上の枝葉と幹が発生するケースも少なくありません。
この大量の木材を処分場まで運搬するためには、トラック・人手・燃料費が必要であり、結果として処分費が追加されます。
また杉は木材としてリサイクルしにくい傾向があります。広葉樹は薪として需要がありますが、杉は燃え方が不安定で、焚き付けとしての需要はあるものの大量の木材を引き取ってもらえるケースは限られています。
そのため一般的にはチップ化処理または焼却処理となり、これらの加工費と運搬費が加算されるのが実情です。
伐採費用だけを見てしまうと、「思ったより高い見積もりになった」と感じる方が多いですが、実際には伐採よりも処分費の割合が大きいケースもあります。
特に枝が多い杉ほど処分が大変で、木の高さや太さに比例して追加費用が発生する点を理解しておくと、見積もり内容を冷静に判断できるでしょう。
抜根作業
抜根作業の特徴と費用は以下を参考にしてください。
⚫︎高さ3〜5mの杉…10,000〜30,000円
⚫︎高さ10m以上の杉…30,000〜80,000円以上
重機使用で追加料金が発生するケースには以下が挙げられます。
⚫︎地中の石・基礎に絡んでいると高額になりやすい
⚫︎担当者が危険木と判断した場合は人員追加
抜根費用が高くなる最大の理由は、杉の根が非常に強く広がる性質にあります。杉はまっすぐ成長しますが、その分根が深く地中に張り、周囲の土をしっかり掴んでいるのが特徴。そのため、小型の庭木のように簡単には抜けません。
特に樹齢が長い杉は、地中1〜2m以上に太い根が伸びており、手作業で対応するのは現実的ではないでしょう。
また庭の地中には水道管・ガス管・家の基礎部分など重要な設備が埋まっているケースがあり、根が絡んでいる場合は慎重な作業が求められます。
重機を使えない狭い場所では、ロープと手作業を併用した特殊抜根が必要となるため、追加料金が発生します。
抜根は必ずしも必要ではない作業ですが、以下のような場合は依頼がおすすめです。
⚫︎新しく木や花を植えたい
⚫︎庭を整地して駐車場にしたい
⚫︎根腐れによる悪臭を防ぎたい
抜根をするか迷う場合は、見積もり時に業者へ相談し、メリット・デメリットを確認するとよいでしょう。
整地費用
整地にかかる主な費用は以下の通りです。
⚫︎整地費用相場…5,000〜30,000円
⚫︎表土の入れ替えをする場合は追加費用
⚫︎重機使用が必要な場合は費用増
⚫︎伐採・抜根を同時依頼すると割引される場合もある
⚫︎雨上がりの柔らかい土では整地に時間がかかりやすい
整地は、伐採後の地面を平らにし、歩きやすく・再利用しやすい状態にするための作業です。
杉の抜根後は大きな穴が開いたり、周囲の土が崩れてデコボコした状態になりやすいため、そのままでは庭として使いにくくなります。
特に駐車場として利用したい場合や、花壇・菜園を作りたい場合には必須の作業です。
整地作業には、土の盛り直し・踏み固め・場合によっては砕石の敷き直しなどが含まれます。
高木だった杉の場合、根を取り除いた後の穴が大きいため、作業スタッフが入念に地盤を固める必要があります。
また整地の手間は土質によって変わります。水はけの悪い粘土質の土壌では、雑草対策や砂利敷きを追加で依頼する場合もあり、この際に費用が上がるケースも。
逆に、伐採・抜根と同時に依頼すると、トータルの工数が減るため割安になる可能性もあります。
「庭をどのように使うか」で整地の必要度は大きく変わるため、伐採の見積もり段階で業者と目的を共有しておくと、不要な追加費用を避けやすくなるでしょう。
杉の伐採に適した時期と避けるべき時期

時期によって木の状態や作業難易度、さらには処分費用まで変わるため、適切な時期を知り、余計なコストやリスクを避けましょう。
特に、庭に大きく育ち過ぎた杉は倒木リスクがあるため、判断を誤ると作業が延期になったり高額な見積もりにつながる可能性もあります。以下では、目的別に最適な伐採時期を見ていきましょう。
木材活用なら11月から12月がベスト
乾燥が進んだ木は加工しやすく、腐りにくく、木材チップにする際の品質も安定しやすいのが特徴です。
他にも11〜12月に伐採が向いている理由として以下が挙げられます。
⚫︎木の含水率が低く、木材として扱いやすい
⚫︎木材の変形・腐敗が起こりにくい
⚫︎冬は虫が少なく、安全に作業できる
⚫︎草木が枯れるため、足元が見やすく作業がスムーズ
⚫︎林業でも冬場が伐採のトップシーズン
11月〜12月は、林業全体でも主伐(木をまとめて伐る時期)が本格化する季節です。杉を含む多くの樹木は、冬に向けて養分を根に蓄えるため、幹や葉に含まれる水分量が下がります。
木の水分量が低いと、重さが軽くなり、クレーン作業やロープワークの安全性が高まるのもメリットです。
さらに杉伐採で発生する木材はチップ処理が主流ですが、乾燥している木ほど処理効率が良いため、処分費用を安く抑えられる可能性があります。
夏の伐採では含水率が高く、処理が難しくなることもあるため、同じ量の木材でも費用差が生まれやすくなります。
また冬は雑草が枯れて地面の状態が見えやすく、重機の配置や伐倒方向の判断がしやすい時期です。
杉は高さが出やすい木であるため、作業スペースの確保が重要ですが、冬場は視界がクリアなため高木伐採のリスクが少なくなります。
木材活用を考えていなくても、冬は総合的に伐採費用が下がりやすい傾向があり、見積もりがリーズナブルになることが多い点も覚えておくと良いでしょう。
花粉症対策なら7月から8月もあり
花粉症対策で夏に伐採するメリットは以下の通りです。
⚫︎翌年の花粉量を減らす可能性がある
⚫︎樹木内の花粉形成前なので、伐採時に花粉が舞いにくい
⚫︎夏は日照時間が長く作業が進みやすい
⚫︎冬前に抜根や土の処理まで終わらせられる
⚫︎スケジュールが取りやすいため業者の調整がしやすい
花粉は春に飛ぶものですが、元となる花芽は夏に作られるため、伐採を済ませておくのがおすすめ。
翌年の花粉飛散量を減らせるケースがありますよ。特に庭木の杉は、人工林とは異なり一本でも花粉量への影響が大きく、夏の伐採は花粉症対策としておすすめです。
また夏は業者のスケジュールに余裕が出るケースが多いため、見積もりが取りやすく、急ぎの案件にも対応してもらいやすい点も◎。
伐採自体は年中可能ですが、冬場は予約が混み合い、希望日に作業できない場合に注意しましょう。
夏のうちに伐採しておくことで、秋以降の整地・植栽・外構工事までスムーズに進められます。
ただし夏は雑草が多く、足元の視界が悪くなるため、高木伐採ではリスクが高まります。業者が草刈りを要する場合は追加料金が発生することもあるため、見積もり時に草刈りの有無を確認しておくと安心です。
春から夏の伐採が不向き
また虫の発生が増える時期でもあり、スタッフの安全性の観点から作業難易度が上がるかもしれません。
春〜初夏が不向きな理由をまとめると以下の通りです。
⚫︎木の含水率が高く、重く・倒れやすい
⚫︎新芽が成長し、枝が増えて作業が複雑化
⚫︎危険生物(蜂など)が増える
⚫︎雑草が茂り、重機配置が難しくなる
⚫︎雨が多い季節で作業日が延期されやすい
春になると樹木は一斉に水を吸い上げ、枝葉を伸ばし始めます。杉も例外ではなく、春〜初夏は1年で最も含水率が高い時期です。
含水率が高い木は非常に重く、伐倒時のコントロールが難しくなるため、住宅街での伐採には不向きとされています。
さらに、枝葉が急速に増えれば、作業員の視界が遮られたり、上部の剪定が難しくなるk脳性も。
また蜂の巣ができやすい季節でもあり、安全管理のために追加のスタッフや防護服が必要となるため費用が高くなる可能性もあります。
作業自体は可能ですが、春〜初夏は リスクや費用・作業日数の3点で依頼しにくい時期といえます。
そのため同じ条件の木でも、冬と比べて見積もりが高く出る点を覚えておきましょう。急ぎでなければ、夏または冬の伐採を選ぶのがおすすめです。
杉の伐採業者を選ぶ際のチェックポイント

特に杉は高さが出やすく、一般の庭木よりも伐採に専門知識が求められるため、慎重な業者選びが欠かせません。特に以下の点を重視しながら選びましょう。
⚫︎杉伐採の実績と口コミを確認する
⚫︎見積もりが明瞭であること
⚫︎対応可能な作業範囲を確認する
⚫︎保険加入の有無を必ず聞く
⚫︎必ず複数社から相見積もりを取る
ここでは失敗しないために必ず確認しておきたい 5つの重要ポイント を解説します。
杉伐採の実績と口コミを確認する
経験が浅い業者だと、安全な倒し方の判断を誤り、家屋や隣家に被害を及ぼす可能性があります。そのため、実績数・過去の施工事例・利用者の口コミを丁寧に確認しましょう。
確認したいポイントを以下にまとめます。
⚫︎杉伐採の実績件数
⚫︎高木(10m以上)伐採の事例があるか
⚫︎吊り切り・特殊伐採の経験があるか
⚫︎Google口コミや比較サイトの評価
⚫︎苦情対応の丁寧さ
実績と口コミを確認する理由は、杉伐採が見た目以上に危険な作業だからです。杉は直立性が高く、幹が太くて重い木であるため、倒す方向をほんの少しでも間違えると大きな事故につながります。
実績豊富な業者は、伐倒方向の判断やクレーン作業の効率化など、安全かつ迅速に作業を行うための現場経験を持っています。
また口コミには、作業の丁寧さ・料金の分かりやすさ・作業後の清掃など、公式サイトでは分からない情報が多く含まれています。
特に以下の内容は要チェックです。
⚫︎約束の時間に来ない
⚫︎見積もりと請求額が違う
⚫︎伐採後の掃除が雑
⚫︎近隣への配慮が足りない
上記の問題が多い業者は避けるべきです。逆に「高木伐採の事例写真が多い」「利用者の満足度が高い」などの業者は信頼度が高く、安心して依頼できます。
見積もりが明瞭であること
逆に、料金の内訳が曖昧な業者は、追加請求や不明瞭な費用トラブルにつながるケースもあるため注意してください。
分かりやすい見積もりに含まれる項目は以下の通りです。
⚫︎伐採費用(高さ・太さに基づく)
⚫︎処分費用(枝葉・幹の量)
⚫︎重機使用料(クレーン・高所作業車)
⚫︎スタッフ人数・作業時間
⚫︎交通費
⚫︎抜根費用の有無
見積もりが明確でないと、作業後に突然費用を請求されるケースがあります。特に杉の伐採はチップ処理・運搬費用がかさむため、処分費の記載漏れや後出し請求が多い分野です。見積もり時には、以下の点を必ず確認しましょう。
⚫︎「追加費用が発生する条件」を事前に説明しているか
⚫︎「伐採費のみの表示で処分費が別請求」になっていないか
⚫︎「消費税込み」で表示されているか
また優良業者は現地調査を必ず行い、木の状態や周囲との距離を確認したうえで見積もりを出します。
写真だけで見積もりを出す業者は、作業当日に危険木扱いを理由に料金を上げる可能性があるため注意しましょう。
最も安心なのは、「費用の内訳」「追加料金の条件」「作業内容」がはっきりと書かれた見積書を提示してくれる業者です。
対応可能な作業範囲を確認する
業者がどこまで対応可能なのかを事前に確認しておくことで、後から別業者を追加する手間を省けます。
事前に確認すべき作業範囲は以下の通りです。
⚫︎高木(10m以上)の伐採
⚫︎吊り伐り・特殊伐採の対応
⚫︎抜根(根の除去)
⚫︎解体処分・チップ化作業
⚫︎整地・砂利敷きなどの追加作業
⚫︎クレーン作業の可否
伐採作業は現場の状況によって難易度が大きく変わります。特に狭い住宅街では、木を真横に倒すスペースが取れず、上部から少しずつ切って吊り下ろす「特殊伐採」が必須になるケースも。
特殊伐採に対応できない業者は工事を断るケースも多く、依頼者が別業者を探さなければならない可能性もあります。
また抜根や整地は伐採とは別工種になるため、対応できない業者も存在します。伐採後に庭を利用したい人(駐車場化・花壇作りなど)は、最初から「一括対応」の業者を選ぶとよいでしょう。
対応範囲が広い業者は、総額が安くなる傾向があります。複数業者を別々に依頼すると、交通費や人件費が二重に発生するため、最初の段階で作業範囲を確認するのが節約にもつながるでしょう。
保険加入の有無を必ず聞く
保険未加入の業者に依頼すると、万が一のときに依頼者の負担が大きくなりますよ。
保険加入で確認すべき点として、以下に注目してみましょう。
⚫︎損害賠償保険の加入状況
⚫︎補償金額(最低1億円が望ましい)
⚫︎作業スタッフが労災保険に加入しているか
⚫︎事故時の対応・補償の範囲
⚫︎「無保険」を誤魔化していないか
自然災害や老朽化による倒木事故が増える中、伐採作業の事故リスクは年々注目されています。特に高さ10mを超える杉は重量も重く、伐倒方向がわずかにズレるだけで大事故につながるかもしれません。
万が一、作業中の木が家屋や車に倒れた場合、損害賠償は数百万円〜数千万円規模になるため特に注意してください。
保険に加入していない業者は、事故時の補償が曖昧になったり、依頼者の自己負担になるケースもあります。
安い業者を選んだ結果、高額の損害を抱えるなどの最悪の事態を避けるためにも、見積もり時に必ず保険加入を確認しましょう。
優良業者は保険加入を積極的に公表しています。逆に、保険の質問に曖昧な回答をする業者は避けるべきでしょう。
必ず複数社から相見積もりを取る
相見積もりのメリットは以下の通りです。
⚫︎市場相場を正確に把握できる
⚫︎過剰な見積もりを避けられる
⚫︎追加費用の有無を比較できる
⚫︎作業内容の違いが分かる
⚫︎交渉がスムーズになり、割引を受けられることも
相見積もりを取らずに1社だけで決めてしまうと、相場より高い料金を支払ってしまう可能性があります。
特に杉伐採は重機・人員・処分費など費用項目が多く、業者によって得意不得意や料金体系が異なるため、差が出やすい分野です。
相見積もりを取る際は、次の項目を比較しましょう。
⚫︎作業内容(伐採のみ・処分込み・抜根込み)
⚫︎木の高さ・太さ
⚫︎作業条件(道路の幅・隣家の距離)
⚫︎希望日程
上記を同じ条件で依頼することで、正確な比較ができます。
また相見積もりに快く応じる業者は信頼性が高く、対応も丁寧です。逆に、相見積もりを嫌がる業者や、急かして契約を迫ってくる点に注意しましょう。
杉の伐採でよくある質問

杉の伐採は自分でできますか?
また伐採にはチェーンソー、防護服、ロープワークなどの専門知識が必要になります。
自力伐採が危険な理由として、以下の点も覚えておきましょう。
⚫︎倒木の方向を制御する技術が必要
⚫︎チェーンソーの扱いに慣れていないとケガをしやすい
⚫︎枝が多く、高さがあるためバランスが崩しやすい
⚫︎電線・家屋・車への衝突リスクが高い
⚫︎処分費用や運搬の手間も自分で負担する必要がある
杉は、庭木の中でも特に高さが出やすく、7〜10年で数m、20年近く経つと10m以上の高木になるケースも珍しくありません。
高木伐採では、木の重心を正確に見極め、倒れる方向をロープで調整しながら慎重に作業する必要があります。
状況は専門業者が数百件以上の現場経験で培っている技術であり、初心者が安全に行うのは難しいでしょう。
また伐採後に発生する大量の枝葉・幹の処分も大きな負担になります。杉は木材としての価値が低く、市のごみ回収では持ち込みが制限される場合が多いため、結局は処分業者へ依頼が必要になります。
チェーンソーの誤操作による事故や落下による骨折・倒木による近隣トラブルは実際に多く発生しており、自治体も注意喚起しています。
安全性・費用・時間を考えると、結局は最初から伐採業者へ任せた方が確実でリスクがないでしょう。
杉の伐採に補助金は使えますか?
補助金が適用される可能性があるケースは以下の通りです。
⚫︎危険木として自治体が認定した場合
⚫︎通学路・公共道路沿いにあり、倒木リスクがある
⚫︎防災計画の一環として地域で整備対象になっている
⚫︎森林整備の補助金(山林所有者向け)が使えるケース
個人宅の庭に生えている杉は、基本的に私有地の管理に分類されるため、自治体の補助金制度の対象外になることがほとんどです。しかし例外として以下のようなケースでは、補助金が認められることがあります。
⚫︎自宅の杉が倒木の危険があり、役所の調査で「危険木」に指定された
⚫︎公道に大きく枝が越境し、通行の妨げになっている
⚫︎大規模災害時に危険と判断され、市が補助する制度がある
⚫︎山林所有者が杉林を伐採する際に使える林業系補助金
また「空き家対策事業」の一環で庭木伐採に補助を出している自治体もあります。ただし、制度は市区町村によって大きく異なるため、事前に役所へ問い合わせる必要があります。
「庭の杉を切りたい」という一般的なケースで補助金が使われることは少ないため、過度な期待を持たず、補助金は“使えたらラッキー”程度に考えるのが現実的と言えます。
杉を伐採した後の処分方法は?
杉の処分方法として、以下の方法があります。
⚫︎伐採業者に処分まで依頼する(最も一般的)
⚫︎自治体の粗大ごみ処理場へ自己搬入する(量の制限あり)
⚫︎薪・チップとして再利用する(少量の枝葉向け)
杉の木は、枝が細く軽い一方で非常に量が多く、伐採後は軽トラック数台分の木材が発生することがあります。
このため一般家庭で処理を行うのは、現実的ではありません。自治体の処分場へ持ち込む場合でも、長さ制限・太さ制限・量制限があるため、持ち込み不可となるケースも多く見られます。
また杉は含水率が高く腐りやすいため、薪として利用するには乾燥期間が必要です。庭で保管スペースを確保できない場合は不向きです。チップ化して庭に敷く方法もありますが、大量の木材を家庭用チッパーで処理するのはほぼ不可能であり、業務用の機械が必要になります。
杉の伐採ならお庭の大将にお任せください

「お庭の大将」では、杉伐採の実績が豊富なスタッフが、高所作業・特殊伐採・抜根作業までワンストップで対応します。
⚫︎10m以上の高木伐採も対応
⚫︎クレーン使用の特殊伐採も可能
⚫︎抜根・整地・処分までトータル対応
⚫︎追加費用のない安心の見積もり
⚫︎全国対応でスケジュール調整も柔軟
安全第一で作業を行い、近隣への配慮も徹底しています。「杉が大きくなりすぎて不安」「隣家に倒れそう」「花粉症対策で切りたい」など、どんな相談もお気軽にお問い合わせください。