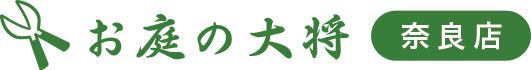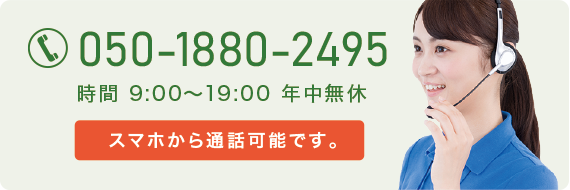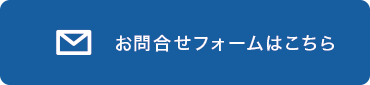伸びすぎた松の剪定はいつ?
自分でできる方法と業者に頼むべき判断基準を紹介!
自分でできる方法と業者に頼むべき判断基準を紹介!

松の枝葉が伸びすぎて形が崩れ、「どう剪定すればいいのか分からない」と悩んでいませんか?
放置すると見た目が悪くなるだけでなく、倒木や病害虫の原因にもなります。特に高さがある松は、自分で切ると危険が伴うケースも。
松の剪定は他の庭木よりも繊細で、時期・方法・枝の見極めを誤ると、樹勢が衰えたり枯れてしまう恐れもあります。
しかしポイントを押さえれば初心者でも自分で整えられ、手入れをしっかりと行えば松の美しい樹形を何十年も保てます。
この記事では、剪定の時期・方法・費用相場までをわかりやすく解説します。最後まで読めば、安全かつ美しい庭づくりの方法が分かりますよ。
放置すると見た目が悪くなるだけでなく、倒木や病害虫の原因にもなります。特に高さがある松は、自分で切ると危険が伴うケースも。
松の剪定は他の庭木よりも繊細で、時期・方法・枝の見極めを誤ると、樹勢が衰えたり枯れてしまう恐れもあります。
しかしポイントを押さえれば初心者でも自分で整えられ、手入れをしっかりと行えば松の美しい樹形を何十年も保てます。
この記事では、剪定の時期・方法・費用相場までをわかりやすく解説します。最後まで読めば、安全かつ美しい庭づくりの方法が分かりますよ。
伸びすぎた松を今すぐ剪定すべき3つの理由
庭のシンボルとして人気の高い松は、放置していると枝葉が伸びすぎてしまい、見た目だけでなく安全面や周囲にも悪影響を及ぼします。
とくに3年以上剪定をしていない場合、倒木や病害虫など深刻な問題が起こる可能性も。ここでは伸びすぎた松を今すぐ剪定すべき3つの理由を、具体的なリスクとともに解説します。
とくに3年以上剪定をしていない場合、倒木や病害虫など深刻な問題が起こる可能性も。ここでは伸びすぎた松を今すぐ剪定すべき3つの理由を、具体的なリスクとともに解説します。
景観を損ね、近隣トラブルの原因になる
剪定を怠ると、松の枝が四方に広がり、庭の景観が崩れてしまいます。また隣家の敷地や道路にはみ出してしまうことで、思わぬトラブルを招くケースも少なくありません。
伸びすぎた松が引き起こす代表的なトラブルとして以下が挙げられます。
⚫︎隣家の庭や屋根に枝が侵入し、落葉や松ヤニで迷惑をかける
⚫︎目隠し代わりだった松が逆に「日照の妨げ」になる
⚫︎落ちた枝葉が排水溝を詰まらせる
⚫︎樹形が乱れ、庭全体の印象が暗くなる
トラブルを放置すると管理不足と見なされ、自治体から指導を受けるケースもあります。
松は生長力が強いため、1年で20〜30cm以上伸びるケースもあるため、こまめに手入れを行いましょう。
とくにY字型の枝が重なってくると、樹形が不格好になり、せっかくの和風庭園の美しさが損なわれます。早めの剪定が、トラブル回避に繋がりますよ。
伸びすぎた松が引き起こす代表的なトラブルとして以下が挙げられます。
⚫︎隣家の庭や屋根に枝が侵入し、落葉や松ヤニで迷惑をかける
⚫︎目隠し代わりだった松が逆に「日照の妨げ」になる
⚫︎落ちた枝葉が排水溝を詰まらせる
⚫︎樹形が乱れ、庭全体の印象が暗くなる
トラブルを放置すると管理不足と見なされ、自治体から指導を受けるケースもあります。
松は生長力が強いため、1年で20〜30cm以上伸びるケースもあるため、こまめに手入れを行いましょう。
とくにY字型の枝が重なってくると、樹形が不格好になり、せっかくの和風庭園の美しさが損なわれます。早めの剪定が、トラブル回避に繋がりますよ。
台風や強風による倒木リスクが高まる
樹高が高く枝が密集した松は、風を受けやすく倒木しやすい恐れがあります。特に根の浅い種類や古木では、風圧に耐えられず倒れるかもしれません。
倒木リスクを高める原因には以下が挙げられます。
⚫︎幹の太さに対して枝葉が過密
⚫︎透かし剪定をしておらず、風通しが悪い
⚫︎地盤が緩んでいる
⚫︎枝先が電線や建物に近づいている
倒木事故は、自宅だけでなく隣家や通行人に損害を与える危険があり、損害賠償の対象となるケースも。
特に近年の台風シーズンでは「風速30m/s」を超える日も増えており、倒木被害のニュースも後を絶ちません。
風通しを良くする透かし剪定や、不要枝の除去を定期的に行えば、枝への風圧を分散させつつ、トラブルリスクを大幅に減らせるでしょう。
倒木リスクを高める原因には以下が挙げられます。
⚫︎幹の太さに対して枝葉が過密
⚫︎透かし剪定をしておらず、風通しが悪い
⚫︎地盤が緩んでいる
⚫︎枝先が電線や建物に近づいている
倒木事故は、自宅だけでなく隣家や通行人に損害を与える危険があり、損害賠償の対象となるケースも。
特に近年の台風シーズンでは「風速30m/s」を超える日も増えており、倒木被害のニュースも後を絶ちません。
風通しを良くする透かし剪定や、不要枝の除去を定期的に行えば、枝への風圧を分散させつつ、トラブルリスクを大幅に減らせるでしょう。
病害虫の発生源となり周囲の植物にも悪影響
枝が混み合うと風通しや日当たりが悪くなり、湿気がこもって病害虫が発生しやすくなります。特に松にはマツカレハやマツノザイセンチュウなどの害虫がつきやすく、放置すれば木が枯れる恐れも…。
よくある松の病害虫と特徴として、以下を知っておくとよいでしょう。
よくある松の病害虫と特徴として、以下を知っておくとよいでしょう。
| 病害虫名 | 被害内容 | 発生時期 |
| マツカレハ | 幼虫が葉を食い荒らす | 春〜初夏 |
| マツノザイセンチュウ | 樹液を吸い上げ、枯死に至る | 夏〜秋 |
| カイガラムシ | 樹皮や枝に付着して樹勢を弱める | 通年 |
剪定を怠ると害虫が枝の奥に潜み、他の植物にも感染を広げてしまいます。また松ヤニのにおいに引き寄せられた害虫が大量発生し、駆除に高額な費用がかかるケースも。定期的な剪定と薬剤散布により、害虫の温床を断ちつつ、松本来の健康な姿を保てますよ。
伸びすぎた松の剪定に最適な時期はいつ?
松は日本庭園を象徴する美しい樹木ですが、成長が早く、放置すると枝葉が密集して風通しが悪くなります。
見た目を保ちつつ健康を維持するためには、剪定の時期を正しく選ぶのがコツ。松の剪定は年に2回行うのがベストで、季節ごとに目的と方法が異なります。
ここでは春・秋・年間管理のポイント、そして避けるべき時期について詳しく解説します。
見た目を保ちつつ健康を維持するためには、剪定の時期を正しく選ぶのがコツ。松の剪定は年に2回行うのがベストで、季節ごとに目的と方法が異なります。
ここでは春・秋・年間管理のポイント、そして避けるべき時期について詳しく解説します。
春のミドリ摘みが基本(4月〜6月)
春のミドリ摘みは、松の新芽を手で摘み取る作業です。4月から6月にかけて行うことで、樹形を整えながら生長をコントロールできます。
ミドリ摘みの効果として以下が挙げられます。
⚫︎新芽の伸びを抑えて全体のバランスを整える
⚫︎枝の間引きを行い、風通しを改善する
⚫︎翌年の芽吹きを促進する
⚫︎樹形を美しく保ち、庭全体の印象を明るくする
春に行うミドリ摘みは、松が最も活動的に成長しているタイミングです。芽を適度に摘むと、不要枝を減らし、枝葉の密集を防ぎます。
初心者の場合は、枝先の新芽を3分の1程度残すことを意識すると失敗しにくいででしょう。また手で摘むのが基本ですが、高い位置や太い枝はハサミを使うとやりやすいですよ。
ミドリ摘みは松の生命力を利用した自然な剪定です。強く切りすぎると枯れ枝や樹形崩れの原因になるため、全体を見ながら丁寧に行ってください。
ミドリ摘みの効果として以下が挙げられます。
⚫︎新芽の伸びを抑えて全体のバランスを整える
⚫︎枝の間引きを行い、風通しを改善する
⚫︎翌年の芽吹きを促進する
⚫︎樹形を美しく保ち、庭全体の印象を明るくする
春に行うミドリ摘みは、松が最も活動的に成長しているタイミングです。芽を適度に摘むと、不要枝を減らし、枝葉の密集を防ぎます。
初心者の場合は、枝先の新芽を3分の1程度残すことを意識すると失敗しにくいででしょう。また手で摘むのが基本ですが、高い位置や太い枝はハサミを使うとやりやすいですよ。
ミドリ摘みは松の生命力を利用した自然な剪定です。強く切りすぎると枯れ枝や樹形崩れの原因になるため、全体を見ながら丁寧に行ってください。
秋の透かし剪定ともみあげ(11月〜12月)
秋は透かし剪定と、もみあげの時期。夏の間に伸びた枝を整理し、不要な葉を取り除く作業を行います。
秋の剪定では以下の作業を行いましょう。
⚫︎重なり合う枝やY字型に分かれた不要枝を除去
⚫︎枯れ枝・病害虫の被害枝を切り落とす
⚫︎古い葉(もみ)を手でもみ落とす
⚫︎全体の樹形を整え、冬越しに備える
透かし剪定によって風通しが改善し、病害虫の発生を防げます。特にマツカレハやマツノザイセンチュウなどは枝の密集部に発生しやすいため、秋の剪定での予防がおすすめです。
また、もみあげは枝の内部にたまった古い葉を手でもみ取る作業で、見た目もすっきりとした印象に変わります。もみあげにより、翌春の新芽が健康に伸びる土台を作れますよ。
松は寒さに強いですが、12月中旬以降の厳冬期に入ると剪定によるダメージが残りやすいため、作業は11月〜12月初旬がおすすめです。
秋の剪定では以下の作業を行いましょう。
⚫︎重なり合う枝やY字型に分かれた不要枝を除去
⚫︎枯れ枝・病害虫の被害枝を切り落とす
⚫︎古い葉(もみ)を手でもみ落とす
⚫︎全体の樹形を整え、冬越しに備える
透かし剪定によって風通しが改善し、病害虫の発生を防げます。特にマツカレハやマツノザイセンチュウなどは枝の密集部に発生しやすいため、秋の剪定での予防がおすすめです。
また、もみあげは枝の内部にたまった古い葉を手でもみ取る作業で、見た目もすっきりとした印象に変わります。もみあげにより、翌春の新芽が健康に伸びる土台を作れますよ。
松は寒さに強いですが、12月中旬以降の厳冬期に入ると剪定によるダメージが残りやすいため、作業は11月〜12月初旬がおすすめです。
年1回で済ませるなら初夏がおすすめ
「忙しくて年2回は難しい」という方は、5月〜6月頃の初夏に1回の剪定でまとめるのがおすすめです。5月〜6月頃なら、春のミドリ摘みと秋の透かし剪定の中間的な効果が得られるでしょう。
年1回剪定のメリットとして、以下の点が挙げられます。
⚫︎作業負担が少なく、初心者にも取り組みやすい
⚫︎生長が活発な時期のため、樹木への負担が少ない
⚫︎病害虫の被害が出にくい
⚫︎ミドリ摘み・樹形整えを同時に行える
一方で、年1回しか剪定しない場合は、全体を軽く仕上げるのが大切です。太い枝を一気に切ると樹勢が弱まり、翌年の発芽に悪影響を与えます。できるだけ透かすように剪定し、自然な樹形を意識しましょう。
業者に依頼する場合も、この時期は剪定依頼が集中しやすく予約が取りにくいので、早めの予約がおすすめです。
年1回剪定のメリットとして、以下の点が挙げられます。
⚫︎作業負担が少なく、初心者にも取り組みやすい
⚫︎生長が活発な時期のため、樹木への負担が少ない
⚫︎病害虫の被害が出にくい
⚫︎ミドリ摘み・樹形整えを同時に行える
一方で、年1回しか剪定しない場合は、全体を軽く仕上げるのが大切です。太い枝を一気に切ると樹勢が弱まり、翌年の発芽に悪影響を与えます。できるだけ透かすように剪定し、自然な樹形を意識しましょう。
業者に依頼する場合も、この時期は剪定依頼が集中しやすく予約が取りにくいので、早めの予約がおすすめです。
避けるべき時期と理由
松の剪定に適さないのは、真夏と真冬です。剪定を避けるべき理由として以下が挙げられます。
| 時期 | 理由 | 影響 |
| 真夏(7〜8月) | 樹液の流れが活発で、剪定傷から松ヤニが大量に出る |
枝が弱りやすく、病気を誘発 |
| 真冬(1〜2月) | 気温が低く、切り口が乾燥して枯れ込みやすい | 枝枯れや芽の萎縮の原因 |
真夏の剪定は、切り口から虫が侵入しやすく、マツノザイセンチュウの感染源になることも。
一方で、真冬は寒風で樹皮が傷み、翌春の新芽が出にくくなります。正しい時期に剪定を行えば、松の寿命を延ばし、美しい樹形を長く保てるでしょう。
一方で、真冬は寒風で樹皮が傷み、翌春の新芽が出にくくなります。正しい時期に剪定を行えば、松の寿命を延ばし、美しい樹形を長く保てるでしょう。
伸びすぎた松の剪定方法!初心者でもできる
伸びすぎた松を放置すると、見た目が乱れるだけでなく、病害虫や倒木リスクも高まります。
しかし「松の剪定は難しい」「自分でやっても大丈夫?」と不安に感じる人も多いかもしれません。実は、ポイントを押さえれば初心者でも剪定は可能です。
ここでは、道具の準備から具体的な枝の切り方まで、わかりやすく解説します。
しかし「松の剪定は難しい」「自分でやっても大丈夫?」と不安に感じる人も多いかもしれません。実は、ポイントを押さえれば初心者でも剪定は可能です。
ここでは、道具の準備から具体的な枝の切り方まで、わかりやすく解説します。
剪定前に揃えておくべき道具一覧
まずは、剪定作業を安全かつスムーズに行うために、必要な道具を揃えましょう。
剪定に必要な基本道具
剪定に必要な基本道具
| 道具名 | 用途 | 注意点 |
| 剪定ばさみ | 細い枝・若い芽を切る |
刃が鋭いものを選ぶ |
| のこぎり | 太い枝を切る | 目詰まり防止にこまめな掃除を |
| 脚立 | 高所作業に使用 | 安定性が高いものを選ぶ |
| 手袋・保護メガネ | 安全対策 | 松ヤニや枝の破片から手や目を守る |
| ブルーシート | 枝葉の回収用 | 作業後の掃除がラクになる |
| 消毒液・癒合剤 | 切り口の保護 | 病害虫の侵入防止に役立つ |
道具をそろえれば、無理なく安全に剪定作業を進められます。特に松ヤニは手や服に付きやすいため、厚手の手袋と作業服を用意しておくと安心です。
また脚立の転倒防止や足場の確保など、安全面の配慮も欠かせません。初心者こそ道具を意識しましょう。
また脚立の転倒防止や足場の確保など、安全面の配慮も欠かせません。初心者こそ道具を意識しましょう。
理想の樹形をイメージする
松の剪定では、ただ枝を切るだけではなく、仕上がりのイメージを考えるのがポイントです。剪定前に考えるべきポイントとして、以下の点を意識しましょう。
⚫︎樹形のバランス(上部は細く、下部は広く)
⚫︎枝の重なりや方向性(内向き枝は整理)
⚫︎風通しと日当たり(密集部を透かす)
⚫︎家や庭全体との調和(建物の高さとのバランス)
松は「自然樹形の美」を重視する樹木です。左右対称よりも、自然な流れを感じる逆三角形のシルエットを目指すと見栄えが良くなります。
また成長方向をイメージして不要な枝を切ることで、翌年以降の手入れも楽になります。最初に全体像をつかんでから作業に入ると、仕上がりに一貫性が生まれるでしょう。
⚫︎樹形のバランス(上部は細く、下部は広く)
⚫︎枝の重なりや方向性(内向き枝は整理)
⚫︎風通しと日当たり(密集部を透かす)
⚫︎家や庭全体との調和(建物の高さとのバランス)
松は「自然樹形の美」を重視する樹木です。左右対称よりも、自然な流れを感じる逆三角形のシルエットを目指すと見栄えが良くなります。
また成長方向をイメージして不要な枝を切ることで、翌年以降の手入れも楽になります。最初に全体像をつかんでから作業に入ると、仕上がりに一貫性が生まれるでしょう。
不要な枝を見極めるポイント
剪定で最も大切なのは、残す枝と切る枝の判断です。無計画に切ってしまうと、松が弱って枯れる原因になるため注意しましょう。不要枝の見極め方は以下を参考にしてくださいね。
⚫︎下向きに伸びた枝(重く垂れて景観を崩す)
⚫︎内向き枝(幹に絡み合い風通しを悪化)
⚫︎交差枝・重なり枝(互いに傷をつけ合う)
⚫︎枯れ枝・徒長枝(勢いよく伸びて樹形を乱す)
⚫︎幹の根元から出た“ひこばえ”
不要な枝を整理すると、光と風が通りやすくなり、病害虫の予防にもつながります。特に透かし剪定(枝を間引く作業)を意識すると、全体のバランスが整いやすくなるでしょう。
切るときは枝の根元からすっきり落とし、切り口には癒合剤を塗布して木の回復を助けるのがコツです。
⚫︎下向きに伸びた枝(重く垂れて景観を崩す)
⚫︎内向き枝(幹に絡み合い風通しを悪化)
⚫︎交差枝・重なり枝(互いに傷をつけ合う)
⚫︎枯れ枝・徒長枝(勢いよく伸びて樹形を乱す)
⚫︎幹の根元から出た“ひこばえ”
不要な枝を整理すると、光と風が通りやすくなり、病害虫の予防にもつながります。特に透かし剪定(枝を間引く作業)を意識すると、全体のバランスが整いやすくなるでしょう。
切るときは枝の根元からすっきり落とし、切り口には癒合剤を塗布して木の回復を助けるのがコツです。
Y字型を意識した枝の整え方
松の剪定では、Y字型が理想の枝形とされています。Y字型は幹から分かれた2本の枝がバランス良く広がる形で、自然な立体感を生み出しますよ。
Y字型の作り方の基本は以下を抑えましょう。
⚫︎枝先を軽く透かし、空間を意識する
⚫︎同じ方向に伸びる枝は1本残して他を切る
⚫︎上向きの枝は短く、下向きの枝はやや長く調整
⚫︎枝の重なりを減らし、太陽光が均等に当たるようにする
剪定中は、全体を何度も離れて見直すことがポイントです。近くで見ていると切りすぎに気づきにくいため、数歩下がって全体のラインを確認すると失敗を防げます。
また松は1年で新芽がぐんと伸びるため、形を整える剪定を続けることで、徐々に理想的な樹形へ近づきます。
Y字型の作り方の基本は以下を抑えましょう。
⚫︎枝先を軽く透かし、空間を意識する
⚫︎同じ方向に伸びる枝は1本残して他を切る
⚫︎上向きの枝は短く、下向きの枝はやや長く調整
⚫︎枝の重なりを減らし、太陽光が均等に当たるようにする
剪定中は、全体を何度も離れて見直すことがポイントです。近くで見ていると切りすぎに気づきにくいため、数歩下がって全体のラインを確認すると失敗を防げます。
また松は1年で新芽がぐんと伸びるため、形を整える剪定を続けることで、徐々に理想的な樹形へ近づきます。
枯れ枝・古葉の取り除き方
松は常緑樹ですが、古い葉や枯れ枝を放置すると、通気性が悪くなり病害虫が発生しやすくなります。剪定時には、「もみあげ」と呼ばれる古葉の除去を行いましょう。
枯れ枝・古葉を取る際のポイントは以下の通りです。
⚫︎枯れ枝は根元から切り落とす
⚫︎手でもみ取るように古葉を落とす(もみあげ)
⚫︎風通しを意識して内部の葉も軽く整理
⚫︎作業後は枝や葉をきれいに片づけて病害虫を防止
古葉は枝の内側に溜まりやすく、湿気の温床になります。そのため秋の透かし剪定の時期に一緒に行うとよいでしょう。
また落とした葉を放置するとマツカレハなどの害虫が卵を産み付けるため、ブルーシートで受けてすぐに処分してしまうのがおすすめ。枯れ枝の除去は、松の健康維持だけでなく、美しい樹形を保つための基本です。
枯れ枝・古葉を取る際のポイントは以下の通りです。
⚫︎枯れ枝は根元から切り落とす
⚫︎手でもみ取るように古葉を落とす(もみあげ)
⚫︎風通しを意識して内部の葉も軽く整理
⚫︎作業後は枝や葉をきれいに片づけて病害虫を防止
古葉は枝の内側に溜まりやすく、湿気の温床になります。そのため秋の透かし剪定の時期に一緒に行うとよいでしょう。
また落とした葉を放置するとマツカレハなどの害虫が卵を産み付けるため、ブルーシートで受けてすぐに処分してしまうのがおすすめ。枯れ枝の除去は、松の健康維持だけでなく、美しい樹形を保つための基本です。
伸びすぎた松を小さくする方法
松の木は成長力が強く、放置すると枝が広がり、あっという間に手が届かないほどの高さになります。
しかし「一気に小さくしたい」と思っても、誤った剪定をすると木が弱り、最悪の場合は枯れてしまうケースも。
ここでは、伸びすぎた松を健康を保ちながら小さくする方法を3つのステップでわかりやすく解説します。
しかし「一気に小さくしたい」と思っても、誤った剪定をすると木が弱り、最悪の場合は枯れてしまうケースも。
ここでは、伸びすぎた松を健康を保ちながら小さくする方法を3つのステップでわかりやすく解説します。
大胆に切っても大丈夫?葉を残す切り方
松を小さくしたいからといって、太い枝を一気に切り落とすのはNGです。松は葉に光を当てて養分を作るため、葉を残さずに剪定すると回復できずに枯れてしまう可能性があります。
そのため、大胆に切るのではなく葉を残して切るのを意識するとよいでしょう。小さく見せるためのカットのコツとして、以下の方法があります。
⚫︎枝の外側にある葉を1〜2芽残すように切る
⚫︎枝の途中で切る場合は、葉のある部分の少し上でカットする
⚫︎枝元からすべて切るのではなく、段階的に短くする
⚫︎切り口は斜めにし、水分がたまりにくくする
枝を短くしても、残した葉が光合成を行い、新しい芽の生育を支えます。また切る位置を工夫すれば自然な形を保ちながら樹形を整えられますよ。
枝を切るときは、必ず幹の方向に向かって流れるようなラインを意識しましょう。外観の美しさだけでなく、風通しも良くなり、病害虫の発生リスクを減らせます。
そのため、大胆に切るのではなく葉を残して切るのを意識するとよいでしょう。小さく見せるためのカットのコツとして、以下の方法があります。
⚫︎枝の外側にある葉を1〜2芽残すように切る
⚫︎枝の途中で切る場合は、葉のある部分の少し上でカットする
⚫︎枝元からすべて切るのではなく、段階的に短くする
⚫︎切り口は斜めにし、水分がたまりにくくする
枝を短くしても、残した葉が光合成を行い、新しい芽の生育を支えます。また切る位置を工夫すれば自然な形を保ちながら樹形を整えられますよ。
枝を切るときは、必ず幹の方向に向かって流れるようなラインを意識しましょう。外観の美しさだけでなく、風通しも良くなり、病害虫の発生リスクを減らせます。
高さを抑えるための芯止め
松を小さくするうえで重要なのが「芯止め」です。これは幹の一番上の頂芽(ちょうが)を止める作業で、木の高さを抑えるのに使えます。
芯止めのやり方は以下の通りです。
⚫︎幹の頂点にある勢いの強い枝(リーダー枝)を確認
⚫︎その枝を根元からカットし、上への生長を止める
⚫︎代わりに側枝(横に伸びた枝)を残して、新たな頂部として誘導する
⚫︎切り口には癒合剤(切り口保護剤)を塗って枯れ防止
芯止めを行うと、木が横方向にエネルギーを使うようになり、全体が低く締まった形になります。ただし、芯止めを強くやりすぎると、バランスが崩れやすくなるため注意が必要です。
芯止めを行うタイミングは「春のミドリ摘み」または「秋の透かし剪定」と合わせるのがベスト。成長期に行えば樹勢が安定し、自然に高さを抑えられます。
芯止めのやり方は以下の通りです。
⚫︎幹の頂点にある勢いの強い枝(リーダー枝)を確認
⚫︎その枝を根元からカットし、上への生長を止める
⚫︎代わりに側枝(横に伸びた枝)を残して、新たな頂部として誘導する
⚫︎切り口には癒合剤(切り口保護剤)を塗って枯れ防止
芯止めを行うと、木が横方向にエネルギーを使うようになり、全体が低く締まった形になります。ただし、芯止めを強くやりすぎると、バランスが崩れやすくなるため注意が必要です。
芯止めを行うタイミングは「春のミドリ摘み」または「秋の透かし剪定」と合わせるのがベスト。成長期に行えば樹勢が安定し、自然に高さを抑えられます。
長期で段階的に小さくする
伸びすぎた松を一気に小さくしようとすると、木がストレスを受けて弱ってしまいます。そのため、2〜3年かけて段階的に小さくしていくのがコツです。
段階的に小さくするステップとして、以下の流れを意識してみましょう。
段階的に小さくするステップとして、以下の流れを意識してみましょう。
| 年数 | 作業内容 | ポイント |
| 1年目 | 高さを少し抑え、透かし剪定で枝を軽く整理 |
樹勢を維持しながら形を整える |
| 2年目 | 枝の内部を透かし、古い枝を整理 | 新しい芽を増やしてバランスを取る |
| 3年目 | 樹形を整える最終調整 | 全体を見ながら自然なシルエットにする |
急激にサイズを変えると、根の吸収量と枝葉のバランスが崩れ、樹勢が弱るリスクが高まります。そのため、毎年少しずつ剪定範囲を広げていけば、木への負担を最小限に抑えながら小さくできますよ。
また枝を減らした分、根元から出る「ひこばえ」や「徒長枝(勢い枝)」が伸びやすくなるため、定期的なチェックも欠かせません。
また枝を減らした分、根元から出る「ひこばえ」や「徒長枝(勢い枝)」が伸びやすくなるため、定期的なチェックも欠かせません。
自分で剪定・業者に依頼はどちらにすべきか
松の剪定は、庭木の中でも特に繊細な作業です。「自分でできるのか」「業者に頼むべきか」で迷う人は多いでしょう。
そのため樹高や枝の太さ・健康状態によって判断するのがポイントです。ここでは費用相場・作業難易度・依頼すべきタイミングを具体的に説明します。
そのため樹高や枝の太さ・健康状態によって判断するのがポイントです。ここでは費用相場・作業難易度・依頼すべきタイミングを具体的に説明します。
松の剪定を業者に依頼した場合の費用相場
業者に剪定を依頼する場合、料金は松の大きさや作業内容で変動します。以下は一般的な費用の目安です。
| 樹高 | 費用相場 | 備考 |
| 〜3m | 約5,000〜10,000円 | 軽剪定・ミドリ摘みなど |
| 3〜5m | 約10,000〜50,000円 | 高所作業を伴う剪定 |
| 5m以上 | 約20,000〜40,000円以上 | 専門技術・複数人作業が必要 |
| 伐採・抜根 | 約10,000〜50,000円 | 状況による追加費用あり |
上記は地域によって異なります。松の種類(黒松・赤松)や形状によっても変動するため、あらかじめ見積書を取っておくと安心です。
業者に依頼するメリットは、安全性と仕上がりの美しさにあります。プロは枝のバランスを見極め、来年以降の芽吹きを考慮した剪定を行うためです。
また切り口処理や松ヤニの処理、ゴミの撤去まで一括で行ってくれるため、時間と手間を大きく節約できるでしょう。
費用を抑えるなら、他の庭木と一緒に剪定を依頼するまとめ割や、地域の造園業者のシーズン前予約(春・秋前)を活用すると良いでしょう。
業者に依頼するメリットは、安全性と仕上がりの美しさにあります。プロは枝のバランスを見極め、来年以降の芽吹きを考慮した剪定を行うためです。
また切り口処理や松ヤニの処理、ゴミの撤去まで一括で行ってくれるため、時間と手間を大きく節約できるでしょう。
費用を抑えるなら、他の庭木と一緒に剪定を依頼するまとめ割や、地域の造園業者のシーズン前予約(春・秋前)を活用すると良いでしょう。
自分で剪定できるのは樹高3m以下が目安
「費用を抑えたい」「自分の手で整えたい」という人は、自分での剪定も可能です。
ただし、安全に行うためにも高さ3m以下を目安にしましょう。
⚫︎地面または脚立で安全に届く範囲
⚫︎細い枝や芽の摘み取り(ミドリ摘み)
⚫︎枯れ枝・不要枝の軽い除去
⚫︎透かし剪定による風通しの改善
低い位置の作業なら、専用の剪定ばさみや手のこがあれば対応できます。しかし、松は切り方を誤ると樹形が崩れたり、病気の原因になるケースも。慎重に進めていきましょう。
特に幹に近い太い枝を無計画に切ると、樹勢が弱まり、翌年の新芽が出なくなることもあります。
3mを超える松は脚立でも不安定になりやすく、転倒・ケガのリスクがあるため、なるべくプロに任せるのが安心です。高い位置の作業と太枝の切断は必ずプロに依頼しましょう。
ただし、安全に行うためにも高さ3m以下を目安にしましょう。
⚫︎地面または脚立で安全に届く範囲
⚫︎細い枝や芽の摘み取り(ミドリ摘み)
⚫︎枯れ枝・不要枝の軽い除去
⚫︎透かし剪定による風通しの改善
低い位置の作業なら、専用の剪定ばさみや手のこがあれば対応できます。しかし、松は切り方を誤ると樹形が崩れたり、病気の原因になるケースも。慎重に進めていきましょう。
特に幹に近い太い枝を無計画に切ると、樹勢が弱まり、翌年の新芽が出なくなることもあります。
3mを超える松は脚立でも不安定になりやすく、転倒・ケガのリスクがあるため、なるべくプロに任せるのが安心です。高い位置の作業と太枝の切断は必ずプロに依頼しましょう。
高所作業や太い枝の処理は業者に任せる
松の剪定では、高所作業と太枝の処理が最も危険で難易度が高い部分です。太い枝はノコギリで切る際に自重で裂け、幹を傷つける危険があります。
また樹高5m以上の松では、命綱・高所作業車・三点支持の技術など専門的な知識が必要です。業者に任せるべきケースか迷ったら、以下を参考にしてください。
⚫︎幹や太枝を切る必要がある
⚫︎樹高が3m以上ある
⚫︎木が電線や屋根に接している
⚫︎幹に亀裂・虫食いなどの異常がある
プロの剪定士は、木の負担を最小限に抑える段階切りや、切り戻し剪定などの技術を持っています。
そのため木の再生を促しながら樹形を美しく整えられるのです。安全性の面からも、脚立で届かない範囲は業者に任せるのがよいでしょう。
また樹高5m以上の松では、命綱・高所作業車・三点支持の技術など専門的な知識が必要です。業者に任せるべきケースか迷ったら、以下を参考にしてください。
⚫︎幹や太枝を切る必要がある
⚫︎樹高が3m以上ある
⚫︎木が電線や屋根に接している
⚫︎幹に亀裂・虫食いなどの異常がある
プロの剪定士は、木の負担を最小限に抑える段階切りや、切り戻し剪定などの技術を持っています。
そのため木の再生を促しながら樹形を美しく整えられるのです。安全性の面からも、脚立で届かない範囲は業者に任せるのがよいでしょう。
松の状態が悪い時は業者に診断してもらおう
伸びすぎた松を放置すると、内部に枯れ枝や病害虫が潜み、健康状態が悪化している可能性があります。以下のような症状がある場合は、プロの診断を受けることをおすすめします。
⚫︎枝先が茶色く変色している
⚫︎幹に樹脂(松ヤニ)が異常ににじみ出ている
⚫︎枝の一部が黒ずんでいる
⚫︎虫のフンや穴が目立つ
⚫︎全体的に葉が薄く、元気がない
上記はマツノザイセンチュウやマツカレハなどの害虫や、病気の初期サインです。放置すると感染が広がり、他の庭木にも悪影響を与えるおそれがあります。
業者なら木の状態を見て、薬剤散布・害虫駆除・土壌改良などの対応が可能です。健康な松を保つためにも、早めの診断と対処をしましょう。
⚫︎枝先が茶色く変色している
⚫︎幹に樹脂(松ヤニ)が異常ににじみ出ている
⚫︎枝の一部が黒ずんでいる
⚫︎虫のフンや穴が目立つ
⚫︎全体的に葉が薄く、元気がない
上記はマツノザイセンチュウやマツカレハなどの害虫や、病気の初期サインです。放置すると感染が広がり、他の庭木にも悪影響を与えるおそれがあります。
業者なら木の状態を見て、薬剤散布・害虫駆除・土壌改良などの対応が可能です。健康な松を保つためにも、早めの診断と対処をしましょう。
まとめ:伸びすぎた松は早めの対処が肝心
伸びすぎた松を放置すると、見た目が悪くなるだけでなく、倒木や病害虫のリスクも高まります。そのため剪定は年1〜2回を目安に、季節に応じて計画的に行いましょう。
適切な時期・方法で剪定を行えば、松は何十年も美しく育ち続けます。危険な作業や判断が難しい場合は、専門業者の手を借りるのもよいでしょう。
適切な時期・方法で剪定を行えば、松は何十年も美しく育ち続けます。危険な作業や判断が難しい場合は、専門業者の手を借りるのもよいでしょう。
庭木の剪定ならお庭の大将にお任せください
剪定時期の見極めや回復のケアは、経験と知識が必要です。自己流で試してうまくいかなかった方は、プロの力を借りることで木を健やかに保てるでしょう。
「お庭の大将」は、年間1,000件以上の庭木管理実績をもつ庭木剪定専門業者です。庭木1本の軽剪定から、全体の景観設計・病害虫対策までトータルでサポートいたします。
プロの剪定は単なる「枝切り」ではなく、木の生命力を引き出すための技術です。特に花芽を残す位置や枝の流れを考慮した剪定は、経験を積んだ職人でなければ難しい部分もあります。
お庭の大将では、樹木の種類やお住まいの地域の気候条件を踏まえ、最も負担の少ないタイミングで作業を行います。
また剪定後の肥料・防虫ケア・次回の剪定時期のアドバイスまで一括でサポートするため、初めて依頼する方でも安心です。
庭木の健康を長く維持したい方や、自分での手入れに限界を感じている方は、ぜひ一度無料相談を活用してください。プロによる適切な剪定で、花も緑も美しくよみがえります。
「お庭の大将」は、年間1,000件以上の庭木管理実績をもつ庭木剪定専門業者です。庭木1本の軽剪定から、全体の景観設計・病害虫対策までトータルでサポートいたします。
プロの剪定は単なる「枝切り」ではなく、木の生命力を引き出すための技術です。特に花芽を残す位置や枝の流れを考慮した剪定は、経験を積んだ職人でなければ難しい部分もあります。
お庭の大将では、樹木の種類やお住まいの地域の気候条件を踏まえ、最も負担の少ないタイミングで作業を行います。
また剪定後の肥料・防虫ケア・次回の剪定時期のアドバイスまで一括でサポートするため、初めて依頼する方でも安心です。
庭木の健康を長く維持したい方や、自分での手入れに限界を感じている方は、ぜひ一度無料相談を活用してください。プロによる適切な剪定で、花も緑も美しくよみがえります。