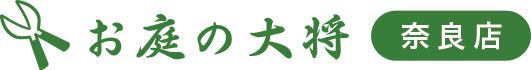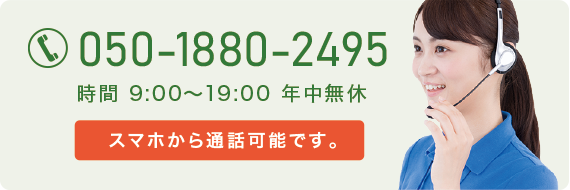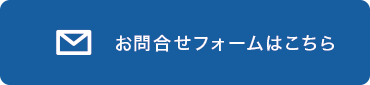庭木の剪定はいつ・どうやる?時期と方法・費用を初心者向けに徹底解説!

「庭木の剪定って、いつ・どうやってやればいいの?」といった不安や疑問を感じたことはありませんか?
庭木の手入れは一見シンプルに見えて、実はかなり奥が深い作業です。間違った時期や方法で剪定してしまうと、木を傷めてしまったり、病害虫を招いたりするリスクも。
本記事では庭木の剪定に関する基礎知識から、時期・方法・注意点・業者への依頼方法まで、実践的で信頼できる情報をまとめました。
この記事を読むことで、剪定の正しいやり方と頼るべきタイミングがわかります。美しい庭を保つための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
庭木の手入れは一見シンプルに見えて、実はかなり奥が深い作業です。間違った時期や方法で剪定してしまうと、木を傷めてしまったり、病害虫を招いたりするリスクも。
本記事では庭木の剪定に関する基礎知識から、時期・方法・注意点・業者への依頼方法まで、実践的で信頼できる情報をまとめました。
この記事を読むことで、剪定の正しいやり方と頼るべきタイミングがわかります。美しい庭を保つための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
庭木の剪定とは?なぜ必要なのか
庭木の剪定とは、庭に植えてある木の枝を切り整える作業です。ただ形を整えるだけでなく、健康な生育を維持し・病害虫を防ぎ・隣家への影響を抑えるなど、さまざまな目的があります。
ここでは剪定の目的と効果、放置した場合のリスクなど、剪定が必要な理由について見ていきましょう。
ここでは剪定の目的と効果、放置した場合のリスクなど、剪定が必要な理由について見ていきましょう。
剪定の目的と効果
剪定には以下のような目的と効果があります。
⚫︎樹形を整える・美観を保つ
⚫︎光や風の通りを良くして内部の新芽を促す
⚫︎枯れ枝・病害枝を取り除き、健康を維持
⚫︎樹木の高さ・枝の張りをコントロールする
⚫︎花つき・実つきの促進
⚫︎病害虫の発生を抑える
たとえば枝が密集していると内部に光が届かず、葉が十分に光合成できなくなります。また湿度がこもりやすくなるため、カビや枯れの原因となるケースも。
剪定によって内部の枝を間引いたり交差枝を除けば、木は新しい芽を伸ばしやすくなります。
さらに枯れた枝や古い枝を除去できれば、栄養や水分もまんべんなく行き渡るようになるでしょう。病気や害虫の予防効果も期待できるため、定期的な剪定は庭木の長寿・健康に直結します。
⚫︎樹形を整える・美観を保つ
⚫︎光や風の通りを良くして内部の新芽を促す
⚫︎枯れ枝・病害枝を取り除き、健康を維持
⚫︎樹木の高さ・枝の張りをコントロールする
⚫︎花つき・実つきの促進
⚫︎病害虫の発生を抑える
たとえば枝が密集していると内部に光が届かず、葉が十分に光合成できなくなります。また湿度がこもりやすくなるため、カビや枯れの原因となるケースも。
剪定によって内部の枝を間引いたり交差枝を除けば、木は新しい芽を伸ばしやすくなります。
さらに枯れた枝や古い枝を除去できれば、栄養や水分もまんべんなく行き渡るようになるでしょう。病気や害虫の予防効果も期待できるため、定期的な剪定は庭木の長寿・健康に直結します。
剪定をしないとどうなる?放置するリスク
剪定をせずに庭木を放置すると、以下のようなリスクがあるため注意しましょう。
⚫︎樹形が乱れ、見た目が悪くなる
⚫︎葉や枝の重なりで風通し・採光が悪化
⚫︎枯れ枝や交差枝が増え、木の負担が増大
⚫︎病害虫が発生しやすくなる
⚫︎隣地・通路にはみ出す枝や落葉でトラブルに
⚫︎大規模な剪定が必要になり費用が高くなる
たとえば、枝葉が伸び放題になると隣家や道路まで枝が張り出し、落ち葉や枝が飛び出せば近所トラブルになる可能性もあります。
また交差枝がこすれて傷つく部分から病気が入る恐れも。さらに長年手をつけないと枝が太くなってしまい、大きく剪定する際に樹木自体へのダメージが大きくなるケースもあります。
そのため木が弱ってしまったり、最悪の場合枯れてしまうため、定期的に手を入れることが重要です。
⚫︎樹形が乱れ、見た目が悪くなる
⚫︎葉や枝の重なりで風通し・採光が悪化
⚫︎枯れ枝や交差枝が増え、木の負担が増大
⚫︎病害虫が発生しやすくなる
⚫︎隣地・通路にはみ出す枝や落葉でトラブルに
⚫︎大規模な剪定が必要になり費用が高くなる
たとえば、枝葉が伸び放題になると隣家や道路まで枝が張り出し、落ち葉や枝が飛び出せば近所トラブルになる可能性もあります。
また交差枝がこすれて傷つく部分から病気が入る恐れも。さらに長年手をつけないと枝が太くなってしまい、大きく剪定する際に樹木自体へのダメージが大きくなるケースもあります。
そのため木が弱ってしまったり、最悪の場合枯れてしまうため、定期的に手を入れることが重要です。
年に何回剪定すればいいのか
庭木の剪定頻度は、樹種・成長速度・目的・予算などによって変わりますが、一般的な目安と注意点は以下の3つです。
⚫︎年に 1〜2回 が基本とされることが多い
⚫︎特に成長の早い樹木や生垣などは年2回が望ましい場合もある
⚫︎剪定しすぎるのも良くないため、過度な剪定回数は避けるべき
たとえば、成長力が低い庭木なら年1回で十分といったケースも。ただし成長力が強い種類や枝葉の伸びが目立つ樹木(シマトネリコやケヤキなど)は、年2回程度の軽剪定を交えておくと、形が乱れにくくなります。
逆に頻繁に剪定を行いすぎると、樹木の生育を阻害したり、切り口が多くなって病害のリスクを高めたりするため注意しましょう。
また庭の見栄えを保ちつつ、無理のない頻度に設定するのがおすすめ。最終的には、木が扱える範囲を超えそうになったら剪定するとイメージするとよいでしょう。
⚫︎年に 1〜2回 が基本とされることが多い
⚫︎特に成長の早い樹木や生垣などは年2回が望ましい場合もある
⚫︎剪定しすぎるのも良くないため、過度な剪定回数は避けるべき
たとえば、成長力が低い庭木なら年1回で十分といったケースも。ただし成長力が強い種類や枝葉の伸びが目立つ樹木(シマトネリコやケヤキなど)は、年2回程度の軽剪定を交えておくと、形が乱れにくくなります。
逆に頻繁に剪定を行いすぎると、樹木の生育を阻害したり、切り口が多くなって病害のリスクを高めたりするため注意しましょう。
また庭の見栄えを保ちつつ、無理のない頻度に設定するのがおすすめ。最終的には、木が扱える範囲を超えそうになったら剪定するとイメージするとよいでしょう。
庭木の剪定に適した時期はいつ?
庭木の剪定は行うタイミングについて悩みどころです。ベストな時期に剪定することで木へのダメージを抑え、健康性と見栄えを両立できるでしょう。
ここでは常緑樹・落葉樹それぞれの剪定タイミングや夏季・冬季剪定の特徴・樹種ごとの具体的な剪定カレンダーをご紹介します。
ここでは常緑樹・落葉樹それぞれの剪定タイミングや夏季・冬季剪定の特徴・樹種ごとの具体的な剪定カレンダーをご紹介します。
常緑樹の剪定時期
常緑樹は四季を通じて葉をつける性質があるため、剪定タイミングを誤ると葉を減らしすぎて木を弱らせるリスクがあります。そのため一般的には、以下のような時期が向いています。
⚫︎春(3月〜5月/新芽が出る直前から出始め)
⚫︎秋(9月〜10月)に軽めの剪定を行う場合もある
具体例として、ツバキ・キンモクセイ・オリーブなどの常緑広葉樹は、3月下旬〜6月が本格剪定の適期とされています 。またスギ、マツ、コニファー類などの常緑針葉樹は、基本的に春の3〜4月ごろに剪定を行うとよいでしょう。
ただし、強剪定(枝を大きく切る)は春の芽吹き前に行うのが望ましく、秋には軽剪定か形を整える程度にとどめるべきとされています。
また真冬や真夏などの極端な気温期は控えることが一般的。木にとって負担になる可能性が高いためなどが理由として挙げられます。
⚫︎春(3月〜5月/新芽が出る直前から出始め)
⚫︎秋(9月〜10月)に軽めの剪定を行う場合もある
具体例として、ツバキ・キンモクセイ・オリーブなどの常緑広葉樹は、3月下旬〜6月が本格剪定の適期とされています 。またスギ、マツ、コニファー類などの常緑針葉樹は、基本的に春の3〜4月ごろに剪定を行うとよいでしょう。
ただし、強剪定(枝を大きく切る)は春の芽吹き前に行うのが望ましく、秋には軽剪定か形を整える程度にとどめるべきとされています。
また真冬や真夏などの極端な気温期は控えることが一般的。木にとって負担になる可能性が高いためなどが理由として挙げられます。
落葉樹の剪定時期
落葉樹は冬に葉を落とし、休眠期に入る性質があります。性質を活かし、葉が落ちきっているときが剪定のベストタイミングとされます。
主な適期は 12月〜2月 の冬季で、この期間中に主幹や太枝を整えるような本格剪定を行うのが一般的です。
しかし注意点として、花木など「旧枝咲き」「新枝咲き」の性質を持つものは、花芽形成時期を考慮して剪定タイミングを微調整しなければなりません。
また、冬期以降の春〜夏にかけて、軽く形を整える軽剪定は可能ですが、大きな枝を切るのは避けるのが望ましいとされています。
落葉が完全に落ちて、枝の形が見やすくなったこの休眠期を使って剪定をすれば、木へのストレスをなるべく抑えつつ翌春以降の成長に備えられますよ。
夏季剪定と冬季剪定の違い
剪定を夏に行うか冬に行うかで、目的・影響・手法が異なります。以下に違いを整理します。
| 特長 |
冬季剪定 | 夏季剪定 |
| 主な目的 | 主幹・太枝の整理、樹形の大改造 | 伸びすぎた枝のカット、風通し・日照改善 |
| 樹木への負荷 | 比較的低い(多くの樹木が休眠期のため) | 高め(成長期に栄養を使っているため) |
| 実施タイミング | 12月〜2月(または冬の終わり) | 4月〜6月あたりが多い |
冬季剪定は、樹木が活動を休んでいる時期を狙うため、枝を切っても回復しやすいとされます。枝の形を整える大きな変形や余分な枝の整理に適した時期ともいえるでしょう。
一方、夏季剪定は、すでに枝葉が伸び始めているため、あくまで軽く形を整える・風通しをよくするのが主な目的です。
ただし真夏(7〜8月)は高温・乾燥のため剪定を控えましょう。植物の負荷が大きくなるためです。
一方、夏季剪定は、すでに枝葉が伸び始めているため、あくまで軽く形を整える・風通しをよくするのが主な目的です。
ただし真夏(7〜8月)は高温・乾燥のため剪定を控えましょう。植物の負荷が大きくなるためです。
樹種別の剪定カレンダー
実際に剪定のタイミングをイメージしやすいよう、代表的な樹種ごとの剪定カレンダーを見てみましょう。
| 樹種・カテゴリ | 基本剪定時期 | 軽剪定可能時期 | 注意事項 |
| 常緑広葉樹(ツバキ・キンモクセイ・サザンカなど) | 3月下旬〜6月 | 8〜10月などに軽く調整可能 | 冬場(11〜2月)に大きく切ると寒害を受けやすい |
| 常緑針葉樹(マツ・スギ・コニファーなど) | 3〜4月(芽吹き前) | 秋〜冬(10〜1月)に軽剪定可 | 冬の寒さや真夏を避け、切りすぎないことが重要 |
| 落葉広葉樹(モミジ・ハナミズキ・アオダモなど) | 12〜2月(冬期) | 3月・6月・9月・10月に軽剪定可 | 花芽を切らないよう剪定時期を意識する必要あり |
たとえばモミジなどの落葉 花木 の場合、花後すぐに剪定すればで翌年の花芽を確保できる種類もあります。
旧枝咲きか新枝咲きかを確認したうえで、冬期剪定と花後剪定を使い分ける工夫があるとさらに良いでしょう。
また地域の気候や日照条件も影響するため、地元の庭木業者に相談しつつ意見も参考に取り入れてください。
旧枝咲きか新枝咲きかを確認したうえで、冬期剪定と花後剪定を使い分ける工夫があるとさらに良いでしょう。
また地域の気候や日照条件も影響するため、地元の庭木業者に相談しつつ意見も参考に取り入れてください。
庭木の剪定で切るべき枝と残すべき枝
庭木の剪定で最も重要なのは、切るものと何を残すものを見極める点です。適当な剪定をすると、木が弱ったり形が崩れたりしてしまいます。ここでは切るべき枝(不要枝)の種類と残すべき枝・枝を選ぶ基準について解説します。
剪定で取り除くべき枝、いわゆる不要枝とは、木の健康や樹形維持にとって邪魔になる枝のことを指します。主に以下の通りです。
⚫︎枯れ枝・病害枝…葉が枯れていたり、幹が黒変・変色している枝
⚫︎徒長枝:勢いよく真上に伸び過ぎた枝、節間が長い枝
⚫︎交差枝・絡み枝…隣の枝とぶつかる、絡み合う枝
⚫︎下垂枝(垂れ枝)…下に垂れ下がっている枝で、他の枝や地面に当たる可能性のあるもの
⚫︎逆さ枝・内向き枝…幹方向や内部に向かって伸びる枝
⚫︎車枝(株元から複数方向に広がる枝)…まとまりなく生えて樹形を乱すもの
⚫︎ヤゴ・ひこばえ(根元や幹基部から出る枝)…過多に出ているものは整理が必要
枯れた枝は木の養分分散を妨げたり、内部の通風・採光を阻害したり、病害虫の温床になるなどのリスクがあります。適度に間引けば、木全体の健全さを高められるでしょう。
逆に、剪定しても残すべき枝には以下のような特徴があります。
⚫︎主幹や幹枝系統…樹形の骨格を作る枝
⚫︎ふところ枝(内側から出て一部は利用できる枝)…適度な内側枝は風通しを保つ役割も
⚫︎更新枝・胴吹き枝(使える枝として残す場合)…将来の枝更新用に残す枝
⚫︎枝張方向・外向き枝…外側方向へ伸び、他枝とぶつからない枝
剪定で取り除くべき枝、いわゆる不要枝とは、木の健康や樹形維持にとって邪魔になる枝のことを指します。主に以下の通りです。
⚫︎枯れ枝・病害枝…葉が枯れていたり、幹が黒変・変色している枝
⚫︎徒長枝:勢いよく真上に伸び過ぎた枝、節間が長い枝
⚫︎交差枝・絡み枝…隣の枝とぶつかる、絡み合う枝
⚫︎下垂枝(垂れ枝)…下に垂れ下がっている枝で、他の枝や地面に当たる可能性のあるもの
⚫︎逆さ枝・内向き枝…幹方向や内部に向かって伸びる枝
⚫︎車枝(株元から複数方向に広がる枝)…まとまりなく生えて樹形を乱すもの
⚫︎ヤゴ・ひこばえ(根元や幹基部から出る枝)…過多に出ているものは整理が必要
枯れた枝は木の養分分散を妨げたり、内部の通風・採光を阻害したり、病害虫の温床になるなどのリスクがあります。適度に間引けば、木全体の健全さを高められるでしょう。
逆に、剪定しても残すべき枝には以下のような特徴があります。
⚫︎主幹や幹枝系統…樹形の骨格を作る枝
⚫︎ふところ枝(内側から出て一部は利用できる枝)…適度な内側枝は風通しを保つ役割も
⚫︎更新枝・胴吹き枝(使える枝として残す場合)…将来の枝更新用に残す枝
⚫︎枝張方向・外向き枝…外側方向へ伸び、他枝とぶつからない枝
| ポイント | 説明 |
| 樹形をイメージする | 最終的な見た目を想像して、残す枝がその形に寄与するかを考える |
| 枝同士の間隔に余裕を持たせる | 枝が密集しすぎないように、風通しや日照の確保を意識 |
| 勢い・太さバランスを考慮 | 強く伸びすぎた枝がある場合、それが残ると樹勢が偏る |
| 将来的な代替を意識 | 一定本数は将来枝として残し、枯れた枝を代替できるようにしておく |
間違った剪定(たとえば主幹を切りすぎる、不要枝を残しすぎる)を行うと、木の再生力を弱めたり、樹冠の崩壊を招いたりするおそれがあるため注意しましょう。
自分で剪定するために必要な道具と準備
庭木の剪定を自分で行いたいと考えるなら、作業内容に合った道具をそろえ、準備を怠らないようにしましょう。
ここでは最低限揃えるべき道具や高所作業用の道具・剪定前にチェックしておく準備事項を詳しくまとめます。
ここでは最低限揃えるべき道具や高所作業用の道具・剪定前にチェックしておく準備事項を詳しくまとめます。
最低限揃えたい剪定道具
まず剪定を始めるにあたって基本的な道具を押さえましょう。以下は、初心者でも揃えやすく、基本的な剪定に対応できる道具です。
| 道具名 | 用途 | 備考 |
| 剪定ばさみ | 細い枝・葉の切り取り | 切れ味がよく、刃が清潔なものを選ぶ |
| 剪定ノコギリ | 太い枝・幹を切る際 |
折りたたみ式や曲刃タイプが使いやすい |
| 作業用手袋 | 手や腕の保護 | 滑り止め付きや丈夫な素材が望ましい |
| 刈り込みばさみ・植木バサミ | 生垣や仕上げの小枝のトリミング | 細かい調整に使う |
| 高枝切りばさみ(ポール式) | 高い枝の剪定 | 届きにくい枝を安全に切るため |
| ブルーシート/下敷き | 枝葉を受けて掃除を簡単にする | 地面が汚れず後片付けが楽になる |
| 熊手/ほうき | 剪定後の枝葉の掃除用 | 庭全体をきれいに整えるのに必須 |
剪定ばさみの種類として、バイパス型・アンビル型を理解しておくとよいでしょう。バイパス型は枝を切るときに刃がすべるように交差し、切り口がきれいに仕上がります。
一方、アンビル型は刃が台にぶつかる構造で、枯れ枝や硬い枝の切断に向いていますよ。状況に合わせて使い分けるのがポイントです。
まずは上記の基本セットを揃え、剪定の経験を積みながら、必要に応じて他の道具を追加するのがよいでしょう。
一方、アンビル型は刃が台にぶつかる構造で、枯れ枝や硬い枝の切断に向いていますよ。状況に合わせて使い分けるのがポイントです。
まずは上記の基本セットを揃え、剪定の経験を積みながら、必要に応じて他の道具を追加するのがよいでしょう。
高所作業の場合の道具
高木や高所の枝剪定を安全に行うには、通常の道具だけでは不十分です。以下のような道具や安全装備を揃えましょう。
⚫︎脚立・伸縮脚立…安定した足場の確保
⚫︎命綱・安全帯…落下防止用の装備
⚫︎ヘルメット・保護メガネ…頭部・目の保護
⚫︎ロープ・滑車器具…大きな枝を落とす際の制御
⚫︎滑り止め靴・安全靴…足元の安定性を確保
⚫︎伸縮式高枝ノコギリ/ポールソー…長い柄で高所から切る道具
⚫︎チェーンソー(高所対応)…非常に大きな枝や幹を処理する場合に限定的に使用
高所作業は非常に危険を伴いますので、自信がない場合にはプロに依頼するのがよいでしょう。
⚫︎脚立・伸縮脚立…安定した足場の確保
⚫︎命綱・安全帯…落下防止用の装備
⚫︎ヘルメット・保護メガネ…頭部・目の保護
⚫︎ロープ・滑車器具…大きな枝を落とす際の制御
⚫︎滑り止め靴・安全靴…足元の安定性を確保
⚫︎伸縮式高枝ノコギリ/ポールソー…長い柄で高所から切る道具
⚫︎チェーンソー(高所対応)…非常に大きな枝や幹を処理する場合に限定的に使用
高所作業は非常に危険を伴いますので、自信がない場合にはプロに依頼するのがよいでしょう。
剪定前にチェック・準備すべきこと
道具を用意したら、いざ剪定に取りかかる前に確認すべき点がいくつかあります。怠ると事故や木へのダメージ、仕上がりの悪化につながる可能性があるため注意が必要です。
| チェック項目 | 内容 |
| 対象の木の状態を観察する | 枯れ枝・病葉の有無をチェックし、どの枝から手をつけるかを計画しておく |
| 作業エリアの整理 | 下に置くものを移動し、枝が落下してもぶつからないようにする |
| 下地の保護 | ブルーシートを敷いて枝葉を受け、掃除を楽にする |
| 天候の確認 | 強風・雨・高温時は避ける。木や作業者に負荷がかかりやすいため |
| 安全確認 | ヘルメット・手袋・保護眼鏡などを装着し、動線や足場の安全性を確認 |
| 切った枝の処理ルートを確保 | 剪定後の枝葉をどこにまとめるか、撤去方法もあらかじめ計画 |
| 作業手順を決めておく | 幹 → 太枝 → 中枝 → 仕上げ枝 の順で進めるとスムーズ |
| 切り口保護材(癒合剤など)の用意 | 大きな枝を切る際には、切り口を保護するための剤を使うことも考慮 |
上記の準備を怠ると、剪定中の怪我や木へのストレス・仕上がりの乱れを招くおそれがあります。しっかり準備してから作業を始めるのが、剪定を安全かつ効果的に進めるコツです。
初心者でもできる剪定の手順
庭木の剪定は、正しい手順を踏めば初心者でも安全に進められます。ただ闇雲に枝を切るのではなく、以下の流れを守ると、木にも庭にも負荷をかけずにきれいに仕上がるでしょう。
⚫︎間引き剪定の進め方
⚫︎切り戻し剪定のやり方
⚫︎剪定後のゴミ処理方法
ここでは各作業ごとに具体的なやり方と注意点を見ていきましょう。
⚫︎間引き剪定の進め方
⚫︎切り戻し剪定のやり方
⚫︎剪定後のゴミ処理方法
ここでは各作業ごとに具体的なやり方と注意点を見ていきましょう。
間引き剪定の進め方
間引き剪定は、木の内部に入り込み、不要な枝を付け根から根本的に取り除く方法です。間引き剪定により風通し・採光性を高め、木の健康を保ちます。間引き剪定の手順は以下の手順で進めていきましょう。
| 手順 | 作業内容 | 説明 |
| 1 | 枯れ枝・病枝の除去 | 最初に一番切るべき枝、すでに枯れていたり病変が見られる枝を根本から切り落とします。 |
| 2 | 重なっている枝・交差枝の除去 | 枝と枝が交差したり、こすれあったりする部分を取り除きます。 |
| 3 | 内向き・逆さ枝の整理 | 幹方向に伸びていたり、内部に向かって伸びる枝を除去します。 |
| 4 | 混み合った部分を適度に間引く | 枝の本数を調整して、間隔に余裕のある構造にします。 |
途中で離れた場所から眺め、樹形が左右対称・上下バランスが取れているかをチェックしつつ剪定を進めましょう。また間引き剪定のポイント・注意点は以下の通りです。
⚫︎切る量は、全体の「1/3 ルール」を目安に。
⚫︎枝の総数または全高の 3分の1 を超えて切らないようにする。
⚫︎内部に日が当たり、風が通るように配慮して剪定を行うこと。
⚫︎必要以上に枝を残しすぎると風通しが悪くなり、逆に切りすぎると木に負荷がかかる。
⚫︎剪定を進める前に、どの枝を残すか・どこを切るかを計画しておくと失敗が少なくなる。
間引き剪定によって、木の内部に風と光が届きやすくなり、病害虫の発生を抑える効果が期待できますよ。
⚫︎切る量は、全体の「1/3 ルール」を目安に。
⚫︎枝の総数または全高の 3分の1 を超えて切らないようにする。
⚫︎内部に日が当たり、風が通るように配慮して剪定を行うこと。
⚫︎必要以上に枝を残しすぎると風通しが悪くなり、逆に切りすぎると木に負荷がかかる。
⚫︎剪定を進める前に、どの枝を残すか・どこを切るかを計画しておくと失敗が少なくなる。
間引き剪定によって、木の内部に風と光が届きやすくなり、病害虫の発生を抑える効果が期待できますよ。
切り戻し剪定のやり方
切り戻し剪定は、すでに間引き剪定で不要枝を整理した後、さらに枝を短く詰めつつ樹形を整えたり、木を若返らせたりする目的で行う手法です。切り戻し剪定の手順は以下を参考にしてください。
| 手順 | 説明 | |
| 1 | 残す枝を決める | 前段階で間引いたあとの枝を見て、バランスよく残す枝を選定。 |
| 2 | 芽の上で剪定 | 外向きの芽のすぐ上で枝を切るようにします。切る位置を意識することで、枝の伸び方をコントロールできます。 |
| 3 | 切り口をきれいに仕上げる | 切り戻す際は水平または斜めに切り口を設け、水はけ・樹液の流れを考えます。 |
| 4 | 強剪定・弱剪定の判断 | 枝を大胆に詰める「強剪定」と、やや控えめに切る「弱剪定」があります。用途や樹種に応じて使い分け。 |
| 5 | 全体を眺めて仕上げる | 剪定後は少し離れて眺め、バランスを確認しながら細部を整えます。 |
切り戻し剪定は木に対するストレスが大きいため、頻繁には行わない方が無難です。また枝先まで切り詰めすぎると、切り口から細かい枝が多数出て、樹形が乱れやすくなります。
花芽がつく種類の木(特に花木)では、切り戻すと翌年の花芽を切ってしまう可能性も。剪定時期との兼ね合いに注意しましょう。切り戻し剪定は、間引き剪定と組み合わせて使うのが基本とされています。
間引き剪定で木を整え、その後切り戻し剪定で形や大きさを調整する流れが、初心者でも扱い方法となります。
花芽がつく種類の木(特に花木)では、切り戻すと翌年の花芽を切ってしまう可能性も。剪定時期との兼ね合いに注意しましょう。切り戻し剪定は、間引き剪定と組み合わせて使うのが基本とされています。
間引き剪定で木を整え、その後切り戻し剪定で形や大きさを調整する流れが、初心者でも扱い方法となります。
剪定後のゴミ処理方法
剪定作業が終わったら、枝葉の後始末も重要です。放置すれば見た目が悪くなるだけでなく、害虫や病原菌の温床になるケースも。
以下に剪定後のゴミ処理の方法とコツを紹介します。ゴミ処理の方法と手順は以下を参考に進めましょう。
以下に剪定後のゴミ処理の方法とコツを紹介します。ゴミ処理の方法と手順は以下を参考に進めましょう。
| 処理方法 | 説明 |
| 枝葉をブルーシートに落とす | 剪定前にブルーシートを敷いておくと、枝葉をその上に落としやすく、あとでまとめやすくなります。 |
| 幹・枝・葉を種類別に分ける | 太枝・細枝・葉で分別すると処理が効率的 |
| 細かい葉・葉片は熊手やほうきで集める | 細かいゴミは地面に接しているため、手で集めづらい |
| 焼却・チップ化・可燃ゴミ出しなど地域ルールに従う | 自治体によって燃えるゴミかどうか、回収方法が異なる |
| 剪定枝をチップ化・堆肥化する場合は適切に処理 | 樹種や条件によってはそのまま庭のマルチ材や堆肥材に使える場合もある |
剪定後のゴミが庭に残ると、特に湿った環境ではカビ・菌・害虫が発生しやすくなります。枯れ枝や葉っぱは病原菌の通り道にもなり得るため、できるだけ速やかに撤去するのが望ましいです。
またゴミをそのまままとめず雑草や土と混ざったまま処分すると、回収時の手間が増えるため、処理のしやすさを考えて分別をおすすめします。剪定後の片付けにかかる時間も作業全体の見積もりに入れておくと安心です。
さらにゴミ処理を業者依頼する場合には、剪定作業と同時に枝葉回収込みも確認して見積もりを取ると、追加費用の心配を減らせます。
またゴミをそのまままとめず雑草や土と混ざったまま処分すると、回収時の手間が増えるため、処理のしやすさを考えて分別をおすすめします。剪定後の片付けにかかる時間も作業全体の見積もりに入れておくと安心です。
さらにゴミ処理を業者依頼する場合には、剪定作業と同時に枝葉回収込みも確認して見積もりを取ると、追加費用の心配を減らせます。
庭木の剪定を業者に依頼する場合の料金相場
庭木の剪定を自分で行うのが難しいと感じたら、プロへの依頼もおすすめです。剪定料金は庭の木の高さ・本数・樹種、作業の難易度、地域などによって大きく変動します。ここでは一般的な相場と、業者の料金体系(日当制/単価制)の違いを見ていきましょう。
剪定料金の相場
業者に庭木の剪定を依頼した場合、木1本あたりの料金が一般的な基準になります。以下は、複数の情報サイトをもとに集めた相場の目安です。
| 樹高/樹木の規模 | 目安料金 | 備考 |
| 低木(〜3m程度) | 約 2,500〜5,000円/本 | 手の届く高さで技術を要さない木 |
| 中木(3〜5m程度) | 約 7,000〜15,000円/本 | 脚立や高枝バサミを使うことが多い |
| 高木(5〜7m程度) | 約 20,000〜25,000円/本 | 高所作業あり、重機やロープが必要な場合も |
| 超高木(7m以上) | 個別見積もり | 樹種・立地・アクセス条件で金額が変動 |
上記の金額は「剪定のみ」の料金であり、枝葉の処分費用や 出張費用・特殊作業(高所・重機使用など)は別途請求されることが多いため、見積もり時に確認が必要です。
また相場の参照例として、造園業者の料金表を見てみましょう。
⚫︎3m…4,500円
⚫︎4m…6,500円
⚫︎5m…9,000円
⚫︎6m以上…13,000円〜
地域や植木屋の規模によっては、このような「高さ別価格表」を用意している業者もあります。
また相場の参照例として、造園業者の料金表を見てみましょう。
⚫︎3m…4,500円
⚫︎4m…6,500円
⚫︎5m…9,000円
⚫︎6m以上…13,000円〜
地域や植木屋の規模によっては、このような「高さ別価格表」を用意している業者もあります。
料金体系の種類(日当制と単価制)
業者が剪定料金を設定する際の方式には大きく分けて、日当制(または時給制)と単価制(木1本あたりなど)があります。それぞれの特徴と適するケースを理解しておきましょう。
| 料金方式 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 日当制/時給制 | 職人1人あたりの「1日」または「1時間」に対して料金を設定 | 見積もりがシンプル、雑多な作業を含みやすい | 作業が長引くと割高になる可能性あり |
| 単価制 | 木1本あたり、または高さ・太さ・本数などで単価を決める | 作業量・木の規模が明確だと見積もりがわかりやすい | 特殊作業や条件変化で追加料金が発生しやすい |
ただし作業が途中で終わらなかったり、追加工事が発生した場合は延長料金がかかるケースもあります。
また単価制であっても、重機使用や交通費、ゴミ処分等は別途料金として加算されることが多いため、見積もり時に含まれているかを確認する必要があるでしょう。
また、どちらを選ぶべきか迷ったら以下を目安にしてくださいね。
⚫︎日当制が向くケース…複数本の木、大規模な庭、作業の範囲が広い場合
⚫︎単価制が向くケース…木が少ない・規模が明確な剪定、1本ごとに区切って依頼したい場合
見積もりを取る際には、どちらの方式が採用されているか、追加費用の有無・作業時間の目安などを必ず確認しましょう。
また単価制であっても、重機使用や交通費、ゴミ処分等は別途料金として加算されることが多いため、見積もり時に含まれているかを確認する必要があるでしょう。
また、どちらを選ぶべきか迷ったら以下を目安にしてくださいね。
⚫︎日当制が向くケース…複数本の木、大規模な庭、作業の範囲が広い場合
⚫︎単価制が向くケース…木が少ない・規模が明確な剪定、1本ごとに区切って依頼したい場合
見積もりを取る際には、どちらの方式が採用されているか、追加費用の有無・作業時間の目安などを必ず確認しましょう。
庭木の剪定はお庭の大将にお任せください
お庭の大将は、庭木剪定を含むお庭メンテナンスを専門に手がけるプロフェッショナル集団です。
お客様のご要望や庭の特性に合わせた丁寧な施工を心がけ、安心して任せていただけるよう徹底した体制を整えています。
お庭の大将が選ばれる理由は以下の通りです。
お客様のご要望や庭の特性に合わせた丁寧な施工を心がけ、安心して任せていただけるよう徹底した体制を整えています。
お庭の大将が選ばれる理由は以下の通りです。
| 特徴 | 説明 |
| 現地調査と無料見積もり | まずはお庭の状態・樹種・剪定希望箇所を確認したうえで、お見積もりを提示。見積もりは無料で行います。 |
| 経験豊富な剪定技術 | 庭木の樹形を損なわず、木の健康を考えた間引き・切り戻しを行う技術力があります。剪定後の姿をイメージできる設計力も強みです。 |
| 高所・特殊作業にも対応 | 高木剪定、ロープ作業、重機使用が必要なケースにも対応可能。安全対策を徹底しつつ、無理なく剪定を進めます。 |
| 枝葉の片付け・処分まで一括対応 | 剪定後のゴミ処理も含めたプランをご用意。面倒な剪定枝の処分もおまかせください。 |
| 保証とアフターケア | 剪定後の木の様子を定期チェックし、剪定が原因の不具合には保証対応も可能です。 |
もし「どこまで剪定が必要か迷っている」「安全に高所木を処理してほしい」「ゴミ処分も含めて一括で頼みたい」といったお悩みがあれば、お庭の大将が解決をお手伝いいたします。まずは、無料見積もり依頼はこちら からご相談ください。