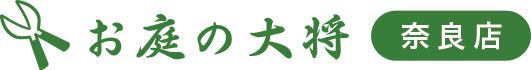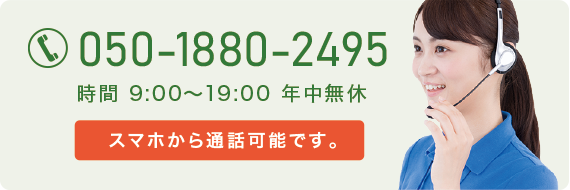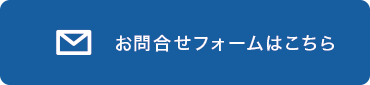柿の木の剪定時期はいつ?
剪定の方法と業者に依頼するときの費用を紹介!
剪定の方法と業者に依頼するときの費用を紹介!

「柿の木がどんどん大きくなって、手に負えない…」「毎年実が少なくて、なんでなのか分からない」といった悩みを抱えていませんか?
柿の木は丈夫で育てやすい反面、適切な剪定をしないと実付きが悪くなったり、木が暴れてしまう性質があります。
この記事では、剪定の基本時期・切ってはいけない枝・結果枝の管理方法・業者依頼時の費用相場など、読むだけで正しく、効率よく剪定するためのポイントが見えるようになる内容をお届けします。
「柿の実がなる庭をもう一度楽しみたい」と思うあなたに、きっと役立つ情報が満載です。ぜひ最後までお読みください。
柿の木は丈夫で育てやすい反面、適切な剪定をしないと実付きが悪くなったり、木が暴れてしまう性質があります。
この記事では、剪定の基本時期・切ってはいけない枝・結果枝の管理方法・業者依頼時の費用相場など、読むだけで正しく、効率よく剪定するためのポイントが見えるようになる内容をお届けします。
「柿の実がなる庭をもう一度楽しみたい」と思うあなたに、きっと役立つ情報が満載です。ぜひ最後までお読みください。
柿の木に剪定が必要な理由
柿の木の不要な枝を整理し、樹形や生育環境を整える作業は、見た目をすっきりさせるだけではありません。
剪定によって、翌年以降の収穫量や品質・作業のしやすさに結びつきます。ここでは、剪定が必要となる主な理由を3つに分けて解説します。
剪定によって、翌年以降の収穫量や品質・作業のしやすさに結びつきます。ここでは、剪定が必要となる主な理由を3つに分けて解説します。
放置すると実付きが悪くなる
柿の木を剪定せず放置しておくと、枝が無秩序に伸び、たくさんの実をつけてしまいます。たとえば枝を剪定せず残してしまうと、ひとつの木に実がたくさんついてしまい、栄養が分散して大きくて美味しい柿にならないと説明といった例も。
実をたくさんつけすぎると、果実1つあたりに行き渡る栄養が少なくなり、「隔年結実(=今年たくさんついたら翌年ほとんどつかない)」という現象も起きやすくなるため注意しましょう。
ただし、結果母枝から伸びた新しい枝に翌年実がつく性質があるため、前年伸びた枝をすべて切ってしまうと実付きが悪化します。実つきを安定させるには、剪定で枝数・実の数ともにコントロールするとよいでしょう。
枝も葉も伸び放題では、木全体のエネルギーが消費されてしまい、次年度に実をつける力が弱くなってしまいます。そのため剪定は、木にとっても良い意味で余裕を与える作業とも言えるのです。
実をたくさんつけすぎると、果実1つあたりに行き渡る栄養が少なくなり、「隔年結実(=今年たくさんついたら翌年ほとんどつかない)」という現象も起きやすくなるため注意しましょう。
ただし、結果母枝から伸びた新しい枝に翌年実がつく性質があるため、前年伸びた枝をすべて切ってしまうと実付きが悪化します。実つきを安定させるには、剪定で枝数・実の数ともにコントロールするとよいでしょう。
枝も葉も伸び放題では、木全体のエネルギーが消費されてしまい、次年度に実をつける力が弱くなってしまいます。そのため剪定は、木にとっても良い意味で余裕を与える作業とも言えるのです。
風通しと日当たりを確保する
剪定を怠ると枝が密集し、葉も茂って日光が当たりにくく、風が通りにくい樹形になってしまいます。そのため、次の問題に注意しましょう。
⚫︎木の内側まで日が届かず、下枝や葉が弱る・枯れる
⚫︎風通しが悪いため、湿気がこもりやすく病害虫の発生リスクが高まる
⚫︎枝同士がこすれて傷ついたり、実が日陰になって品質低下につながったりする
剪定しないと枝や葉が混み合い、日光・風通しが悪くなり、生育に悪影響となるため注意しましょう。剪定で改善すべきポイントは以下の通りです。
⚫︎内向き・下向き・重なった枝を間引きする
⚫︎樹形を横に広がる形に整えて、光が各枝・実に届くようにする
⚫︎風が抜ける空間を意識して枝を整理する
樹内の風と光の通り道を確保すれば、木が健やかに育ち、実のつきも安定します。放置して枝葉が重なれば、病気や害虫との闘いも増えてしまうため、剪定を通して見える風・通る風・届く光を作るのが大切です。
⚫︎木の内側まで日が届かず、下枝や葉が弱る・枯れる
⚫︎風通しが悪いため、湿気がこもりやすく病害虫の発生リスクが高まる
⚫︎枝同士がこすれて傷ついたり、実が日陰になって品質低下につながったりする
剪定しないと枝や葉が混み合い、日光・風通しが悪くなり、生育に悪影響となるため注意しましょう。剪定で改善すべきポイントは以下の通りです。
⚫︎内向き・下向き・重なった枝を間引きする
⚫︎樹形を横に広がる形に整えて、光が各枝・実に届くようにする
⚫︎風が抜ける空間を意識して枝を整理する
樹内の風と光の通り道を確保すれば、木が健やかに育ち、実のつきも安定します。放置して枝葉が重なれば、病気や害虫との闘いも増えてしまうため、剪定を通して見える風・通る風・届く光を作るのが大切です。
収穫しやすい高さを保つ
成長を続ける柿の木は、放っておくと樹高が メートル以上になるケースも珍しくありません。 このままでは以下のような困った状況に陥ります。
⚫︎枝が高く手が届かず、収穫作業が難しい・安全性が低い
⚫︎枝を切る・摘果する・害虫を駆除するといった管理作業そのものが大変になる
⚫︎木が大きすぎると、剪定で一気に切る必要が出て木にダメージを与えてしまう
トラブルを防ぐために、剪定では以下の点に注意しましょう。
⚫︎毎年少しずつ高さを抑える「切り戻し」や「主幹の整理」
⚫︎高すぎる主枝を間引き、横方向に広がる主枝を残す
⚫︎樹高を低めに保つことで、脚立や梯子を使わずに作業ができるようにする
しっかりとした整備をしておくと、長年にわたる管理・収穫がずっとラクになります。さらに木の構造が把握しやすくなるため、計画的な手入れも可能になるのです。
⚫︎枝が高く手が届かず、収穫作業が難しい・安全性が低い
⚫︎枝を切る・摘果する・害虫を駆除するといった管理作業そのものが大変になる
⚫︎木が大きすぎると、剪定で一気に切る必要が出て木にダメージを与えてしまう
トラブルを防ぐために、剪定では以下の点に注意しましょう。
⚫︎毎年少しずつ高さを抑える「切り戻し」や「主幹の整理」
⚫︎高すぎる主枝を間引き、横方向に広がる主枝を残す
⚫︎樹高を低めに保つことで、脚立や梯子を使わずに作業ができるようにする
しっかりとした整備をしておくと、長年にわたる管理・収穫がずっとラクになります。さらに木の構造が把握しやすくなるため、計画的な手入れも可能になるのです。
柿の剪定に最適な時期を知ろう
柿の木の剪定を成功させるには、剪定のタイミングが大きなポイントです。ベストな時期を選ばなければ、せっかくの努力が水の泡になるだけでなく、木そのものにダメージを与えてしまう恐れもあります。
特に「実がならない」「剪定後に枯れてしまった」といったトラブルの多くは、時期の判断ミスによるものです。ここでは柿の剪定に最適な時期と理由・注意すべき点について解説していきます。
またシルバー人材センターとの契約は請負契約となるため、万が一の事故や破損に備えて損害保険の加入状況を確認しておくと安心して任せられますよ。
「費用をできるだけ抑えたい」「地域の信頼できる人に頼みたい」という方には、シルバー人材センターがおすすめ。特に、軽剪定や垣根の整備など、専門的な技術を必要としない作業にはおすすめです。
特に「実がならない」「剪定後に枯れてしまった」といったトラブルの多くは、時期の判断ミスによるものです。ここでは柿の剪定に最適な時期と理由・注意すべき点について解説していきます。
またシルバー人材センターとの契約は請負契約となるため、万が一の事故や破損に備えて損害保険の加入状況を確認しておくと安心して任せられますよ。
「費用をできるだけ抑えたい」「地域の信頼できる人に頼みたい」という方には、シルバー人材センターがおすすめ。特に、軽剪定や垣根の整備など、専門的な技術を必要としない作業にはおすすめです。
冬の休眠期が基本の剪定時期
柿の木の剪定は冬の休眠期が基本です。具体的には12月から2月上旬が最も適した時期とされています。
期間中、木は活動を止めているため、剪定による負担が最小限に抑えらるでしょう。その他の理由は以下の通りです。
⚫︎樹液の流れが止まっており、切り口からの水分の流出が少ない
⚫︎木が休んでいるため、剪定によるストレスを感じにくい
⚫︎葉が落ちているので枝の構造が見やすく、不要な枝が見分けやすい
特にこの時期に行うべき剪定作業として、以下を意識するとよいでしょう。
⚫︎結果母枝の整理
⚫︎徒長枝の間引き
⚫︎主幹や骨格枝の「切り戻し」や「透かし剪定」
柿の木にとって、冬の剪定は体を整える整体のようなものです。来季の実付きに影響する花芽を守りつつ、木のバランスを整えるため、タイミングを逃さないようにしましょう。
特に1月は剪定にぴったりな時期とされており、プロの剪定業者も同時期での作業をおすすめしています。
ただし地域によっては1月に厳しい寒さが続くケースがあり、切り口が凍結し、ダメージを受けやすくなるため注意が必要です。
剪定後には癒合剤と呼ばれる保護剤を切り口に塗れば、乾燥や病原菌の侵入を防ぐ効果が期待できるでしょう。
初心者の方にとっては、枝の選び方や切り方が難しいと感じるかもしれません。そのため最初は不要な枝(内向き枝、交差枝、下向き枝など)の整理から始めてみましょう。
期間中、木は活動を止めているため、剪定による負担が最小限に抑えらるでしょう。その他の理由は以下の通りです。
⚫︎樹液の流れが止まっており、切り口からの水分の流出が少ない
⚫︎木が休んでいるため、剪定によるストレスを感じにくい
⚫︎葉が落ちているので枝の構造が見やすく、不要な枝が見分けやすい
特にこの時期に行うべき剪定作業として、以下を意識するとよいでしょう。
⚫︎結果母枝の整理
⚫︎徒長枝の間引き
⚫︎主幹や骨格枝の「切り戻し」や「透かし剪定」
柿の木にとって、冬の剪定は体を整える整体のようなものです。来季の実付きに影響する花芽を守りつつ、木のバランスを整えるため、タイミングを逃さないようにしましょう。
特に1月は剪定にぴったりな時期とされており、プロの剪定業者も同時期での作業をおすすめしています。
ただし地域によっては1月に厳しい寒さが続くケースがあり、切り口が凍結し、ダメージを受けやすくなるため注意が必要です。
剪定後には癒合剤と呼ばれる保護剤を切り口に塗れば、乾燥や病原菌の侵入を防ぐ効果が期待できるでしょう。
初心者の方にとっては、枝の選び方や切り方が難しいと感じるかもしれません。そのため最初は不要な枝(内向き枝、交差枝、下向き枝など)の整理から始めてみましょう。
夏に軽い整枝をするメリット
冬の剪定が基本となる一方で、夏場の軽い整枝も忘れてはいけません。6月〜7月頃にかけて、伸びすぎた枝や不要な徒長枝を取り除くことで、日当たりや風通しを確保できます。
夏剪定の目的は以下の通りです。
⚫︎栄養が過剰に使われるのを防ぐ
⚫︎実への日光を確保し、甘さ・色付きの向上を図る
⚫︎密集を防ぎ、病害虫の予防につなげる
夏剪定では以下の作業を行いましょう。
⚫︎伸びすぎた徒長枝の摘心
⚫︎葉をわずかに間引く(透かし剪定)
⚫︎実にかぶさる枝・葉の整理
夏の整枝は軽くが基本です。過度に枝葉を切ると、木に負担がかかり、逆に実付きが悪くなる恐れも。翌年の花芽に影響しなよう慎重に行いましょう。
枝や葉を切りすぎると、光合成がうまく行えず、実の発育が止まってしまうケースもあります。
特に花芽ができる夏場は、結果母枝の整理を誤ると、翌年の実がつかなくなるリスクがあるため注意が必要です。
徒長枝(栄養が集中して真っ直ぐに勢いよく伸びる枝)は早めに切り、他の枝や実への栄養配分を安定させましょう。あくまで補助的な剪定として、木の健康状態を見ながら必要最低限の整枝にとどめます。
夏剪定の目的は以下の通りです。
⚫︎栄養が過剰に使われるのを防ぐ
⚫︎実への日光を確保し、甘さ・色付きの向上を図る
⚫︎密集を防ぎ、病害虫の予防につなげる
夏剪定では以下の作業を行いましょう。
⚫︎伸びすぎた徒長枝の摘心
⚫︎葉をわずかに間引く(透かし剪定)
⚫︎実にかぶさる枝・葉の整理
夏の整枝は軽くが基本です。過度に枝葉を切ると、木に負担がかかり、逆に実付きが悪くなる恐れも。翌年の花芽に影響しなよう慎重に行いましょう。
枝や葉を切りすぎると、光合成がうまく行えず、実の発育が止まってしまうケースもあります。
特に花芽ができる夏場は、結果母枝の整理を誤ると、翌年の実がつかなくなるリスクがあるため注意が必要です。
徒長枝(栄養が集中して真っ直ぐに勢いよく伸びる枝)は早めに切り、他の枝や実への栄養配分を安定させましょう。あくまで補助的な剪定として、木の健康状態を見ながら必要最低限の整枝にとどめます。
剪定してはいけない時期とは
剪定に適さない時期も知っておきましょう。たとえば春の芽吹き直前(2月下旬〜3月)や秋(9月〜10月)は避けるべき時期です。
誤った時期に剪定を行うと、木に大きなストレスを与えてしまうため注意しましょう。剪定に不向きな時期とその理由は以下を参考にしてください。
誤った時期に剪定を行うと、木に大きなストレスを与えてしまうため注意しましょう。剪定に不向きな時期とその理由は以下を参考にしてください。
| 時期 | 理由 |
| 2月下旬〜3月 | 芽吹き直前で樹液が流れ始め、切り口から水が出やすくなる |
| 9月〜10月 | 翌年の花芽が形成されており、誤って切ると実がつかない原因に |
| 梅雨〜真夏 | 高温多湿の中で切り口から病気が入りやすくなる |
柿の木は季節の変化に非常に敏感なため、剪定時期を誤ると木全体のバランスが崩れてしまいます。
特に花芽が形成される秋に強剪定してしまうと、翌年の収穫がゼロになるケースも珍しくありません。
また芽吹き直前の剪定は「泣き枝」と呼ばれる水分の漏れを起こし、木が弱ってしまう可能性があります。
どうしても切らなければならない状況であっても、春の芽吹き直前(2月下旬〜3月)や秋(9月〜10月)の時期は避けるのが無難です。
初心者の方は特に剪定してはいけない時期を押さえつつ、失敗リスクを大きく減らしましょう。判断が難しい場合は、専門業者に相談するのもおすすめの方法です。
特に花芽が形成される秋に強剪定してしまうと、翌年の収穫がゼロになるケースも珍しくありません。
また芽吹き直前の剪定は「泣き枝」と呼ばれる水分の漏れを起こし、木が弱ってしまう可能性があります。
どうしても切らなければならない状況であっても、春の芽吹き直前(2月下旬〜3月)や秋(9月〜10月)の時期は避けるのが無難です。
初心者の方は特に剪定してはいけない時期を押さえつつ、失敗リスクを大きく減らしましょう。判断が難しい場合は、専門業者に相談するのもおすすめの方法です。
初心者でもできる柿の剪定手順
柿の木を健康に保ち、毎年しっかりと実をつけさせるには剪定が欠かせません。特に初心者の方は「何から始めればいいのか分からない」「枝を切りすぎて失敗しないか不安」と感じるかもしれませんね。しかし以下のポイントを押さえれば誰でも実践可能です。
⚫︎柿の剪定に使う道具を揃えよう
⚫︎まず不要な枝を見極める
⚫︎徒長枝と混み枝の処理から始める
⚫︎結果枝の切り戻し方を覚える
⚫︎幹の高さを調整して管理しやすく
ここでは道具の準備から実際の剪定ステップまで、初めての方にもわかりやすく順を追って解説します。
⚫︎柿の剪定に使う道具を揃えよう
⚫︎まず不要な枝を見極める
⚫︎徒長枝と混み枝の処理から始める
⚫︎結果枝の切り戻し方を覚える
⚫︎幹の高さを調整して管理しやすく
ここでは道具の準備から実際の剪定ステップまで、初めての方にもわかりやすく順を追って解説します。
柿の剪定に使う道具を揃えよう
剪定作業をスムーズかつ安全に進めるには、作業内容に合った道具選びがとても大切です。以下の道具を事前に準備しておきましょう。
必要な剪定道具一覧
必要な剪定道具一覧
| 道具名 | 用途 |
| 剪定ばさみ | 細い枝を切る基本の道具 |
| 太枝切り鋏 | 太めの枝(直径3cm前後)を切るのに適している |
| ノコギリ |
太枝や幹の切り戻しに使用 |
| 脚立 | 高い枝を安全に切るために必要 |
| 癒合剤 | 切り口を保護して病気を防ぐ |
| 手袋・ゴーグル | ケガや飛び枝から身を守るための保護具 |
上記の道具はホームセンターや園芸店、オンラインショップでも購入可能です。剪定ばさみは基本ツールですが、切れ味の良いものを選ぶと作業が格段にしやすくなります。
特に切り口がスパッときれいに仕上がると、木へのダメージも抑えられるため、できるだけプロ仕様の製品を使うとよいでしょう。
太枝切り鋏やノコギリは、力のかかる作業が多いため、手のサイズや握力に合ったものを選ぶと疲れにくく、安全性も◎。
また切り口から病気が入るのを防ぐ癒合剤(ゆごうざい)も必須アイテム。雑菌の侵入や乾燥を防ぎ、木の回復を助けてくれます。
慣れないうちは「剪定って大変そう」と思いがちですが、道具さえ整っていれば、意外とスムーズに進められます。道具選びも成功のコツです。
特に切り口がスパッときれいに仕上がると、木へのダメージも抑えられるため、できるだけプロ仕様の製品を使うとよいでしょう。
太枝切り鋏やノコギリは、力のかかる作業が多いため、手のサイズや握力に合ったものを選ぶと疲れにくく、安全性も◎。
また切り口から病気が入るのを防ぐ癒合剤(ゆごうざい)も必須アイテム。雑菌の侵入や乾燥を防ぎ、木の回復を助けてくれます。
慣れないうちは「剪定って大変そう」と思いがちですが、道具さえ整っていれば、意外とスムーズに進められます。道具選びも成功のコツです。
まず不要な枝を見極める
柿の剪定で最初にやるべきは、切るべき枝と残すべき枝の判断です。誤ると、せっかくの作業が台無しになってしまいます。まずは以下のような「不要な枝」をチェックしましょう。
⚫︎交差枝:枝同士が交差してこすれ合うもの
⚫︎内向き枝:木の中心に向かって伸びている枝
⚫︎下向き枝:重さで下がり、実がついても日光が当たりにくい枝
⚫︎枯れ枝・病気の枝:明らかに枯れていたり、病斑のあるもの
⚫︎ひこばえ(根元から出る若枝):栄養を吸うだけで実がつかない
枝を切る際は、枝の付け根から5mm程度離れた部分で切りましょう。中途半端に残すと、枯れ込みや病気の原因になります。
不要な枝の選別がうまくできるようになると、全体の剪定が格段にラクになります。たとえば交差枝は、時間が経つとこすれ合って傷になり、そこから病原菌が侵入する可能性も。早めの対処がポイントです。
また内向きに伸びた枝や下向き枝は、光合成を妨げるだけでなく、将来的な樹形の乱れにもつながるので注意しましょう。
ひこばえは勢いがあり、つい残してしまいがち。しかし実際には養分を消費するだけで、ほとんど果実はつきません。
枝を見極めるには、「来年実をつける可能性があるか?」を基準に考えるのがポイントです。慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、少しずつ木のクセを把握しつつ、進めていきましょう。
⚫︎交差枝:枝同士が交差してこすれ合うもの
⚫︎内向き枝:木の中心に向かって伸びている枝
⚫︎下向き枝:重さで下がり、実がついても日光が当たりにくい枝
⚫︎枯れ枝・病気の枝:明らかに枯れていたり、病斑のあるもの
⚫︎ひこばえ(根元から出る若枝):栄養を吸うだけで実がつかない
枝を切る際は、枝の付け根から5mm程度離れた部分で切りましょう。中途半端に残すと、枯れ込みや病気の原因になります。
不要な枝の選別がうまくできるようになると、全体の剪定が格段にラクになります。たとえば交差枝は、時間が経つとこすれ合って傷になり、そこから病原菌が侵入する可能性も。早めの対処がポイントです。
また内向きに伸びた枝や下向き枝は、光合成を妨げるだけでなく、将来的な樹形の乱れにもつながるので注意しましょう。
ひこばえは勢いがあり、つい残してしまいがち。しかし実際には養分を消費するだけで、ほとんど果実はつきません。
枝を見極めるには、「来年実をつける可能性があるか?」を基準に考えるのがポイントです。慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、少しずつ木のクセを把握しつつ、進めていきましょう。
徒長枝と混み枝の処理から始める
剪定作業で特に注意したいのが「徒長枝(とちょうし)」と「混み枝」です。放置すると、栄養の分配が偏ったり、風通しが悪くなって病気の原因になります。徒長枝・混み枝には以下の特長があるため、チェックしておきましょう。
⚫︎徒長枝:勢いよく真上にまっすぐ伸びた枝。栄養を多く消費し、実をつけにくい
⚫︎混み枝:枝が密集し、光や風が通らない状態になっている箇所の枝
剪定のポイントは以下の通りです。
⚫︎徒長枝は根元から切る、または途中で切り戻す
⚫︎混み枝は重なっている部分を間引いて、全体に光が入るように調整
⚫︎周囲の枝とのバランスを見ながら、1か所に枝が集中しないように整える
徒長枝は見た目に勢いがあり元気そうに見えますが、実は実をつけないエネルギー泥棒です。放っておくと木の栄養が吸い取られてしまい、他の枝の成長に影響を及ぼします。
そのため早い段階で見つけて剪定しましょう。また混み枝は病害虫の温床になるケースも。風が通らず湿気がこもると、カビや害虫が発生しやすくなり、果実や葉にダメージを与えます。
剪定時には枝が互いに呼吸できるスペースを確保するようにし、全体のバランスを見ながら枝を間引いていきましょう。
特に透かし剪定と呼ばれる技術では、枝を均等に配置し、木全体に日光が届くようにするのが目的です。
⚫︎徒長枝:勢いよく真上にまっすぐ伸びた枝。栄養を多く消費し、実をつけにくい
⚫︎混み枝:枝が密集し、光や風が通らない状態になっている箇所の枝
剪定のポイントは以下の通りです。
⚫︎徒長枝は根元から切る、または途中で切り戻す
⚫︎混み枝は重なっている部分を間引いて、全体に光が入るように調整
⚫︎周囲の枝とのバランスを見ながら、1か所に枝が集中しないように整える
徒長枝は見た目に勢いがあり元気そうに見えますが、実は実をつけないエネルギー泥棒です。放っておくと木の栄養が吸い取られてしまい、他の枝の成長に影響を及ぼします。
そのため早い段階で見つけて剪定しましょう。また混み枝は病害虫の温床になるケースも。風が通らず湿気がこもると、カビや害虫が発生しやすくなり、果実や葉にダメージを与えます。
剪定時には枝が互いに呼吸できるスペースを確保するようにし、全体のバランスを見ながら枝を間引いていきましょう。
特に透かし剪定と呼ばれる技術では、枝を均等に配置し、木全体に日光が届くようにするのが目的です。
結果枝の切り戻し方を覚える
剪定において、どこまで枝を切るかは悩ましいポイントのひとつです。特に重要なのが結果枝(けっかし)の切り戻しです。
これは翌年の果実をつける可能性の高い枝を適切な長さに整える作業であり、実付きに大きく影響します。
これは翌年の果実をつける可能性の高い枝を適切な長さに整える作業であり、実付きに大きく影響します。
| 項目 | 内容 |
| 結果枝とは? | 前年に伸びた健康な枝で、翌年の果実がつく「花芽」がついている枝。 |
| 切り戻しの基本 | ・全体の1/3〜1/2ほどの長さに短く切る ・風通し・日当たりを確保 ・切る位置は「外芽(外側に伸びる芽)」の少し上が基本 |
| 切る際の注意点 | ・花芽と葉芽を見分け、花芽を残す ・切り口は斜めにして水が溜まりにくくすることが大切 |
結果枝の切り戻しを誤ると、「翌年に実がつかない」「木が弱る」といった失敗につながるため、特に慎重に行いたい作業です。
目安としては、枝の途中にある花芽(ふくらみが大きく丸い芽)を確認し、少し手前でカットするのがベスト。
反対に、葉芽(細くとがった芽)ばかり残してしまうと、翌年は葉ばかり茂って実がならない状態になってしまいます。
柿の木は「隔年結果(かくねんけっか)」という性質を持ちやすく、剪定でバランスよく結果枝を残すことで、毎年安定して実がつきやすくなるでしょう。
花芽の判別は慣れないと難しいかもしれませんが、数回経験すれば自然と見極められるようになりますよ。
目安としては、枝の途中にある花芽(ふくらみが大きく丸い芽)を確認し、少し手前でカットするのがベスト。
反対に、葉芽(細くとがった芽)ばかり残してしまうと、翌年は葉ばかり茂って実がならない状態になってしまいます。
柿の木は「隔年結果(かくねんけっか)」という性質を持ちやすく、剪定でバランスよく結果枝を残すことで、毎年安定して実がつきやすくなるでしょう。
花芽の判別は慣れないと難しいかもしれませんが、数回経験すれば自然と見極められるようになりますよ。
幹の高さを調整して管理しやすく
柿の木は成長が早く、放置すると数メートルの高さにまで育ちます。しかし高くなりすぎると剪定や収穫、病害虫対策が難しくなるため、幹の高さを一定に保つことも重要なポイントです。高さ調整のメリットは以下をチェックしましょう。
⚫︎脚立なしで収穫できるようになる
⚫︎剪定や摘果、害虫駆除などの管理がしやすくなる
⚫︎強風による倒木リスクや枝折れの予防にもつながる
また幹の高さを抑えるための剪定として以下の方法があります。
⚫︎主幹(幹の中心)を「切り戻し剪定」で短く整える
⚫︎上に向かって伸びる主枝・徒長枝は根元からカット
⚫︎将来の樹形を考え、横に広がる枝を残す
柿の木は自然にまかせておくと、手の届かないほどの高さにまで育ってしまいます。そのまま放っておくと、収穫時に危険を伴うだけでなく、枝の剪定や病害虫の管理も非常に困難になるでしょう。
そこで必要なのが幹の高さの調整です。理想的な樹高は2.5〜3メートル前後とされており、家庭の庭でも作業しやすい高さといえます。
幹や主枝を思い切って短くすることで、新しく伸びる枝の方向性もコントロールしやすくなりますよ。
こういった状態を「切り戻し剪定」と呼びますが、一度に切りすぎると木が弱ってしまうため、数年に分けて少しずつ行うのがベストです。高さを抑えれば、毎年の剪定が格段に楽になり、実も手軽に収穫できます。
⚫︎脚立なしで収穫できるようになる
⚫︎剪定や摘果、害虫駆除などの管理がしやすくなる
⚫︎強風による倒木リスクや枝折れの予防にもつながる
また幹の高さを抑えるための剪定として以下の方法があります。
⚫︎主幹(幹の中心)を「切り戻し剪定」で短く整える
⚫︎上に向かって伸びる主枝・徒長枝は根元からカット
⚫︎将来の樹形を考え、横に広がる枝を残す
柿の木は自然にまかせておくと、手の届かないほどの高さにまで育ってしまいます。そのまま放っておくと、収穫時に危険を伴うだけでなく、枝の剪定や病害虫の管理も非常に困難になるでしょう。
そこで必要なのが幹の高さの調整です。理想的な樹高は2.5〜3メートル前後とされており、家庭の庭でも作業しやすい高さといえます。
幹や主枝を思い切って短くすることで、新しく伸びる枝の方向性もコントロールしやすくなりますよ。
こういった状態を「切り戻し剪定」と呼びますが、一度に切りすぎると木が弱ってしまうため、数年に分けて少しずつ行うのがベストです。高さを抑えれば、毎年の剪定が格段に楽になり、実も手軽に収穫できます。
柿の剪定で絶対に覚えるべきポイント
柿の剪定には、収穫量を大きく左右するポイントがいくつかあります。
⚫︎花芽がつく場所を理解する
⚫︎結果母枝を残すことが最重要
⚫︎切りすぎると実がつかなくなる
知らずに剪定をしてしまうと、「まったく実がつかない」「枝ばかり茂ってしまった」といった失敗につながりかねません。ここでは、柿の剪定で絶対に覚えておきたい3つの要点を詳しく解説します。
⚫︎花芽がつく場所を理解する
⚫︎結果母枝を残すことが最重要
⚫︎切りすぎると実がつかなくなる
知らずに剪定をしてしまうと、「まったく実がつかない」「枝ばかり茂ってしまった」といった失敗につながりかねません。ここでは、柿の剪定で絶対に覚えておきたい3つの要点を詳しく解説します。
花芽がつく場所を理解する
剪定で最も注意すべきポイントとして、花芽の位置を理解しましょう。花芽を誤って切ってしまうと、翌年に実がまったくつかない可能性があるため、慎重な見極めが重要です。花芽と葉芽の違いは以下を参考にしてください。
| 芽の種類 | 特徴 | 見分け方 |
| 花芽 | 果実になる芽 |
丸くてふっくらしている |
| 葉芽 | 葉や枝になる芽 | 細くて尖っている |
花芽のつく位置の傾向は以下の通りです。
⚫︎基本的に前年に伸びた枝の先端〜中間部分につく
⚫︎日当たりが良く、勢いが良すぎない枝に多くつく
⚫︎徒長枝(勢いが強すぎる枝)にはほとんどつかない
剪定時にありがちな失敗が、「枝を整えようとしたら、実がまったくつかなくなった」といったケースです。原因の多くは、花芽を意識せずに切ってしまっている点。
柿の花芽は、冬の剪定時にすでに形成されており、枝先のふくらんだ芽を残すことで、翌年の開花と結実が期待できます。
花芽は葉芽よりも明らかに大きく丸みがあるため、慣れれば見分けも簡単でしょう。特に冬の休眠期(12月〜1月頃)は葉が落ちていて芽が見やすいので、時期をみて剪定すれば判断しやすくなります。
⚫︎基本的に前年に伸びた枝の先端〜中間部分につく
⚫︎日当たりが良く、勢いが良すぎない枝に多くつく
⚫︎徒長枝(勢いが強すぎる枝)にはほとんどつかない
剪定時にありがちな失敗が、「枝を整えようとしたら、実がまったくつかなくなった」といったケースです。原因の多くは、花芽を意識せずに切ってしまっている点。
柿の花芽は、冬の剪定時にすでに形成されており、枝先のふくらんだ芽を残すことで、翌年の開花と結実が期待できます。
花芽は葉芽よりも明らかに大きく丸みがあるため、慣れれば見分けも簡単でしょう。特に冬の休眠期(12月〜1月頃)は葉が落ちていて芽が見やすいので、時期をみて剪定すれば判断しやすくなります。
結果母枝を残すことが最重要
柿の木の実は、結果母枝(けっかぼし)と呼ばれる特定の枝から発生する「結果枝」に実ります。そのため、結果母枝を適切に残すのが剪定の大前提です。結果母枝とは以下の枝を指します。
⚫︎前年に結果枝を出した、実績のある枝
⚫︎翌年も実をつける土台となる枝
⚫︎木の骨格に近い役割を果たし、年々太くなる傾向がある
結果母枝を見極めるポイントとして以下も覚えておきましょう。
⚫︎太さは鉛筆〜指くらい
⚫︎成長が穏やかで、枝がやや横向きに伸びている
⚫︎花芽がつきやすい位置にある(木の外側)
柿の木は、前年に実をつけた枝(結果枝)が1年で役目を終えた後、再びその元となる枝(結果母枝)から新たな結果枝が出て、実がなります。
つまり毎年安定して収穫を得るためには、結果母枝をいかに健全に残すかがカギです。誤って結果母枝を剪定してしまうと、翌年に実がつく枝が育たず、収穫ゼロという事態になりかねません。
結果母枝は見た目ではやや地味な存在ですが、剪定の計画を立てる際には結果母枝から来年の実がなる点を意識して残す必要があります。
最初はどれが結果母枝か分かりにくいかもしれませんが、枝先に実がついていた枝の根元として覚えておくと良いでしょう。
⚫︎前年に結果枝を出した、実績のある枝
⚫︎翌年も実をつける土台となる枝
⚫︎木の骨格に近い役割を果たし、年々太くなる傾向がある
結果母枝を見極めるポイントとして以下も覚えておきましょう。
⚫︎太さは鉛筆〜指くらい
⚫︎成長が穏やかで、枝がやや横向きに伸びている
⚫︎花芽がつきやすい位置にある(木の外側)
柿の木は、前年に実をつけた枝(結果枝)が1年で役目を終えた後、再びその元となる枝(結果母枝)から新たな結果枝が出て、実がなります。
つまり毎年安定して収穫を得るためには、結果母枝をいかに健全に残すかがカギです。誤って結果母枝を剪定してしまうと、翌年に実がつく枝が育たず、収穫ゼロという事態になりかねません。
結果母枝は見た目ではやや地味な存在ですが、剪定の計画を立てる際には結果母枝から来年の実がなる点を意識して残す必要があります。
最初はどれが結果母枝か分かりにくいかもしれませんが、枝先に実がついていた枝の根元として覚えておくと良いでしょう。
切りすぎると実がつかなくなる
剪定は大切な作業ですが、切りすぎは禁物です。枝を大量に切ってしまうと、木が弱ってしまい、翌年の実付きに大きく影響します。切りすぎによる影響として以下の点に注意しましょう。
⚫︎花芽がなくなり、実がならない
⚫︎光合成が行えず、木全体の活力が低下
⚫︎過剰な枝の成長(徒長枝)が増えて管理が困難になる
また適切な剪定量の目安は以下を参考にしてください。
⚫︎全体の2〜3割程度が目安
⚫︎必要最小限の剪定にとどめる
⚫︎切った後の枝のバランスを確認しながら進める
剪定は大胆にやりたくなりますが、柿の木に関しては例外といえます。特に初心者が陥りやすいのが、形を整えようとして枝を切りすぎてしまうトラブルです。
花芽がすべて失われてしまい、1年分の収穫がなくなるというリスクもあるため注意しましょう。
また枝を多く切ると、木は防御反応として勢いのある徒長枝を多数発生させますが、実をつけにくいため、毎年の剪定作業がかえって大変になります。
剪定は切る技術ではなく、残す技術だと理解しましょう。切りたくなる気持ちを抑え、「残すべき枝」をしっかり見極める目を養っていくのがコツです。
⚫︎花芽がなくなり、実がならない
⚫︎光合成が行えず、木全体の活力が低下
⚫︎過剰な枝の成長(徒長枝)が増えて管理が困難になる
また適切な剪定量の目安は以下を参考にしてください。
⚫︎全体の2〜3割程度が目安
⚫︎必要最小限の剪定にとどめる
⚫︎切った後の枝のバランスを確認しながら進める
剪定は大胆にやりたくなりますが、柿の木に関しては例外といえます。特に初心者が陥りやすいのが、形を整えようとして枝を切りすぎてしまうトラブルです。
花芽がすべて失われてしまい、1年分の収穫がなくなるというリスクもあるため注意しましょう。
また枝を多く切ると、木は防御反応として勢いのある徒長枝を多数発生させますが、実をつけにくいため、毎年の剪定作業がかえって大変になります。
剪定は切る技術ではなく、残す技術だと理解しましょう。切りたくなる気持ちを抑え、「残すべき枝」をしっかり見極める目を養っていくのがコツです。
柿の木の剪定を業者に頼む場合の費用
自分で剪定を行うのが難しいと感じた場合、プロの業者に依頼するのもよいでしょう。特に木が高くなりすぎていたり、太枝の剪定や処分が必要な場合には、安全面からも業者依頼がおすすめです。
ここでは柿の木の剪定に業者を頼んだときの費用相場と、依頼前に確認しておくべきポイントを整理します。
ここでは柿の木の剪定に業者を頼んだときの費用相場と、依頼前に確認しておくべきポイントを整理します。
費用相場と料金体系を把握しよう
業者に頼む際の費用は、主に木の高さ・枝の込み具合・作業内容・処分の有無などによって大きく変わります。まずは費用相場を把握して、見積もりを取る際の基準にしてください。
| 木の高さ・状態 | 相場価格 |
備考 |
| 0〜3m・枝少なめ | 約3,000〜5,000円 |
ごく軽い剪定・枝の処分が不要なケース |
| 3〜5m・中程度の剪定 | 約10,000〜20,000円 | 枝が多め・処分作業を含むケース |
| 5〜7m以上・太枝・処分含む | 約15,000〜30,000円以上 | 高所作業や太枝の剪定、処分作業込み |
上記の数字はあくまで目安であり、実際には様々な条件が重なり、見積もりはさらに高くなる可能性があります。
また依頼前に、出張料やゴミ処分費・脚立・高所作業車使用料・駐車場代などが別途かかるかどうかを必ず確認しましょう。
見積もりは複数社から取得し、作業内容・費用・保証(剪定後の木の管理含む)などを比較するのが安心です。
また依頼前に、出張料やゴミ処分費・脚立・高所作業車使用料・駐車場代などが別途かかるかどうかを必ず確認しましょう。
見積もりは複数社から取得し、作業内容・費用・保証(剪定後の木の管理含む)などを比較するのが安心です。
業者選び・依頼前に確認すべきポイント
費用だけで業者を選ぶと、「当日になって追加料金」「剪定後に実がつかない」「枝が残っていた」など後悔するリスクがあります。ここでは安心して依頼できる業者を選ぶためのチェックリストを紹介します。
⚫︎複数業者から「現地見積もり」を取って比較
⚫︎剪定・処分・運搬まで含まれるか確認
⚫︎高所作業や脚立作業が必要な場合、保険加入・安全対策はあるか
⚫︎剪定後の木の様子(実の付き具合含む)についてフォローがあるか
⚫︎木に関する知識(例えば「花芽」「結果母枝」「徒長枝」など)を持っているか確認
また依頼時に業者に以下の内容を伝えておくと、トラブルを避けつつ安心して依頼可能です。
⚫︎木の種類(柿の木)・高さ・枝の込み具合
⚫︎過去の剪定履歴(2年以上手入れしていない等)
⚫︎お庭のアクセス状況(脚立・高所作業車が入るか)
⚫︎剪定後の枝・幹の処分を希望するか否か
⚫︎害獣・病害虫の心配があるかどうか
特に初心者の方が依頼する際は、悩みや疑問をあらかじめ業者に伝えておくと、剪定の方法を提案してくれる可能性があります。
また剪定作業には切りすぎによるリスクも存在します。業者に「切りすぎないように」「花芽を残すように」といった配慮を依頼するのもOKです。
見積もり後の追加料金が発生しないよう、料金に何が含まれているかを明確にしてもらうと安心ですよ。
⚫︎複数業者から「現地見積もり」を取って比較
⚫︎剪定・処分・運搬まで含まれるか確認
⚫︎高所作業や脚立作業が必要な場合、保険加入・安全対策はあるか
⚫︎剪定後の木の様子(実の付き具合含む)についてフォローがあるか
⚫︎木に関する知識(例えば「花芽」「結果母枝」「徒長枝」など)を持っているか確認
また依頼時に業者に以下の内容を伝えておくと、トラブルを避けつつ安心して依頼可能です。
⚫︎木の種類(柿の木)・高さ・枝の込み具合
⚫︎過去の剪定履歴(2年以上手入れしていない等)
⚫︎お庭のアクセス状況(脚立・高所作業車が入るか)
⚫︎剪定後の枝・幹の処分を希望するか否か
⚫︎害獣・病害虫の心配があるかどうか
特に初心者の方が依頼する際は、悩みや疑問をあらかじめ業者に伝えておくと、剪定の方法を提案してくれる可能性があります。
また剪定作業には切りすぎによるリスクも存在します。業者に「切りすぎないように」「花芽を残すように」といった配慮を依頼するのもOKです。
見積もり後の追加料金が発生しないよう、料金に何が含まれているかを明確にしてもらうと安心ですよ。
費用を抑えるための工夫とポイント
「できれば費用を抑えたい」と考えている方に向けて、業者に依頼する際に使えるコツを紹介します。
⚫︎早めに剪定を依頼して、枝が大きくなる前に処理する
⚫︎剪定・処分・運搬を一括で頼むと割安になることがある
⚫︎木の高さが低いうち( m未満)に作業を済ませる
⚫︎剪定履歴を伝えて、不要な枝の処理だけに絞ってもらう
⚫︎複数社に見積もりを取り、明細を比較する
例えば、木が成長して5m以上・枝が込み合ってからでは、高所作業車・脚立の設置・重機使用などが必要になり、費用が跳ね上がるケースがあります。
逆に、まだ木が低く枝もそれほど混んでいない時期に頼めば、比較的簡単な作業で済むため低料金で済む可能性も。
また剪定後の枝・幹の処分が含まれているかどうかで費用が数千〜数万円変わるケースがあるため、「処分費用込み」の見積もりがおすすめ。
繁忙期(冬〜春)や急ぎの案件では費用が高めになる傾向があるため、早めに相談し「日時はおまかせ」といった条件で依頼できるとコストを抑えやすいです。
信頼できる業者を選び、見積もり内容をしっかりチェックすれば、安心かつ納得のいく剪定ができるでしょう。
⚫︎早めに剪定を依頼して、枝が大きくなる前に処理する
⚫︎剪定・処分・運搬を一括で頼むと割安になることがある
⚫︎木の高さが低いうち( m未満)に作業を済ませる
⚫︎剪定履歴を伝えて、不要な枝の処理だけに絞ってもらう
⚫︎複数社に見積もりを取り、明細を比較する
例えば、木が成長して5m以上・枝が込み合ってからでは、高所作業車・脚立の設置・重機使用などが必要になり、費用が跳ね上がるケースがあります。
逆に、まだ木が低く枝もそれほど混んでいない時期に頼めば、比較的簡単な作業で済むため低料金で済む可能性も。
また剪定後の枝・幹の処分が含まれているかどうかで費用が数千〜数万円変わるケースがあるため、「処分費用込み」の見積もりがおすすめ。
繁忙期(冬〜春)や急ぎの案件では費用が高めになる傾向があるため、早めに相談し「日時はおまかせ」といった条件で依頼できるとコストを抑えやすいです。
信頼できる業者を選び、見積もり内容をしっかりチェックすれば、安心かつ納得のいく剪定ができるでしょう。
柿の木の剪定についてよくある質問
剪定に関する基本は理解していても、「この枝は切っていいのか?」「木が大きくなりすぎたらどうする?」など、いざ実践となると疑問が湧いてくるものです。ここでは柿の木の剪定においてよく寄せられる質問に答えます。
柿の剪定で切ってはいけない枝はありますか
柿の木の剪定では、「切ってはいけない枝」と「切るべき枝」の見極めが重要です。間違った剪定は、翌年の収穫に大きな影響を与えかねません。
切ってはいけない主な枝は以下の通りです。
⚫︎結果母枝:翌年の実を支える大切な枝。剪定の基本は「残す」こと
⚫︎花芽がついている枝:先端に丸い芽(花芽)がついている枝は翌年の実の候補
⚫︎主幹や骨格枝:木全体を支える幹や太い骨格枝は構造を保つため必要
切るべき枝の例も見ておきましょう。
⚫︎徒長枝(勢いよく上に伸びた栄養ばかり取る枝)
⚫︎交差枝や内向き枝
⚫︎病害がある枝・枯れ枝
柿の木の剪定で最も重要なのは、花芽を残し、木の形を整える作業です。初心者は樹形を整えるために見た目で枝を切ってしまい、大事な花芽や結果母枝まで切ってしまうかもしれません。
結果的に翌年の実がならず、「剪定で失敗した」と感じる原因になるでしょう。花芽は冬に既に形成されているため、剪定時にしっかり確認しながら作業を進めるのがコツ。判断がつかないときは、無理をせずプロに相談するのが安心です。
切ってはいけない主な枝は以下の通りです。
⚫︎結果母枝:翌年の実を支える大切な枝。剪定の基本は「残す」こと
⚫︎花芽がついている枝:先端に丸い芽(花芽)がついている枝は翌年の実の候補
⚫︎主幹や骨格枝:木全体を支える幹や太い骨格枝は構造を保つため必要
切るべき枝の例も見ておきましょう。
⚫︎徒長枝(勢いよく上に伸びた栄養ばかり取る枝)
⚫︎交差枝や内向き枝
⚫︎病害がある枝・枯れ枝
柿の木の剪定で最も重要なのは、花芽を残し、木の形を整える作業です。初心者は樹形を整えるために見た目で枝を切ってしまい、大事な花芽や結果母枝まで切ってしまうかもしれません。
結果的に翌年の実がならず、「剪定で失敗した」と感じる原因になるでしょう。花芽は冬に既に形成されているため、剪定時にしっかり確認しながら作業を進めるのがコツ。判断がつかないときは、無理をせずプロに相談するのが安心です。
柿の木が大きくなりすぎた時の対処法は
長年手入れをしていない柿の木は、あっという間に手の届かない高さにまで育ってしまいます。
木が高くなると、剪定や収穫作業が困難になり、風通しや日当たりも悪くなりがちです。大きくなりすぎた柿の木の対応策として、以下の点を試してみましょう。
強剪定を数年に分けて行う(一気に切ると木が弱るため段階的に)
⚫︎主幹を切り戻して高さを抑える(ただし慎重に)
⚫︎幹や主枝の「切り返し」で新たな骨格を作る
⚫︎剪定後の管理を徹底し、徒長枝の抑制を行う
高くなりすぎた柿の木は、手入れも困難になり、実がついても収穫できずに落ちてしまうなど、さまざまな問題を引き起こします。
強剪定で一気に小さくしたくなるかもしれませんが、木にとって大きなストレスとなり、翌年以降の実付きに深刻な影響を及ぼす可能性も。
そのため1〜2年に分けて少しずつ剪定し、木の負担を減らすのが基本です。樹高を抑えるために主幹を思い切って切り戻す方法もありますが、剪定箇所には癒合剤を塗るなど、木を保護する配慮が必要です。
慣れていない人には難しい作業となるため、高所剪定に関しては業者への依頼も検討しましょう。
木が高くなると、剪定や収穫作業が困難になり、風通しや日当たりも悪くなりがちです。大きくなりすぎた柿の木の対応策として、以下の点を試してみましょう。
強剪定を数年に分けて行う(一気に切ると木が弱るため段階的に)
⚫︎主幹を切り戻して高さを抑える(ただし慎重に)
⚫︎幹や主枝の「切り返し」で新たな骨格を作る
⚫︎剪定後の管理を徹底し、徒長枝の抑制を行う
高くなりすぎた柿の木は、手入れも困難になり、実がついても収穫できずに落ちてしまうなど、さまざまな問題を引き起こします。
強剪定で一気に小さくしたくなるかもしれませんが、木にとって大きなストレスとなり、翌年以降の実付きに深刻な影響を及ぼす可能性も。
そのため1〜2年に分けて少しずつ剪定し、木の負担を減らすのが基本です。樹高を抑えるために主幹を思い切って切り戻す方法もありますが、剪定箇所には癒合剤を塗るなど、木を保護する配慮が必要です。
慣れていない人には難しい作業となるため、高所剪定に関しては業者への依頼も検討しましょう。
柿の病害虫対策はどうすればいいですか
柿の木は比較的丈夫な果樹ですが、剪定や手入れが行き届かないと病害虫の被害を受ける恐れがあります。とくに実がつきやすい季節や高温多湿な時期には注意が必要です。
主な病害虫と対策法
主な病害虫と対策法
| 病害虫の名前 | 症状 | 対策方法 |
| カキノヘタムシガ | 果実が黒くなり、落果する | 早期摘果、フェロモントラップ設置 |
| カイガラムシ | 枝や幹に白・茶色の虫が付着し樹液を吸う | 剪定で風通し改善、薬剤散布 |
| うどんこ病 | 葉が白く粉をふいたようになる | 風通し改善、予防的薬剤の使用 |
| 黒星病 | 実に黒い斑点が出る | 発病枝の除去、収穫後の薬剤散布 |
柿の病害虫は、一度発生すると被害が広がりやすく、実の品質や収穫量に大きな影響を与えます。そのため病気の予防には、剪定によって風通しと日当たりを確保しましょう。
また剪定時に病害枝を発見したら、早急に切り落とし、焼却するなどの処理が必要です。害虫対策では、発生時期に合わせた薬剤の使用や、防虫ネット・フェロモントラップの活用も効果的です。
自然環境に配慮したい方は、剪定をしっかり行い、病害虫の住みにくい環境づくりを心がけましょう。
また剪定時に病害枝を発見したら、早急に切り落とし、焼却するなどの処理が必要です。害虫対策では、発生時期に合わせた薬剤の使用や、防虫ネット・フェロモントラップの活用も効果的です。
自然環境に配慮したい方は、剪定をしっかり行い、病害虫の住みにくい環境づくりを心がけましょう。
柿の木の剪定はお庭の大将にお任せください
「庭木剪定が難しい」「毎年実がならない」「高すぎて手が届かない」など、柿の木の管理にお困りの方へ。そんなときこそ、庭木剪定のプロフェッショナル・お庭の大将にご相談ください。お庭の大将では、以下の体制を整え、ご依頼をお待ちしております。
⚫︎柿の木の特性を熟知した職人が対応
⚫︎花芽・結果母枝を意識した丁寧な剪定
⚫︎高所作業も安全かつ確実に実施
⚫︎剪定後の枝処分・庭の清掃もお任せ
⚫︎明朗な料金体系&現地見積もり無料
柿の木は毎年の成長が早く、放置するとすぐに枝葉が混み合い、風通しや日当たりが悪化します。そのため病害虫が発生したり、実がつかなくなるといった問題も発生しやすいのがネック。
お庭の大将では、現地の状況を丁寧に確認し、それぞれの木に合った最適な剪定をご提案。安全第一の施工はもちろん、剪定後の樹勢回復にも配慮しています。
お客様の「またお願いしたい」を大切に、地域密着型でサポート!まずは無料見積もりから、お気軽にご相談ください。
⚫︎柿の木の特性を熟知した職人が対応
⚫︎花芽・結果母枝を意識した丁寧な剪定
⚫︎高所作業も安全かつ確実に実施
⚫︎剪定後の枝処分・庭の清掃もお任せ
⚫︎明朗な料金体系&現地見積もり無料
柿の木は毎年の成長が早く、放置するとすぐに枝葉が混み合い、風通しや日当たりが悪化します。そのため病害虫が発生したり、実がつかなくなるといった問題も発生しやすいのがネック。
お庭の大将では、現地の状況を丁寧に確認し、それぞれの木に合った最適な剪定をご提案。安全第一の施工はもちろん、剪定後の樹勢回復にも配慮しています。
お客様の「またお願いしたい」を大切に、地域密着型でサポート!まずは無料見積もりから、お気軽にご相談ください。