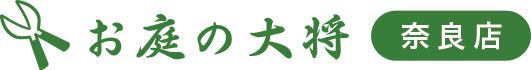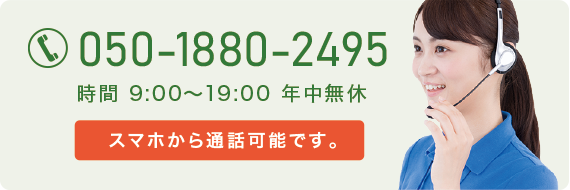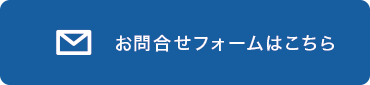木の伐採を自分でやる方法と業者依頼の判断基準!
費用・時期・手順を徹底解説!
費用・時期・手順を徹底解説!

「庭の木を伐採したいけれど、どこから手をつければいいのか分からない…」
そんな悩みを抱えてはいませんか。
木の伐採は一度の判断ミスで事故や近隣トラブルにつながりやすく、素人では危険を見抜きづらい作業です。
木 伐採は 木のサイズ・場所・危険度によって最適な方法が異なります。
本記事では、自分で伐採できる木の条件、安全な作業手順、業者に依頼する場合の費用相場・伐採に適した時期など、正しい判断に必要な情報を解説します。
この記事を読むことで、初めての伐採で不安な方でも、迷わず行動に移せるようになるでしょう。
そんな悩みを抱えてはいませんか。
木の伐採は一度の判断ミスで事故や近隣トラブルにつながりやすく、素人では危険を見抜きづらい作業です。
木 伐採は 木のサイズ・場所・危険度によって最適な方法が異なります。
本記事では、自分で伐採できる木の条件、安全な作業手順、業者に依頼する場合の費用相場・伐採に適した時期など、正しい判断に必要な情報を解説します。
この記事を読むことで、初めての伐採で不安な方でも、迷わず行動に移せるようになるでしょう。
木の伐採とは?抜根との違いを理解しよう
庭木の手入れで、伐採と抜根の違いがよく分からず迷っていませんか。どちらの作業も木を処理する目的で行われますが、作業内容・費用・必要な道具・作業時間が大きく異なるため、誤って選んでしまうと余計なコストやリスクが発生します。
ここでは伐採の基本的な意味や作業工程・抜根との違い、それぞれを選ぶべきタイミングについて見ていきましょう。
ここでは伐採の基本的な意味や作業工程・抜根との違い、それぞれを選ぶべきタイミングについて見ていきましょう。
伐採は木を根元から切り倒す作業
伐採とは、木を根元付近で切り倒す作業を指します。チェーンソーや、ノコギリを使い、幹の太さや高さに合わせて安全に木を切り落とすのが一般的。
切り倒した後には、切り株が残り、根っこ自体は地中のまま残ります。伐採は庭木だけでなく、街路樹・山林・店舗や建物周辺の危険木にも行われる重要な作業です。
伐採の特徴をまとめると以下の通りです。
切り倒した後には、切り株が残り、根っこ自体は地中のまま残ります。伐採は庭木だけでなく、街路樹・山林・店舗や建物周辺の危険木にも行われる重要な作業です。
伐採の特徴をまとめると以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 作業内容 | 木を根元近くから切り倒す |
| 道具 | ノコギリ、チェーンソー、ロープ、保護具 |
| 残るもの |
切り株・根っこ |
| 作業時間 | 木の大きさにより30分〜半日 |
| 費用相場 | 庭木の伐採:5,000円〜50,000円(高さ・太さで変動) |
| リスク | 倒れる方向の誤り、チェーンソー事故、周囲の破損 |
伐採では、受け口と呼ばれる切り込みを倒したい方向に入れ、追い口を反対側に入れて、木が想定した方向に倒れるよう調整します。
受け口の工程が不十分だと、木が違う方向へ倒れ、家屋・塀・車などを破損する可能性が。
さらに慣れない人がチェーンソーを使うのは非常に危険で、年間でも多くの事故が報告されています。作業中はゴーグル・耳栓・安全靴・グローブなど、十分な保護具が欠かせません。
また伐採は切って倒すだけのシンプルな作業と思われがちですが、実際には倒れた木の処分・搬出が大きな労力になります。
幹の太さが20cmを超える木は大変重く、一人で運ぶのが難しいでしょう。さらに枝葉の処分は自治体によって、ルールが異なるため注意が必要です。
多くの地域では、可燃ごみとして出せる量が限られているため、軽トラックで運ぶなど大掛かりになる場合があるでしょう。
業者に依頼するメリットは、作業の安全性が高いだけでなく、倒れた木の処分までまとめて依頼できる点です。
特に高さ5メートルを超える木や、家や電線が近い場所に植わっている木は、素人が伐採するには危険が伴うケースも。プロに任せるほうが結果的に安く済むケースも多いです。
受け口の工程が不十分だと、木が違う方向へ倒れ、家屋・塀・車などを破損する可能性が。
さらに慣れない人がチェーンソーを使うのは非常に危険で、年間でも多くの事故が報告されています。作業中はゴーグル・耳栓・安全靴・グローブなど、十分な保護具が欠かせません。
また伐採は切って倒すだけのシンプルな作業と思われがちですが、実際には倒れた木の処分・搬出が大きな労力になります。
幹の太さが20cmを超える木は大変重く、一人で運ぶのが難しいでしょう。さらに枝葉の処分は自治体によって、ルールが異なるため注意が必要です。
多くの地域では、可燃ごみとして出せる量が限られているため、軽トラックで運ぶなど大掛かりになる場合があるでしょう。
業者に依頼するメリットは、作業の安全性が高いだけでなく、倒れた木の処分までまとめて依頼できる点です。
特に高さ5メートルを超える木や、家や電線が近い場所に植わっている木は、素人が伐採するには危険が伴うケースも。プロに任せるほうが結果的に安く済むケースも多いです。
抜根は根っこまで完全に取り除く作業
抜根(ばっこん)とは、伐採後に地中の「根っこ」まで完全に取り除く作業です。木の表面だけでなく、地中に残った根全体を掘り起こし、撤去するため、伐採より大幅に手間と費用がかかります。
特に幹が太い木や、長年植わっている庭木は根が深く伸びているため注意!地中で複雑に広がっているため、掘り起こす作業は専門的な技術を要します。
抜根の特徴は以下の通りです。
⚫︎地中の根っこを残さず取り除く
⚫︎重機(ユンボ)を使う場合がある
⚫︎根の処分費用が別途必要
⚫︎土地を更地にしたいときに最適
⚫︎シロアリ対策にもつながる
⚫︎作業難度は伐採より高い
抜根が必要になる最大の理由は、木の再生を防ぐためです。伐採後も根が残っていると、木は再び芽を出すことがあり、場合によっては数年後にまた伐採が必要になるケースがあります。
また根が残れば土壌内に空洞ができたり、シロアリの住処になる恐れもあるため、外構工事・駐車場造成・家の建て替えを予定している場合は抜根が必須です。
抜根作業では根の位置や太さ・周囲の構造物(ブロック塀・水道管・配線)を避けながら慎重に掘り進めます。
そのため作業には専門知識が必要で、根が深く広がっているケースでは小型の重機を使うのが一般的です。
特に高さ5m以上の庭木や、植えてから20年以上経っている木は、根が想像以上に強く張っているため、人力での抜根は非常に難しいでしょう。
費用相場としては、小さな庭木で5,000円〜10,000円、大きな木では30,000円〜100,000円と幅があります。
伐採と違い、根をすべて掘り起こすため時間もかかり、地中の石や障害物が見つかれば追加費用が必要になるケースも。
安全性・時間・コストの面から見ても、自分で抜根作業を行うのは現実的ではなく、業者への依頼がもっともスムーズかつ安全な方法となるでしょう。
特に幹が太い木や、長年植わっている庭木は根が深く伸びているため注意!地中で複雑に広がっているため、掘り起こす作業は専門的な技術を要します。
抜根の特徴は以下の通りです。
⚫︎地中の根っこを残さず取り除く
⚫︎重機(ユンボ)を使う場合がある
⚫︎根の処分費用が別途必要
⚫︎土地を更地にしたいときに最適
⚫︎シロアリ対策にもつながる
⚫︎作業難度は伐採より高い
抜根が必要になる最大の理由は、木の再生を防ぐためです。伐採後も根が残っていると、木は再び芽を出すことがあり、場合によっては数年後にまた伐採が必要になるケースがあります。
また根が残れば土壌内に空洞ができたり、シロアリの住処になる恐れもあるため、外構工事・駐車場造成・家の建て替えを予定している場合は抜根が必須です。
抜根作業では根の位置や太さ・周囲の構造物(ブロック塀・水道管・配線)を避けながら慎重に掘り進めます。
そのため作業には専門知識が必要で、根が深く広がっているケースでは小型の重機を使うのが一般的です。
特に高さ5m以上の庭木や、植えてから20年以上経っている木は、根が想像以上に強く張っているため、人力での抜根は非常に難しいでしょう。
費用相場としては、小さな庭木で5,000円〜10,000円、大きな木では30,000円〜100,000円と幅があります。
伐採と違い、根をすべて掘り起こすため時間もかかり、地中の石や障害物が見つかれば追加費用が必要になるケースも。
安全性・時間・コストの面から見ても、自分で抜根作業を行うのは現実的ではなく、業者への依頼がもっともスムーズかつ安全な方法となるでしょう。
それぞれどんな時に選ぶべきか
伐採と抜根は目的が異なるため、状況に応じて正しい方法を選ぶとよいでしょう。ここでは、どちらを選ぶべきか迷っている人向けに、具体的な判断基準を整理しました。
まず選ぶ基準としては、以下を参考にするとよいでしょう。
まず選ぶ基準としては、以下を参考にするとよいでしょう。
| 状況 | 適した作業 |
| 木を倒したいだけ | 伐採 |
| 木が倒れそうで危険 | 伐採 |
| 根から完全に撤去したい | 抜根 |
| 外構工事・駐車場造成をする | 抜根 |
| 木の再生を防ぎたい | 抜根 |
| 費用を抑えたい | 伐採 |
| 大木で危険リスクが高い | 業者依頼で伐採+必要に応じて抜根 |
伐採を選ぶべきケースは、木を倒したいだけや、日当たりを改善したいなど木を地上部から取り除けば問題が解決する状況です。
切り株が残っても支障がない場合は、伐採のみで十分対応できます。また費用を抑えたい場合も伐採が適しています。
一方で抜根が必要なのは、「庭を更地にしたい」「車を停めたい」「外構リフォームをする」「木が再生しては困る」といった、根っこまで取り除く必要があるケースです。
抜根をしないまま工事を進めると地中の根が邪魔になり、施工業者が困ため注意しましょう。
また根が残っていると地面が盛り上がったり、地盤が不安定になったりすることもあるため、長期的に見ても抜根は重要です。
さらに重要なのは、安全性です。特に高さ5〜10m以上の庭木は素人が扱うには危険が大きく、伐採方向の読み違いやチェーンソーの暴発で事故が発生しやすいため注意してください。
大木の処理や家・電線が近い場所の伐採は、必ず専門業者への依頼を検討すべきでしょう。専門業者ならロープワークや高所作業車を使い、安全に木を切り分けながら処理できます。
切り株が残っても支障がない場合は、伐採のみで十分対応できます。また費用を抑えたい場合も伐採が適しています。
一方で抜根が必要なのは、「庭を更地にしたい」「車を停めたい」「外構リフォームをする」「木が再生しては困る」といった、根っこまで取り除く必要があるケースです。
抜根をしないまま工事を進めると地中の根が邪魔になり、施工業者が困ため注意しましょう。
また根が残っていると地面が盛り上がったり、地盤が不安定になったりすることもあるため、長期的に見ても抜根は重要です。
さらに重要なのは、安全性です。特に高さ5〜10m以上の庭木は素人が扱うには危険が大きく、伐採方向の読み違いやチェーンソーの暴発で事故が発生しやすいため注意してください。
大木の処理や家・電線が近い場所の伐採は、必ず専門業者への依頼を検討すべきでしょう。専門業者ならロープワークや高所作業車を使い、安全に木を切り分けながら処理できます。
自分で伐採できる木とできない木の見分け方
庭木の伐採を考えるとき、「自分でできるのか」「業者に依頼すべきなのか」で迷っていませんか。
木の高さや幹の太さだけでなく、周辺環境の安全性・必要な道具・作業スペースなど複数の要素が関わるため、判断を誤ると大きな事故につながります。
安全に作業を進めるための基準が分かれば、無駄な出費やトラブルを避けられるでしょう。
木の高さや幹の太さだけでなく、周辺環境の安全性・必要な道具・作業スペースなど複数の要素が関わるため、判断を誤ると大きな事故につながります。
安全に作業を進めるための基準が分かれば、無駄な出費やトラブルを避けられるでしょう。
高さ3m以下で直径20cm以下なら自分でも可能
木の伐採を自分で行える目安として、高さ3メートル以下・幹の直径20cm以下が一般的な基準になります。
このサイズなら、ノコギリや小型のチェーンソーが扱いやすく、倒れる際の危険性も比較的低いのが特徴。
初心者でも対応できるケースが多いです。ただし「可能=安全」というわけではなく、あくまで適切な準備と手順を踏めばという前提を忘れないようにしましょう。
自分で伐採できる木の条件は以下を目安にしてください。
このサイズなら、ノコギリや小型のチェーンソーが扱いやすく、倒れる際の危険性も比較的低いのが特徴。
初心者でも対応できるケースが多いです。ただし「可能=安全」というわけではなく、あくまで適切な準備と手順を踏めばという前提を忘れないようにしましょう。
自分で伐採できる木の条件は以下を目安にしてください。
| 条件 | 内容 |
| 高さ | 3m以下 |
| 幹の太さ | 20cm以下 |
| 枝の広がり |
周囲に接触しない範囲 |
| 道具の準備 | ノコギリ、チェーンソー、小型脚立 |
| 周辺環境 | 建物・電線・ガラスから離れている |
| 作業人数 | 最低2名(サポート要員含む) |
高さ3メートル以下の木は、倒れる際の勢いが比較的弱いため、方向をコントロールしやすくなります。
しかし伐採の基本である、受け口・追いの切り方を誤ると、倒れる方向がズレてしまい危険です。
幹の太さが20cmを超えると、チェーンソーの刃の長さが不足したり、切断時の振動が大きくなり、初心者では扱いが難しくなるでしょう。
さらに自分で伐採する場合は、安全装備が欠かせません。耐切創グローブや安全靴・フェイスガードなど、最低限の保護具を揃える必要があります。
また作業は一人で行うべきではなく、倒れる方向の監視やロープで木を引っ張る補助員が必要です。
自治体によっては伐採した木や枝葉をそのまま捨てられない場合があるため、処分方法を事前に確認することも大切です。
様々な点を踏まえると、小さな木であっても準備は意外と大変であり、無理に自力でやるより、業者に依頼したほうが結果的に早く、安全かつ安く済むケースも少なくありません。
しかし伐採の基本である、受け口・追いの切り方を誤ると、倒れる方向がズレてしまい危険です。
幹の太さが20cmを超えると、チェーンソーの刃の長さが不足したり、切断時の振動が大きくなり、初心者では扱いが難しくなるでしょう。
さらに自分で伐採する場合は、安全装備が欠かせません。耐切創グローブや安全靴・フェイスガードなど、最低限の保護具を揃える必要があります。
また作業は一人で行うべきではなく、倒れる方向の監視やロープで木を引っ張る補助員が必要です。
自治体によっては伐採した木や枝葉をそのまま捨てられない場合があるため、処分方法を事前に確認することも大切です。
様々な点を踏まえると、小さな木であっても準備は意外と大変であり、無理に自力でやるより、業者に依頼したほうが結果的に早く、安全かつ安く済むケースも少なくありません。
これ以上大きい木は業者に依頼すべき理由
高さ3m以上、幹の太さ20cm以上の木は、素人が伐採するには非常に危険が伴います。木の重さは想像以上で、倒れ方が少しズレただけで塀やガラスを破損したり、最悪の場合は重大事故につながるケースも。
業者に依頼すべき理由は安全性・技術力・処分の利便性の3つが大きなポイントです。
業者に依頼すべき木の特徴は以下の通りです。
⚫︎高さ3m以上、幹が太い
⚫︎周囲に建物・車・電線がある
⚫︎枝が高所に広がっている
⚫︎ロープワークが必要な場面が多い
⚫︎木の傾きが強く倒れる方向が読めない
⚫︎チェーンソーでの切断が必要
木は高さが増すほど倒れる際の力が強くなり、コントロールできる範囲が急激に狭くなります。たとえば高さ5mの木は、直径20cm程度でも数百キロ単位の重量があり、倒れた際に壁やフェンスを破壊する可能性があります。
業者は部分伐採と呼ばれる技術を用い、上部から少しずつ切り落とし、ロープで丁寧に地面へ降ろすため、安全に作業できる点が特徴です。
また倒すスペースが十分に取れない住宅密集地では、高所作業車やクライミング技術(アーボリスト技術)が必要になります。主に専門資格を要する作業であり、一般の方が真似できるものではありません。
さらに伐採後の処分も大きな負担です。大木の幹は非常に重く、一般家庭の車では運搬できないケースが多いです。
業者ならその場で粉砕処理したり、トラックで持ち帰って処分してくれるため、手間と時間を大幅に省けるでしょう。
業者に依頼すべき理由は安全性・技術力・処分の利便性の3つが大きなポイントです。
業者に依頼すべき木の特徴は以下の通りです。
⚫︎高さ3m以上、幹が太い
⚫︎周囲に建物・車・電線がある
⚫︎枝が高所に広がっている
⚫︎ロープワークが必要な場面が多い
⚫︎木の傾きが強く倒れる方向が読めない
⚫︎チェーンソーでの切断が必要
木は高さが増すほど倒れる際の力が強くなり、コントロールできる範囲が急激に狭くなります。たとえば高さ5mの木は、直径20cm程度でも数百キロ単位の重量があり、倒れた際に壁やフェンスを破壊する可能性があります。
業者は部分伐採と呼ばれる技術を用い、上部から少しずつ切り落とし、ロープで丁寧に地面へ降ろすため、安全に作業できる点が特徴です。
また倒すスペースが十分に取れない住宅密集地では、高所作業車やクライミング技術(アーボリスト技術)が必要になります。主に専門資格を要する作業であり、一般の方が真似できるものではありません。
さらに伐採後の処分も大きな負担です。大木の幹は非常に重く、一般家庭の車では運搬できないケースが多いです。
業者ならその場で粉砕処理したり、トラックで持ち帰って処分してくれるため、手間と時間を大幅に省けるでしょう。
周辺環境もチェック!電線や建物が近くにある場合は要注意
伐採の難易度を左右するのは、木の大きさだけではありません。たとえ小さな木でも、電線や建物・ガラス窓・道路・隣家の敷地などが近くにあると、倒す方向が制限され、事故リスクが高まります。周辺環境のチェックは、木を切る前の最重要作業とも言えます。
周辺環境で注意すべきポイントは以下の通りです。
周辺環境で注意すべきポイントは以下の通りです。
| 危険要素 | リスク内容 |
| 電線 | 感電・停電・通信障害 |
| 建物 | 壁・窓の破損、修繕費の発生 |
| 隣家の敷地 |
トラブル・弁償問題 |
| 車・道路 | 交通事故や物損リスク |
| 傾斜地 | 足場の不安定化 |
特に注意すべきなのが電線です。木が少し触れただけでも停電や通信トラブルにつながるケースがあり、場合によっては電力会社へ連絡が必要になる可能性もあります。
自力で伐採しようとして電線に木が倒れかかった場合、高額な賠償になる可能性もゼロではありません。
また住宅密集地では倒すスペースが極端に狭く、木を倒すという発想自体が間違いになります。プロの伐採業者は、木に登って枝を少しずつ切り落とし、ロープでゆっくりと地上に降ろす「吊り切り作業」を行います。
高度な技術があるからこそ、建物のすぐ隣でも安全に作業できるのです。
また風向きや地面の傾き、根の張り方によってもリスクは大きく変化します。すべてを素人が判断するのは難しく、判断ミスは重大事故につながる可能性が。
安全面・近隣トラブル・修繕費のリスクを考えると、周辺環境に不安がある場合は、迷わず業者に依頼するのがおすすめです。
自力で伐採しようとして電線に木が倒れかかった場合、高額な賠償になる可能性もゼロではありません。
また住宅密集地では倒すスペースが極端に狭く、木を倒すという発想自体が間違いになります。プロの伐採業者は、木に登って枝を少しずつ切り落とし、ロープでゆっくりと地上に降ろす「吊り切り作業」を行います。
高度な技術があるからこそ、建物のすぐ隣でも安全に作業できるのです。
また風向きや地面の傾き、根の張り方によってもリスクは大きく変化します。すべてを素人が判断するのは難しく、判断ミスは重大事故につながる可能性が。
安全面・近隣トラブル・修繕費のリスクを考えると、周辺環境に不安がある場合は、迷わず業者に依頼するのがおすすめです。
自分で木を伐採する手順を解説
庭木を自分で伐採したいと思っても、正しい手順や道具がわからず不安になる人は多いでしょう。
木の伐採には危険が伴うため、流れを理解せずに作業すると事故につながる可能性が高くなります。ここでは初心者でも理解できるように「伐採作業の基本手順」を見ていきましょう。
木の伐採には危険が伴うため、流れを理解せずに作業すると事故につながる可能性が高くなります。ここでは初心者でも理解できるように「伐採作業の基本手順」を見ていきましょう。
必要な道具を揃える
木を安全に伐採するためには、切断のための道具だけでなく、自分の身を守る安全装備、作業をスムーズに進める補助道具など、複数のアイテムが必要です。
道具が不十分なまま作業すると、ケガのリスクが高まり、木が予期しない方向へ倒れてしまう可能性もあります。まずは、必ず揃えておきたい道具を整理してみましょう。
道具が不十分なまま作業すると、ケガのリスクが高まり、木が予期しない方向へ倒れてしまう可能性もあります。まずは、必ず揃えておきたい道具を整理してみましょう。
切断に使う道具はノコギリかチェーンソー
伐採の要となるのが、切断用の道具です。木の太さや種類に応じて、ノコギリかチェーンソーを使い分けます。
切断道具の比較は以下の通りです。
切断道具の比較は以下の通りです。
| 道具 | 特徴 | 適した木の太さ |
| 手ノコギリ | 安価で扱いやすい/静かな作業が可能 | 直径10〜15cm程度 |
| 小型チェーンソー | DIY向け/軽量で家庭用に最適 | 直径15〜20cm |
| 中型チェーンソー | パワーが強く早く切れる/扱いには注意が必要 | 直径20cm以上 |
ノコギリは操作が簡単な一方、太い木を切るには時間がかかる点を覚えておきましょう。そのため直径15cm以下の細い庭木に向いています。
チェーンソーはパワーがあるため効率よく作業できますが、振動や反動(キックバック)が強く、正しい持ち方を知らないと危険です。特に直径20cm以上の木を切る場合は、刃の長さやエンジンのパワーが十分なチェーンソーが必要になるケースも。
切断道具の選び方を誤ると、途中で刃が詰まったり、切断中に木が折れて想定外の方向へ倒れる危険があります。
またチェーンソーを使用する際は、事前点検が必須です。チェーンの張り具合やオイルの量・スイッチの反応などを確認してから作業に入ることで、事故の防止につながります。
切断時は常に両手でしっかり支え、足元が安定しているか確認しながら進めるのもポイントです。切断道具は、木の大きさ・作業する人のスキル・周囲の状況を考慮して選びましょう。
チェーンソーはパワーがあるため効率よく作業できますが、振動や反動(キックバック)が強く、正しい持ち方を知らないと危険です。特に直径20cm以上の木を切る場合は、刃の長さやエンジンのパワーが十分なチェーンソーが必要になるケースも。
切断道具の選び方を誤ると、途中で刃が詰まったり、切断中に木が折れて想定外の方向へ倒れる危険があります。
またチェーンソーを使用する際は、事前点検が必須です。チェーンの張り具合やオイルの量・スイッチの反応などを確認してから作業に入ることで、事故の防止につながります。
切断時は常に両手でしっかり支え、足元が安定しているか確認しながら進めるのもポイントです。切断道具は、木の大きさ・作業する人のスキル・周囲の状況を考慮して選びましょう。
安全を守るための装備を忘れずに
伐採作業で最も重要なのが、安全装備です。切断中の木の破片飛散、チェーンソーの反動、枝の落下など、作業中は危険が常に存在します。十分な装備を整えることで、ケガのリスクを大幅に減らせるでしょう。
最低限の安全装備として、以下を用意してください。
⚫︎防護メガネ(飛散物から目を保護)
⚫︎耐切創手袋(チェーンソー対応が望ましい)
⚫︎安全靴(滑りにくく足を守る)
⚫︎ヘルメット(枝落下の危険に備える)
⚫︎厚手の作業着(皮膚の保護)
⚫︎耳栓(チェーンソーの騒音対策)
チェーンソーは非常に音が大きく、長時間作業していると聴覚に影響が出る恐れがあります。そのため耳栓や、イヤーマフは忘れずに準備し、作業を短時間で区切るなど疲労対策も必要です。
また破片が飛んで視界を遮られると判断を誤る原因になるため、防護メガネの着用は必須。作業服は肌をしっかり覆う厚手のものを選び、枝やチェーンソーが直接当たるリスクを減らしましょう。
さらに、伐採作業は見通しが悪い状態で危険が重なりやすいため、一人で行うのは避けるべきです。補助員をつけ、周囲を見守ってもらうだけで事故リスクは大きく低下しますよ。安全装備に、備えすぎはありません。
プロの伐採業者が完全な安全装備をしているのは、それだけリスクが多い作業だからです。道具を揃える段階で安全第一を徹底しましょう。
最低限の安全装備として、以下を用意してください。
⚫︎防護メガネ(飛散物から目を保護)
⚫︎耐切創手袋(チェーンソー対応が望ましい)
⚫︎安全靴(滑りにくく足を守る)
⚫︎ヘルメット(枝落下の危険に備える)
⚫︎厚手の作業着(皮膚の保護)
⚫︎耳栓(チェーンソーの騒音対策)
チェーンソーは非常に音が大きく、長時間作業していると聴覚に影響が出る恐れがあります。そのため耳栓や、イヤーマフは忘れずに準備し、作業を短時間で区切るなど疲労対策も必要です。
また破片が飛んで視界を遮られると判断を誤る原因になるため、防護メガネの着用は必須。作業服は肌をしっかり覆う厚手のものを選び、枝やチェーンソーが直接当たるリスクを減らしましょう。
さらに、伐採作業は見通しが悪い状態で危険が重なりやすいため、一人で行うのは避けるべきです。補助員をつけ、周囲を見守ってもらうだけで事故リスクは大きく低下しますよ。安全装備に、備えすぎはありません。
プロの伐採業者が完全な安全装備をしているのは、それだけリスクが多い作業だからです。道具を揃える段階で安全第一を徹底しましょう。
ロープや脚立など補助的な道具も準備しよう
切断道具だけでなく、木を安全な方向へ倒したり、高所の枝を落としたりする補助道具も必要です。
| 道具 | 役割 |
| ロープ | 木を倒す方向を調整・固定 |
| 脚立 | 高い位置の枝切りに必要 |
| くさび |
受け口・追い口のずれ防止 |
| ガイド棒 | チェーンソー切断時の安定補助 |
| ブルーシート | 茂った枝を集めやすくする |
| 掃除道具 | 切り落とした枝の処分用 |
ロープは木を倒す方向を調整する際に欠かせません。事前に倒したい方向とは反対側にロープをかけ、補助員が一定のテンションで引けば、安全に木を誘導できます。脚立は枝の高さに合わせて選び、転倒しにくい設計のものを優先すると安心です。
また切断中にチェーンソーが木に挟まれるケースがあります。くさびを挟んで隙間を支えれば、刃が動かなくなるのを防げるでしょう。
伐採後の処理も意外と大変で、枝葉が大量に出るため、ブルーシートで広い範囲を覆っておくと後片付けが楽になりますよ。
補助道具を準備せずに作業を始めると、木が思わぬ方向へ倒れる・高い枝が切れないなどのトラブルが起こりやすくなります。安全でスムーズな作業のためにも、補助道具の準備は軽視できません。
また切断中にチェーンソーが木に挟まれるケースがあります。くさびを挟んで隙間を支えれば、刃が動かなくなるのを防げるでしょう。
伐採後の処理も意外と大変で、枝葉が大量に出るため、ブルーシートで広い範囲を覆っておくと後片付けが楽になりますよ。
補助道具を準備せずに作業を始めると、木が思わぬ方向へ倒れる・高い枝が切れないなどのトラブルが起こりやすくなります。安全でスムーズな作業のためにも、補助道具の準備は軽視できません。
倒す方向を決めてロープで固定する
伐採作業で最も重要なのが、倒す方向の決定です。木は重量があり、一度倒れ始めると方向の調整が難しくなるため、倒す方向を誤ると建物やフェンスを損傷する危険があります。
また電線や道路が近い場合は重大事故につながるため、慎重に判断しなければなりません。
倒す方向を決める際に見るべきポイントは以下の通りです。
⚫︎木の傾き
⚫︎枝の重さが偏っている方向
⚫︎周囲の建物・フェンスの位置
⚫︎風向きや風の強さ
⚫︎電線の位置
⚫︎作業スペースの広さ
木は見た目では直立しているように見えても、幹がわずかに傾いていたり、枝が片側に重く伸びています。
この偏りが伐採時の倒れる方向に影響するため、事前観察は欠かせません。風が強い日や不規則な風向きの日は、伐採作業を避けるのが安全です。
倒す方向を決めたら、ロープを幹の高い位置に結び、補助員が一定の力で引きつつ倒れる方向をサポートします。ロープを使えば木の倒れる勢いをコントロールしやすくなり、方向ブレを防げるためです。
さらに倒す方向に十分なスペースがあるか確認し、近隣への影響も考慮する必要があります。
作業中に木が道路側へ倒れると交通事故を招く恐れがあり、電線にかかると停電トラブルの原因になります。倒す方向の判断は、伐採作業の成功率を左右する大切な作業です。
また電線や道路が近い場合は重大事故につながるため、慎重に判断しなければなりません。
倒す方向を決める際に見るべきポイントは以下の通りです。
⚫︎木の傾き
⚫︎枝の重さが偏っている方向
⚫︎周囲の建物・フェンスの位置
⚫︎風向きや風の強さ
⚫︎電線の位置
⚫︎作業スペースの広さ
木は見た目では直立しているように見えても、幹がわずかに傾いていたり、枝が片側に重く伸びています。
この偏りが伐採時の倒れる方向に影響するため、事前観察は欠かせません。風が強い日や不規則な風向きの日は、伐採作業を避けるのが安全です。
倒す方向を決めたら、ロープを幹の高い位置に結び、補助員が一定の力で引きつつ倒れる方向をサポートします。ロープを使えば木の倒れる勢いをコントロールしやすくなり、方向ブレを防げるためです。
さらに倒す方向に十分なスペースがあるか確認し、近隣への影響も考慮する必要があります。
作業中に木が道路側へ倒れると交通事故を招く恐れがあり、電線にかかると停電トラブルの原因になります。倒す方向の判断は、伐採作業の成功率を左右する大切な作業です。
邪魔な枝を事前に切り落としておく
幹を切り倒す前に、枝を先に落としておくことで安全性と作業効率が大幅に向上します。枝が多いまま伐採すると、倒れる方向に引っかかるものが増え、思わぬ方向へ倒れる原因になるため注意しましょう。
事前の枝落としが必要な理由は以下の通りです。
事前の枝落としが必要な理由は以下の通りです。
| 理由 | 説明 |
| 倒れる方向を制御しやすい |
重心が整うため正確な方向へ倒れる |
| 近隣の建物への接触を防ぐ | 枝が引っかかる事故を防ぐ |
| 作業スペースが広くなる |
足場の確保が容易 |
| チェーンソーの作業性向上 | 幹が見やすく安全に切断できる |
枝落としでは、軽い枝から順に落としていくと安全です。下から切ると枝が頭上に落ちるリスクがあるため、基本は上から順に切り落としましょう。
ただし高所の枝を自力で切るのは危険が伴うため、脚立を使う場合は転倒に注意し、必ず補助員を配置してください。
枝を落とすことで木の重心が中心に戻り、倒れる方向をコントロールしやすくなります。特に庭木は片側の光を求めて成長するため、枝の偏りが大きくなりがち。偏りを解消しないまま伐採すると、想定外の方向へ倒れる原因になります。
さらに枝落としは作業スペースを確保する意味でも重要です。広いスペースがあると、チェーンソーを使う際に姿勢が安定し、安全な作業ができます。枝落としは伐採前の“準備として最も重要な工程”と言っても過言ではありません。
ただし高所の枝を自力で切るのは危険が伴うため、脚立を使う場合は転倒に注意し、必ず補助員を配置してください。
枝を落とすことで木の重心が中心に戻り、倒れる方向をコントロールしやすくなります。特に庭木は片側の光を求めて成長するため、枝の偏りが大きくなりがち。偏りを解消しないまま伐採すると、想定外の方向へ倒れる原因になります。
さらに枝落としは作業スペースを確保する意味でも重要です。広いスペースがあると、チェーンソーを使う際に姿勢が安定し、安全な作業ができます。枝落としは伐採前の“準備として最も重要な工程”と言っても過言ではありません。
受け口と追い口を正しく入れて安全に倒す
伐採の核心となるのが受け口と、追い口の作り方です。この2つの切り込みが正しく入っていないと、木が意図しない方向へ倒れて危険が増します。
受け口は、木が倒れる方向のガイドとなる部分です。受け口の角度が狭すぎると木が途中でひっかかり、倒れにくくなります。
広すぎても木の支えが弱くなるため、45度前後が最も安定する点を覚えておきましょう。
追い口はその反対側から入れる切り込みで、受け口よりやや高い位置から切るのが安全です。段差があることで倒れる方向が一定になり、均等に力が逃げていきます。
追い口を入れる際は、チェーンソーが木に挟まれないよう注意します。角度が悪かったり、受け口が浅かったりすると、途中でチェーンソーが動かなくなり作業が止まるケースも。
この場合、くさびを挟んで隙間を広げながら慎重に切り進めると安全です。
木が傾き始めたら、チェーンソーはすぐに止め、倒れる方向から速やかに離れましょう。木が完全に倒れるまで近づかないようにする点も重要です。
受け口と追い口は伐採手順の中で最も事故が起こりやすい工程であり、慎重に行いたい作業といえます。
受け口は、木が倒れる方向のガイドとなる部分です。受け口の角度が狭すぎると木が途中でひっかかり、倒れにくくなります。
広すぎても木の支えが弱くなるため、45度前後が最も安定する点を覚えておきましょう。
追い口はその反対側から入れる切り込みで、受け口よりやや高い位置から切るのが安全です。段差があることで倒れる方向が一定になり、均等に力が逃げていきます。
追い口を入れる際は、チェーンソーが木に挟まれないよう注意します。角度が悪かったり、受け口が浅かったりすると、途中でチェーンソーが動かなくなり作業が止まるケースも。
この場合、くさびを挟んで隙間を広げながら慎重に切り進めると安全です。
木が傾き始めたら、チェーンソーはすぐに止め、倒れる方向から速やかに離れましょう。木が完全に倒れるまで近づかないようにする点も重要です。
受け口と追い口は伐採手順の中で最も事故が起こりやすい工程であり、慎重に行いたい作業といえます。
倒した後は適切なサイズに切り分ける
木を倒した後は、適切なサイズに切り分けて処分しやすくします。伐採後の木は重量があり、運ぶだけでも大きな負担になるため、扱いやすい大きさに整理しましょう。
切り分け作業のポイントは以下の通りです。
切り分け作業のポイントは以下の通りです。
| 作業内容 | 目的 |
| 幹を50〜80cmごとに切る | 持ち運びしやすくする |
| 枝葉を細かく切る | ゴミ袋に入れやすくする |
| 根元の整形 | 切り株の高さ調整 |
| ブルーシートでまとめる | 掃除が簡単になる |
倒した木は意外と重く、太い幹であれば1本だけでも持ち上げるのが難しいケースがあります。そのため、持ち運びやすいサイズに切り分けておくとよいでしょう。
チェーンソーで切る際は、木が転がらないよう固定し、安定した姿勢で作業するのがポイントです。
枝葉は自治体によって処分ルールが異なるため、事前に確認しておきましょう。多くの地域では、指定袋に入るサイズや長さの上限が決められています。
ブルーシートの上に枝葉を落とせば、掃除がスムーズになり、作業時間の短縮につながりますよ。
太い幹は処分費用が別途発生する場合があり、軽トラックなどの運搬手段が必要になるケースもあります。
様々な手間や費用を考えると、自分で伐採するメリットが小さく感じられるかもしれません。倒した後の処理や処分作業まで含めると、業者に任せたほうが効率的な場合も多いです。
チェーンソーで切る際は、木が転がらないよう固定し、安定した姿勢で作業するのがポイントです。
枝葉は自治体によって処分ルールが異なるため、事前に確認しておきましょう。多くの地域では、指定袋に入るサイズや長さの上限が決められています。
ブルーシートの上に枝葉を落とせば、掃除がスムーズになり、作業時間の短縮につながりますよ。
太い幹は処分費用が別途発生する場合があり、軽トラックなどの運搬手段が必要になるケースもあります。
様々な手間や費用を考えると、自分で伐採するメリットが小さく感じられるかもしれません。倒した後の処理や処分作業まで含めると、業者に任せたほうが効率的な場合も多いです。
木の伐採に適した時期はいつ?季節ごとの違い
木の伐採は行うタイミングによって作業の難易度や費用、安全性が大きく変わります。木の状態は季節によって水分量や重さが異なり、切り倒した後の処分のしやすさも変化する点を覚えておきましょう。
また木が育つ成長期や、雨が続く梅雨は作業リスクが高くなるため、伐採時期を慎重に選ぶのがコツ。
ここでは季節ごとの特徴や最適な伐採時期、避けたほうがよい時期についてわかりやすく解説します。
また木が育つ成長期や、雨が続く梅雨は作業リスクが高くなるため、伐採時期を慎重に選ぶのがコツ。
ここでは季節ごとの特徴や最適な伐採時期、避けたほうがよい時期についてわかりやすく解説します。
冬が最適な理由は木が軽くて扱いやすいから
木の伐採に最も適した季節は冬です。落葉樹の葉が落ちて軽くなり、木全体の水分量が減るため、伐採作業がしやすくなります。
枝葉の量が減ることで倒れる方向を見極めやすく、チェーンソーの刃の進みもスムーズになります。
冬に伐採が適している理由は以下の通りです。
枝葉の量が減ることで倒れる方向を見極めやすく、チェーンソーの刃の進みもスムーズになります。
冬に伐採が適している理由は以下の通りです。
| 理由 | 説明 |
| 木の水分量が少ない | 軽くなるため切断しやすい |
| 枝葉が少ない | 倒れる方向が安定しやすい |
| 虫が少ない | 作業中のトラブルが少ない |
| 成長が止まっている | ダメージが最小限で庭木にやさしい |
| 作業日程が組みやすい | 業者の繁忙期を避けられることも |
冬は木が休眠期に入り、成長が止まることで樹液の流れが緩やかになります。樹液が少ない状態の木は軽いため、伐採時の倒れるスピードや安定性を読みやすくなる点がメリット。
特に高さがある木や太い幹の庭木では、重さの違いが作業の安全性に関係します。
また落葉樹の場合は枝葉がほとんど落ちているため、伐採時の視界が広がり、枝が他の樹木や建物に引っかかるリスクが低くなります。虫が少なく、害虫対策をする必要がないのも冬のメリットです。
他にも業者に依頼する場合も冬はメリットがあります。外構工事の繁忙期が過ぎて比較的スケジュールが取りやすく、費用の交渉がしやすい場合も。
作業員の安全面から見ても、夏のように熱中症のリスクがなく、安定した作業が可能でしょう。伐採の条件を考えると、冬はメリットが最も多い季節と言えます。
特に高さがある木や太い幹の庭木では、重さの違いが作業の安全性に関係します。
また落葉樹の場合は枝葉がほとんど落ちているため、伐採時の視界が広がり、枝が他の樹木や建物に引っかかるリスクが低くなります。虫が少なく、害虫対策をする必要がないのも冬のメリットです。
他にも業者に依頼する場合も冬はメリットがあります。外構工事の繁忙期が過ぎて比較的スケジュールが取りやすく、費用の交渉がしやすい場合も。
作業員の安全面から見ても、夏のように熱中症のリスクがなく、安定した作業が可能でしょう。伐採の条件を考えると、冬はメリットが最も多い季節と言えます。
避けたい時期は梅雨と成長期
伐採に適さない時期として、梅雨と木の成長期(春〜初夏)が挙げられます。梅雨と木の成長期(春〜初夏)の時期は木の水分量が多く、雨による作業リスクも高いため、可能であれば避けたほうがよいでしょう。
避けたい時期と理由は以下の通りです。
⚫︎梅雨は地面が滑りやすい
⚫︎雨による視界不良でチェーンソー作業が危険
⚫︎湿気で木が重くなり倒れる方向が読みにくい
⚫︎春〜初夏は木が成長期で水分量が多い
⚫︎枝葉が大きく広がり作業性が低下
⚫︎害虫が増えるため危険が増す
梅雨時期は地面がぬかるんでおり、脚立が安定しにくく、作業員が滑る危険性があります。チェーンソーの扱いは少しのバランスの崩れが重大事故につながるため、雨天の伐採は避けるべきです。
雨で木が重くなることで倒れる方向の予測も難しくなり、ロープでの調整も不安定になるでしょう。
その後、春から初夏にかけては木が成長期に入り、水分を多く吸い上げています。樹液が多い状態の木は重く、切断時の抵抗が増えるため、作業に時間がかかるだけでなく倒れる際の勢いが強くなる点に注意しましょう。
また枝葉が茂っていると伐採時の視界が狭くなり、周囲の建物や電線に接触しやすくなるため危険性が増します。
さらに暖かい季節は害虫や蜂などの発生も多く、伐採中に刺されたり巣を刺激するリスクも。作業者の安全だけでなく、近隣トラブルの観点からも、春〜初夏の伐採は十分注意が必要です。
避けたい時期と理由は以下の通りです。
⚫︎梅雨は地面が滑りやすい
⚫︎雨による視界不良でチェーンソー作業が危険
⚫︎湿気で木が重くなり倒れる方向が読みにくい
⚫︎春〜初夏は木が成長期で水分量が多い
⚫︎枝葉が大きく広がり作業性が低下
⚫︎害虫が増えるため危険が増す
梅雨時期は地面がぬかるんでおり、脚立が安定しにくく、作業員が滑る危険性があります。チェーンソーの扱いは少しのバランスの崩れが重大事故につながるため、雨天の伐採は避けるべきです。
雨で木が重くなることで倒れる方向の予測も難しくなり、ロープでの調整も不安定になるでしょう。
その後、春から初夏にかけては木が成長期に入り、水分を多く吸い上げています。樹液が多い状態の木は重く、切断時の抵抗が増えるため、作業に時間がかかるだけでなく倒れる際の勢いが強くなる点に注意しましょう。
また枝葉が茂っていると伐採時の視界が狭くなり、周囲の建物や電線に接触しやすくなるため危険性が増します。
さらに暖かい季節は害虫や蜂などの発生も多く、伐採中に刺されたり巣を刺激するリスクも。作業者の安全だけでなく、近隣トラブルの観点からも、春〜初夏の伐採は十分注意が必要です。
縁起を担ぐなら土用の日を避ける人もいる
昔から、伐採は縁起に関わる作業と考えられてきました。特に日本では、土用の期間(立春・立夏・立秋・立冬の前18日間)は土を動かすのを避けるといった風習があります。
伐採と縁起の関係には諸説ありますが、おおむね以下の通りです。
伐採と縁起の関係には諸説ありますが、おおむね以下の通りです。
| 風習内容 | 説明 |
| 土用に伐採を避ける | 土の神が怒るとされている |
| 大木は特に慎重に扱う | “家の守り木”と捉える地域もある |
| 引っ越しや工事も避けることが多い | 土を傷つける行為と考えられてきた |
土用に伐採を避ける風習は地域や家庭によって大きく異なります。現代では必ず守らなければならないものではありませんが、家族の考え方や地域の風習によっては重視されるケースも。
特に大きな木や長年庭にあった木は守り木とされていたり、家族の思い出と結びついていることが多く、心理的な抵抗が生まれるケースがあります。
業者に依頼する場合も、土用期間を避けたいという希望を伝えると柔軟に対応してくれるでしょう。縁起面を配慮することで、家族が納得しやすくなり、伐採後の後悔を減らせる点も◎。
伐採は物理的な作業にとどまらず、心理面や地域の慣習も関係する作業です。作業の安全性だけでなく、縁起を重視したい場合は日程調整を行うと安心できるでしょう。
特に大きな木や長年庭にあった木は守り木とされていたり、家族の思い出と結びついていることが多く、心理的な抵抗が生まれるケースがあります。
業者に依頼する場合も、土用期間を避けたいという希望を伝えると柔軟に対応してくれるでしょう。縁起面を配慮することで、家族が納得しやすくなり、伐採後の後悔を減らせる点も◎。
伐採は物理的な作業にとどまらず、心理面や地域の慣習も関係する作業です。作業の安全性だけでなく、縁起を重視したい場合は日程調整を行うと安心できるでしょう。
業者に木の伐採を依頼した場合の費用相場
伐採を業者に依頼する場合、最も気になるポイントが費用です。木の高さや幹の太さ・作業場所の環境によって金額が大きく変わります。
また伐採だけでなく抜根や処分費用が別途かかるため、全体の費用を把握しておくとよいでしょう。ここでは一般的な費用相場をわかりやすくまとめます。
また伐採だけでなく抜根や処分費用が別途かかるため、全体の費用を把握しておくとよいでしょう。ここでは一般的な費用相場をわかりやすくまとめます。
木の高さ別に見る費用の目安
木の伐採費用は高さで大きく変わります。おおよその相場は以下を参考にしてください。
| 木の高さ | 費用相場 |
| 〜3m | 5000〜20000円 |
| 3〜5m | 15000〜40000円 |
| 5〜7m | 30000〜80000円 |
| 7〜10m | 50000〜150000円 |
| 10m以上 | 要見積もり(高所作業車が必要) |
高さが増すほど作業の難易度が上がり、費用も高くなります。5m以上の木は自力で伐採するには非常に危険で、専門技術が必要。
高所作業車やロープワークを使用しながら、枝を少しずつ切り落としていく吊り切り作業が行われるため、通常の伐採よりも時間と人員が必要です。
また木が傾いていたり、建物や電線の近くにある場合は追加料金が発生しやすい点に注意。業者によって料金体系が異なるため複数見積もりを取り、作業内容まで確認しましょう。
高所作業車やロープワークを使用しながら、枝を少しずつ切り落としていく吊り切り作業が行われるため、通常の伐採よりも時間と人員が必要です。
また木が傾いていたり、建物や電線の近くにある場合は追加料金が発生しやすい点に注意。業者によって料金体系が異なるため複数見積もりを取り、作業内容まで確認しましょう。
抜根まで依頼すると追加費用
ただし伐採した木の根っこを完全に取り除く「抜根」は、伐採よりも費用がかかります。相場は以下を参考にしてください。
| 木のサイズ | 抜根費用 |
| 小サイズ(〜3m) | 5,000〜15,000円 |
| 中サイズ(3〜5m) | 10,000〜30,000円 |
| 大サイズ(5m以上) | 30,000〜100,000円 |
抜根は地中の根を掘り起こす作業であるため、伐採以上に体力と技術を必要とします。根は複雑に張り巡らされており、水道管やブロック塀に近い場合は慎重な作業が必要です。大きな木の場合は重機を使うことも多く、その分費用が上がります。
また庭をそのまま整地したい、外構工事を予定している場合などは抜根が欠かせません。伐採だけでは再び芽が出ることがあるため、完全に処理したい場合は抜根まで依頼するのが安全です。
また庭をそのまま整地したい、外構工事を予定している場合などは抜根が欠かせません。伐採だけでは再び芽が出ることがあるため、完全に処理したい場合は抜根まで依頼するのが安全です。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 作業費 | 人件費・時間単価など | 約5,000〜20,000円 |
| 重機費 | クレーン車・高所作業車など | 約10,000〜30,000円 |
| 処分費 | 切った枝・幹の運搬と廃棄 |
約5,000〜20,000円/人 |
| 抜根費 | 根を掘り出す作業 |
約10,000〜50,000円 |
| 安全対策費 | ロープ作業・交通誘導員など | 約5,000〜15,000円 |
伐採した木の処分方法と費用について
伐採後の木は想像以上に量が多く、処分にも費用がかかります。処分費用の目安は以下の通りです。
⚫︎枝葉の処分…3,000〜10,000円
⚫︎幹の処分…5,000〜20,000円
⚫︎大量の場合…軽トラ1台分で10,000〜30,000円
枝葉は軽いもののかさばるため、袋に入れて出せない量が一度に発生します。自治体のルールによっては「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの規制があり、超える場合は粗大ごみ扱いになる点に注意しましょう。幹は重量があるため、運搬にはトラックが必要です。
業者に依頼すると、その場で粉砕処理(チッパー作業)を行ってくれる場合もあり、処分費用が抑えられることがあります。処分方法を含めて見積もりを比較することで、最終的な費用を抑えられるでしょう。
⚫︎枝葉の処分…3,000〜10,000円
⚫︎幹の処分…5,000〜20,000円
⚫︎大量の場合…軽トラ1台分で10,000〜30,000円
枝葉は軽いもののかさばるため、袋に入れて出せない量が一度に発生します。自治体のルールによっては「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの規制があり、超える場合は粗大ごみ扱いになる点に注意しましょう。幹は重量があるため、運搬にはトラックが必要です。
業者に依頼すると、その場で粉砕処理(チッパー作業)を行ってくれる場合もあり、処分費用が抑えられることがあります。処分方法を含めて見積もりを比較することで、最終的な費用を抑えられるでしょう。
木の伐採についてよくある質問
ここでは木の伐採に関して特に寄せられる質問に回答します。
高さ何メートルまでなら自分で伐採できますか?
伐採を自分で行えるかどうかは、木の「高さ」と「幹の直径」で判断するのが一般的です。安全に作業できる基準を超える木は、素人では対応が難しく、業者に依頼するのが最も安全な方法になります。
自分で伐採可能な木の基準は以下の通りです。
自分で伐採可能な木の基準は以下の通りです。
| 項目 | 基準 |
| 高さ | 3m以下 |
| 幹の太さ | 直径20cm以下 |
| 枝の広がり | 建物・電線から離れている |
| 必要道具 | ノコギリor小型チェーンソー |
| 作業人数 | 2名以上(補助員必須) |
高さ3m以下・直径20cm以下の木は比較的扱いやすく、自分で伐採しても大きな危険が生まれにくいサイズです。
小型のチェーンソーやノコギリでも切断しやすく、倒れる際の勢いも弱いため、倒す方向をコントロールしやすいでしょう。
ただし「安全にできる」といった意味ではなく、準備と技術があれば可能レベルである点には注意が必要です。
一方で高さ4〜5mを超える木は、素人では非常に危険です。倒れる勢いが大きくなり、方向がわずかにズレただけで塀や窓を破損する可能性があります。
特に住宅密集地では、倒すスペースが足りず、木登り伐採(アーボリスト技術)が必要になるケースも。
また風の強さや木の傾き・枝の量・周囲の安全確保など、判断すべきポイントが多く、見た目だけで「簡単に切れそう」と判断するのは非常に危険です。
大きな木ほどプロの技術が必要となるため、無理に自分で作業せず、業者への依頼を検討しましょう。
小型のチェーンソーやノコギリでも切断しやすく、倒れる際の勢いも弱いため、倒す方向をコントロールしやすいでしょう。
ただし「安全にできる」といった意味ではなく、準備と技術があれば可能レベルである点には注意が必要です。
一方で高さ4〜5mを超える木は、素人では非常に危険です。倒れる勢いが大きくなり、方向がわずかにズレただけで塀や窓を破損する可能性があります。
特に住宅密集地では、倒すスペースが足りず、木登り伐採(アーボリスト技術)が必要になるケースも。
また風の強さや木の傾き・枝の量・周囲の安全確保など、判断すべきポイントが多く、見た目だけで「簡単に切れそう」と判断するのは非常に危険です。
大きな木ほどプロの技術が必要となるため、無理に自分で作業せず、業者への依頼を検討しましょう。
大きな木を伐採する際の注意点や危険なことは?
大きな木の伐採は、危険が非常に多く潜んでいます。木の重さ・高さ・倒れる勢いが素人の予想を大きく超えることがあり、毎年多くの事故が報告されています。
大きな木の伐採で起こりやすい危険には以下が挙げられます。
⚫︎倒れる方向のズレによる事故
⚫︎チェーンソーのキックバック
⚫︎枝の落下による怪我
⚫︎隣家や車の破損
⚫︎電線に接触して停電事故
⚫︎根の張り具合による倒木の予測不能
⚫︎高所作業中の転落
大きな木は重心が高く、少しの角度の誤差や風の影響でも倒れる方向が変わります。幹が倒れる力は数百キロにも達し、素人がロープで調整するだけでは制御しきれません。
特に住宅街では建物や駐車場が近いため、一方向に倒せないケースがほとんどです。
またチェーンソーを扱い慣れていない場合、刃が跳ね返るキックバックが発生しやすく、非常に危険です。高所での枝落としは滑落事故につながるため素人が対応するのは大変危険です。
プロの伐採業者は、木登り技術やロープワークを駆使し、木を少しずつ切り分けて下ろす吊り切り作業を行います。この技術は専門訓練を受けた作業員でなければできません。
さらに電線に近い場合は停電や感電事故のリスクがあり、電気会社への連絡が必要なケースも。危険なリスクを正しく判断するには専門知識が必須です。
大きな木を安全に伐採するには、経験・道具・人員が揃ったプロに依頼することが唯一の安全策と言えます。
大きな木の伐採で起こりやすい危険には以下が挙げられます。
⚫︎倒れる方向のズレによる事故
⚫︎チェーンソーのキックバック
⚫︎枝の落下による怪我
⚫︎隣家や車の破損
⚫︎電線に接触して停電事故
⚫︎根の張り具合による倒木の予測不能
⚫︎高所作業中の転落
大きな木は重心が高く、少しの角度の誤差や風の影響でも倒れる方向が変わります。幹が倒れる力は数百キロにも達し、素人がロープで調整するだけでは制御しきれません。
特に住宅街では建物や駐車場が近いため、一方向に倒せないケースがほとんどです。
またチェーンソーを扱い慣れていない場合、刃が跳ね返るキックバックが発生しやすく、非常に危険です。高所での枝落としは滑落事故につながるため素人が対応するのは大変危険です。
プロの伐採業者は、木登り技術やロープワークを駆使し、木を少しずつ切り分けて下ろす吊り切り作業を行います。この技術は専門訓練を受けた作業員でなければできません。
さらに電線に近い場合は停電や感電事故のリスクがあり、電気会社への連絡が必要なケースも。危険なリスクを正しく判断するには専門知識が必須です。
大きな木を安全に伐採するには、経験・道具・人員が揃ったプロに依頼することが唯一の安全策と言えます。
木の伐採後の処分方法は?
伐採後の木は想像以上に量があり、処分方法が分からないという相談が非常に多いです。処分には自治体ルールが関係しており、事前確認が必須となります。伐採後の処分方法としては、以下の方法を参考にしてください。
| 処分方法 | 特徴 |
| 自治体のゴミ回収 | 長さ・太さの規定がある場合が多い |
| 粗大ごみとして回収 |
追加料金が必要 |
| 自分で清掃センターへ持ち込み | 手間はかかるが安価 |
| 業者に処分まで依頼 |
最も楽・安全で確実 |
| 薪として再利用 |
小さな庭木に向く |
伐採した木は太さや量によって処分の手間が大きく変わります。自治体の一般ごみとして出すには、「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの細かい規定があり、規定を超える場合は粗大ごみ扱いになります。
幹が太い木は重量があるため、持ち運ぶだけでも大変です。
自分で清掃センターへ持ち込む方法もありますが、軽トラックが必要だったり、量によっては手数料が発生したりします。庭木の量が多い場合は作業負担が大きくなりがちです。
業者はその場で木を粉砕する専用機械(チッパー)を使用する場合もあり、大量の枝や幹でもスムーズに処分できます。
費用はかかるものの、時間・労力・リスクを考えると最もおすすめの方法です。
幹が太い木は重量があるため、持ち運ぶだけでも大変です。
自分で清掃センターへ持ち込む方法もありますが、軽トラックが必要だったり、量によっては手数料が発生したりします。庭木の量が多い場合は作業負担が大きくなりがちです。
業者はその場で木を粉砕する専用機械(チッパー)を使用する場合もあり、大量の枝や幹でもスムーズに処分できます。
費用はかかるものの、時間・労力・リスクを考えると最もおすすめの方法です。
木の伐採はお庭の大将にお任せください
木の伐採は一見簡単に見えても、実際は高度な判断と安全対策が必要な作業です。「自分でできるか不安」「大きな木で危険そう」「処分までまとめて頼みたい」という方は、プロに任せることで安心して問題を解決できます。
お庭の大将では、庭木一本の小規模伐採から、大木の特殊伐採・抜根まで幅広く対応しています。
資格を持つスタッフが現地調査を行い、周囲の安全確保・作業工程・費用までわかりやすく説明するため、初めての方でも安心です。また、事前の見積もりは無料で、追加料金の心配もありません。
伐採後の処分や整地まで一括対応可能。「とにかくすべて任せたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
お庭の大将では、庭木一本の小規模伐採から、大木の特殊伐採・抜根まで幅広く対応しています。
資格を持つスタッフが現地調査を行い、周囲の安全確保・作業工程・費用までわかりやすく説明するため、初めての方でも安心です。また、事前の見積もりは無料で、追加料金の心配もありません。
伐採後の処分や整地まで一括対応可能。「とにかくすべて任せたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

「庭の木を伐採したいけれど、どこから手をつければいいのか分からない…」
そんな悩みを抱えてはいませんか。
木の伐採は一度の判断ミスで事故や近隣トラブルにつながりやすく、素人では危険を見抜きづらい作業です。
木 伐採は 木のサイズ・場所・危険度によって最適な方法が異なります。
本記事では、自分で伐採できる木の条件、安全な作業手順、業者に依頼する場合の費用相場・伐採に適した時期など、正しい判断に必要な情報を解説します。
この記事を読むことで、初めての伐採で不安な方でも、迷わず行動に移せるようになるでしょう。
そんな悩みを抱えてはいませんか。
木の伐採は一度の判断ミスで事故や近隣トラブルにつながりやすく、素人では危険を見抜きづらい作業です。
木 伐採は 木のサイズ・場所・危険度によって最適な方法が異なります。
本記事では、自分で伐採できる木の条件、安全な作業手順、業者に依頼する場合の費用相場・伐採に適した時期など、正しい判断に必要な情報を解説します。
この記事を読むことで、初めての伐採で不安な方でも、迷わず行動に移せるようになるでしょう。
木の伐採とは?抜根との違いを理解しよう
庭木の手入れで、伐採と抜根の違いがよく分からず迷っていませんか。どちらの作業も木を処理する目的で行われますが、作業内容・費用・必要な道具・作業時間が大きく異なるため、誤って選んでしまうと余計なコストやリスクが発生します。
ここでは伐採の基本的な意味や作業工程・抜根との違い、それぞれを選ぶべきタイミングについて見ていきましょう。
ここでは伐採の基本的な意味や作業工程・抜根との違い、それぞれを選ぶべきタイミングについて見ていきましょう。
伐採は木を根元から切り倒す作業
伐採とは、木を根元付近で切り倒す作業を指します。チェーンソーや、ノコギリを使い、幹の太さや高さに合わせて安全に木を切り落とすのが一般的。
切り倒した後には、切り株が残り、根っこ自体は地中のまま残ります。伐採は庭木だけでなく、街路樹・山林・店舗や建物周辺の危険木にも行われる重要な作業です。
伐採の特徴をまとめると以下の通りです。
切り倒した後には、切り株が残り、根っこ自体は地中のまま残ります。伐採は庭木だけでなく、街路樹・山林・店舗や建物周辺の危険木にも行われる重要な作業です。
伐採の特徴をまとめると以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 作業内容 | 木を根元近くから切り倒す |
| 道具 | ノコギリ、チェーンソー、ロープ、保護具 |
| 残るもの |
切り株・根っこ |
| 作業時間 | 木の大きさにより30分〜半日 |
| 費用相場 | 庭木の伐採:5,000円〜50,000円(高さ・太さで変動) |
| リスク | 倒れる方向の誤り、チェーンソー事故、周囲の破損 |
伐採では、受け口と呼ばれる切り込みを倒したい方向に入れ、追い口を反対側に入れて、木が想定した方向に倒れるよう調整します。
受け口の工程が不十分だと、木が違う方向へ倒れ、家屋・塀・車などを破損する可能性が。
さらに慣れない人がチェーンソーを使うのは非常に危険で、年間でも多くの事故が報告されています。作業中はゴーグル・耳栓・安全靴・グローブなど、十分な保護具が欠かせません。
また伐採は切って倒すだけのシンプルな作業と思われがちですが、実際には倒れた木の処分・搬出が大きな労力になります。
幹の太さが20cmを超える木は大変重く、一人で運ぶのが難しいでしょう。さらに枝葉の処分は自治体によって、ルールが異なるため注意が必要です。
多くの地域では、可燃ごみとして出せる量が限られているため、軽トラックで運ぶなど大掛かりになる場合があるでしょう。
業者に依頼するメリットは、作業の安全性が高いだけでなく、倒れた木の処分までまとめて依頼できる点です。
特に高さ5メートルを超える木や、家や電線が近い場所に植わっている木は、素人が伐採するには危険が伴うケースも。プロに任せるほうが結果的に安く済むケースも多いです。
受け口の工程が不十分だと、木が違う方向へ倒れ、家屋・塀・車などを破損する可能性が。
さらに慣れない人がチェーンソーを使うのは非常に危険で、年間でも多くの事故が報告されています。作業中はゴーグル・耳栓・安全靴・グローブなど、十分な保護具が欠かせません。
また伐採は切って倒すだけのシンプルな作業と思われがちですが、実際には倒れた木の処分・搬出が大きな労力になります。
幹の太さが20cmを超える木は大変重く、一人で運ぶのが難しいでしょう。さらに枝葉の処分は自治体によって、ルールが異なるため注意が必要です。
多くの地域では、可燃ごみとして出せる量が限られているため、軽トラックで運ぶなど大掛かりになる場合があるでしょう。
業者に依頼するメリットは、作業の安全性が高いだけでなく、倒れた木の処分までまとめて依頼できる点です。
特に高さ5メートルを超える木や、家や電線が近い場所に植わっている木は、素人が伐採するには危険が伴うケースも。プロに任せるほうが結果的に安く済むケースも多いです。
抜根は根っこまで完全に取り除く作業
抜根(ばっこん)とは、伐採後に地中の「根っこ」まで完全に取り除く作業です。木の表面だけでなく、地中に残った根全体を掘り起こし、撤去するため、伐採より大幅に手間と費用がかかります。
特に幹が太い木や、長年植わっている庭木は根が深く伸びているため注意!地中で複雑に広がっているため、掘り起こす作業は専門的な技術を要します。
抜根の特徴は以下の通りです。
⚫︎地中の根っこを残さず取り除く
⚫︎重機(ユンボ)を使う場合がある
⚫︎根の処分費用が別途必要
⚫︎土地を更地にしたいときに最適
⚫︎シロアリ対策にもつながる
⚫︎作業難度は伐採より高い
抜根が必要になる最大の理由は、木の再生を防ぐためです。伐採後も根が残っていると、木は再び芽を出すことがあり、場合によっては数年後にまた伐採が必要になるケースがあります。
また根が残れば土壌内に空洞ができたり、シロアリの住処になる恐れもあるため、外構工事・駐車場造成・家の建て替えを予定している場合は抜根が必須です。
抜根作業では根の位置や太さ・周囲の構造物(ブロック塀・水道管・配線)を避けながら慎重に掘り進めます。
そのため作業には専門知識が必要で、根が深く広がっているケースでは小型の重機を使うのが一般的です。
特に高さ5m以上の庭木や、植えてから20年以上経っている木は、根が想像以上に強く張っているため、人力での抜根は非常に難しいでしょう。
費用相場としては、小さな庭木で5,000円〜10,000円、大きな木では30,000円〜100,000円と幅があります。
伐採と違い、根をすべて掘り起こすため時間もかかり、地中の石や障害物が見つかれば追加費用が必要になるケースも。
安全性・時間・コストの面から見ても、自分で抜根作業を行うのは現実的ではなく、業者への依頼がもっともスムーズかつ安全な方法となるでしょう。
特に幹が太い木や、長年植わっている庭木は根が深く伸びているため注意!地中で複雑に広がっているため、掘り起こす作業は専門的な技術を要します。
抜根の特徴は以下の通りです。
⚫︎地中の根っこを残さず取り除く
⚫︎重機(ユンボ)を使う場合がある
⚫︎根の処分費用が別途必要
⚫︎土地を更地にしたいときに最適
⚫︎シロアリ対策にもつながる
⚫︎作業難度は伐採より高い
抜根が必要になる最大の理由は、木の再生を防ぐためです。伐採後も根が残っていると、木は再び芽を出すことがあり、場合によっては数年後にまた伐採が必要になるケースがあります。
また根が残れば土壌内に空洞ができたり、シロアリの住処になる恐れもあるため、外構工事・駐車場造成・家の建て替えを予定している場合は抜根が必須です。
抜根作業では根の位置や太さ・周囲の構造物(ブロック塀・水道管・配線)を避けながら慎重に掘り進めます。
そのため作業には専門知識が必要で、根が深く広がっているケースでは小型の重機を使うのが一般的です。
特に高さ5m以上の庭木や、植えてから20年以上経っている木は、根が想像以上に強く張っているため、人力での抜根は非常に難しいでしょう。
費用相場としては、小さな庭木で5,000円〜10,000円、大きな木では30,000円〜100,000円と幅があります。
伐採と違い、根をすべて掘り起こすため時間もかかり、地中の石や障害物が見つかれば追加費用が必要になるケースも。
安全性・時間・コストの面から見ても、自分で抜根作業を行うのは現実的ではなく、業者への依頼がもっともスムーズかつ安全な方法となるでしょう。
それぞれどんな時に選ぶべきか
伐採と抜根は目的が異なるため、状況に応じて正しい方法を選ぶとよいでしょう。ここでは、どちらを選ぶべきか迷っている人向けに、具体的な判断基準を整理しました。
まず選ぶ基準としては、以下を参考にするとよいでしょう。
まず選ぶ基準としては、以下を参考にするとよいでしょう。
| 状況 | 適した作業 |
| 木を倒したいだけ | 伐採 |
| 木が倒れそうで危険 | 伐採 |
| 根から完全に撤去したい | 抜根 |
| 外構工事・駐車場造成をする | 抜根 |
| 木の再生を防ぎたい | 抜根 |
| 費用を抑えたい | 伐採 |
| 大木で危険リスクが高い | 業者依頼で伐採+必要に応じて抜根 |
伐採を選ぶべきケースは、木を倒したいだけや、日当たりを改善したいなど木を地上部から取り除けば問題が解決する状況です。
切り株が残っても支障がない場合は、伐採のみで十分対応できます。また費用を抑えたい場合も伐採が適しています。
一方で抜根が必要なのは、「庭を更地にしたい」「車を停めたい」「外構リフォームをする」「木が再生しては困る」といった、根っこまで取り除く必要があるケースです。
抜根をしないまま工事を進めると地中の根が邪魔になり、施工業者が困ため注意しましょう。
また根が残っていると地面が盛り上がったり、地盤が不安定になったりすることもあるため、長期的に見ても抜根は重要です。
さらに重要なのは、安全性です。特に高さ5〜10m以上の庭木は素人が扱うには危険が大きく、伐採方向の読み違いやチェーンソーの暴発で事故が発生しやすいため注意してください。
大木の処理や家・電線が近い場所の伐採は、必ず専門業者への依頼を検討すべきでしょう。専門業者ならロープワークや高所作業車を使い、安全に木を切り分けながら処理できます。
切り株が残っても支障がない場合は、伐採のみで十分対応できます。また費用を抑えたい場合も伐採が適しています。
一方で抜根が必要なのは、「庭を更地にしたい」「車を停めたい」「外構リフォームをする」「木が再生しては困る」といった、根っこまで取り除く必要があるケースです。
抜根をしないまま工事を進めると地中の根が邪魔になり、施工業者が困ため注意しましょう。
また根が残っていると地面が盛り上がったり、地盤が不安定になったりすることもあるため、長期的に見ても抜根は重要です。
さらに重要なのは、安全性です。特に高さ5〜10m以上の庭木は素人が扱うには危険が大きく、伐採方向の読み違いやチェーンソーの暴発で事故が発生しやすいため注意してください。
大木の処理や家・電線が近い場所の伐採は、必ず専門業者への依頼を検討すべきでしょう。専門業者ならロープワークや高所作業車を使い、安全に木を切り分けながら処理できます。
自分で伐採できる木とできない木の見分け方
庭木の伐採を考えるとき、「自分でできるのか」「業者に依頼すべきなのか」で迷っていませんか。
木の高さや幹の太さだけでなく、周辺環境の安全性・必要な道具・作業スペースなど複数の要素が関わるため、判断を誤ると大きな事故につながります。
安全に作業を進めるための基準が分かれば、無駄な出費やトラブルを避けられるでしょう。
木の高さや幹の太さだけでなく、周辺環境の安全性・必要な道具・作業スペースなど複数の要素が関わるため、判断を誤ると大きな事故につながります。
安全に作業を進めるための基準が分かれば、無駄な出費やトラブルを避けられるでしょう。
高さ3m以下で直径20cm以下なら自分でも可能
木の伐採を自分で行える目安として、高さ3メートル以下・幹の直径20cm以下が一般的な基準になります。
このサイズなら、ノコギリや小型のチェーンソーが扱いやすく、倒れる際の危険性も比較的低いのが特徴。
初心者でも対応できるケースが多いです。ただし「可能=安全」というわけではなく、あくまで適切な準備と手順を踏めばという前提を忘れないようにしましょう。
自分で伐採できる木の条件は以下を目安にしてください。
このサイズなら、ノコギリや小型のチェーンソーが扱いやすく、倒れる際の危険性も比較的低いのが特徴。
初心者でも対応できるケースが多いです。ただし「可能=安全」というわけではなく、あくまで適切な準備と手順を踏めばという前提を忘れないようにしましょう。
自分で伐採できる木の条件は以下を目安にしてください。
| 条件 | 内容 |
| 高さ | 3m以下 |
| 幹の太さ | 20cm以下 |
| 枝の広がり |
周囲に接触しない範囲 |
| 道具の準備 | ノコギリ、チェーンソー、小型脚立 |
| 周辺環境 | 建物・電線・ガラスから離れている |
| 作業人数 | 最低2名(サポート要員含む) |
高さ3メートル以下の木は、倒れる際の勢いが比較的弱いため、方向をコントロールしやすくなります。
しかし伐採の基本である、受け口・追いの切り方を誤ると、倒れる方向がズレてしまい危険です。
幹の太さが20cmを超えると、チェーンソーの刃の長さが不足したり、切断時の振動が大きくなり、初心者では扱いが難しくなるでしょう。
さらに自分で伐採する場合は、安全装備が欠かせません。耐切創グローブや安全靴・フェイスガードなど、最低限の保護具を揃える必要があります。
また作業は一人で行うべきではなく、倒れる方向の監視やロープで木を引っ張る補助員が必要です。
自治体によっては伐採した木や枝葉をそのまま捨てられない場合があるため、処分方法を事前に確認することも大切です。
様々な点を踏まえると、小さな木であっても準備は意外と大変であり、無理に自力でやるより、業者に依頼したほうが結果的に早く、安全かつ安く済むケースも少なくありません。
しかし伐採の基本である、受け口・追いの切り方を誤ると、倒れる方向がズレてしまい危険です。
幹の太さが20cmを超えると、チェーンソーの刃の長さが不足したり、切断時の振動が大きくなり、初心者では扱いが難しくなるでしょう。
さらに自分で伐採する場合は、安全装備が欠かせません。耐切創グローブや安全靴・フェイスガードなど、最低限の保護具を揃える必要があります。
また作業は一人で行うべきではなく、倒れる方向の監視やロープで木を引っ張る補助員が必要です。
自治体によっては伐採した木や枝葉をそのまま捨てられない場合があるため、処分方法を事前に確認することも大切です。
様々な点を踏まえると、小さな木であっても準備は意外と大変であり、無理に自力でやるより、業者に依頼したほうが結果的に早く、安全かつ安く済むケースも少なくありません。
これ以上大きい木は業者に依頼すべき理由
高さ3m以上、幹の太さ20cm以上の木は、素人が伐採するには非常に危険が伴います。木の重さは想像以上で、倒れ方が少しズレただけで塀やガラスを破損したり、最悪の場合は重大事故につながるケースも。
業者に依頼すべき理由は安全性・技術力・処分の利便性の3つが大きなポイントです。
業者に依頼すべき木の特徴は以下の通りです。
⚫︎高さ3m以上、幹が太い
⚫︎周囲に建物・車・電線がある
⚫︎枝が高所に広がっている
⚫︎ロープワークが必要な場面が多い
⚫︎木の傾きが強く倒れる方向が読めない
⚫︎チェーンソーでの切断が必要
木は高さが増すほど倒れる際の力が強くなり、コントロールできる範囲が急激に狭くなります。たとえば高さ5mの木は、直径20cm程度でも数百キロ単位の重量があり、倒れた際に壁やフェンスを破壊する可能性があります。
業者は部分伐採と呼ばれる技術を用い、上部から少しずつ切り落とし、ロープで丁寧に地面へ降ろすため、安全に作業できる点が特徴です。
また倒すスペースが十分に取れない住宅密集地では、高所作業車やクライミング技術(アーボリスト技術)が必要になります。主に専門資格を要する作業であり、一般の方が真似できるものではありません。
さらに伐採後の処分も大きな負担です。大木の幹は非常に重く、一般家庭の車では運搬できないケースが多いです。
業者ならその場で粉砕処理したり、トラックで持ち帰って処分してくれるため、手間と時間を大幅に省けるでしょう。
業者に依頼すべき理由は安全性・技術力・処分の利便性の3つが大きなポイントです。
業者に依頼すべき木の特徴は以下の通りです。
⚫︎高さ3m以上、幹が太い
⚫︎周囲に建物・車・電線がある
⚫︎枝が高所に広がっている
⚫︎ロープワークが必要な場面が多い
⚫︎木の傾きが強く倒れる方向が読めない
⚫︎チェーンソーでの切断が必要
木は高さが増すほど倒れる際の力が強くなり、コントロールできる範囲が急激に狭くなります。たとえば高さ5mの木は、直径20cm程度でも数百キロ単位の重量があり、倒れた際に壁やフェンスを破壊する可能性があります。
業者は部分伐採と呼ばれる技術を用い、上部から少しずつ切り落とし、ロープで丁寧に地面へ降ろすため、安全に作業できる点が特徴です。
また倒すスペースが十分に取れない住宅密集地では、高所作業車やクライミング技術(アーボリスト技術)が必要になります。主に専門資格を要する作業であり、一般の方が真似できるものではありません。
さらに伐採後の処分も大きな負担です。大木の幹は非常に重く、一般家庭の車では運搬できないケースが多いです。
業者ならその場で粉砕処理したり、トラックで持ち帰って処分してくれるため、手間と時間を大幅に省けるでしょう。
周辺環境もチェック!電線や建物が近くにある場合は要注意
伐採の難易度を左右するのは、木の大きさだけではありません。たとえ小さな木でも、電線や建物・ガラス窓・道路・隣家の敷地などが近くにあると、倒す方向が制限され、事故リスクが高まります。周辺環境のチェックは、木を切る前の最重要作業とも言えます。
周辺環境で注意すべきポイントは以下の通りです。
周辺環境で注意すべきポイントは以下の通りです。
| 危険要素 | リスク内容 |
| 電線 | 感電・停電・通信障害 |
| 建物 | 壁・窓の破損、修繕費の発生 |
| 隣家の敷地 |
トラブル・弁償問題 |
| 車・道路 | 交通事故や物損リスク |
| 傾斜地 | 足場の不安定化 |
特に注意すべきなのが電線です。木が少し触れただけでも停電や通信トラブルにつながるケースがあり、場合によっては電力会社へ連絡が必要になる可能性もあります。
自力で伐採しようとして電線に木が倒れかかった場合、高額な賠償になる可能性もゼロではありません。
また住宅密集地では倒すスペースが極端に狭く、木を倒すという発想自体が間違いになります。プロの伐採業者は、木に登って枝を少しずつ切り落とし、ロープでゆっくりと地上に降ろす「吊り切り作業」を行います。
高度な技術があるからこそ、建物のすぐ隣でも安全に作業できるのです。
また風向きや地面の傾き、根の張り方によってもリスクは大きく変化します。すべてを素人が判断するのは難しく、判断ミスは重大事故につながる可能性が。
安全面・近隣トラブル・修繕費のリスクを考えると、周辺環境に不安がある場合は、迷わず業者に依頼するのがおすすめです。
自力で伐採しようとして電線に木が倒れかかった場合、高額な賠償になる可能性もゼロではありません。
また住宅密集地では倒すスペースが極端に狭く、木を倒すという発想自体が間違いになります。プロの伐採業者は、木に登って枝を少しずつ切り落とし、ロープでゆっくりと地上に降ろす「吊り切り作業」を行います。
高度な技術があるからこそ、建物のすぐ隣でも安全に作業できるのです。
また風向きや地面の傾き、根の張り方によってもリスクは大きく変化します。すべてを素人が判断するのは難しく、判断ミスは重大事故につながる可能性が。
安全面・近隣トラブル・修繕費のリスクを考えると、周辺環境に不安がある場合は、迷わず業者に依頼するのがおすすめです。
自分で木を伐採する手順を解説
庭木を自分で伐採したいと思っても、正しい手順や道具がわからず不安になる人は多いでしょう。
木の伐採には危険が伴うため、流れを理解せずに作業すると事故につながる可能性が高くなります。ここでは初心者でも理解できるように「伐採作業の基本手順」を見ていきましょう。
木の伐採には危険が伴うため、流れを理解せずに作業すると事故につながる可能性が高くなります。ここでは初心者でも理解できるように「伐採作業の基本手順」を見ていきましょう。
必要な道具を揃える
木を安全に伐採するためには、切断のための道具だけでなく、自分の身を守る安全装備、作業をスムーズに進める補助道具など、複数のアイテムが必要です。
道具が不十分なまま作業すると、ケガのリスクが高まり、木が予期しない方向へ倒れてしまう可能性もあります。まずは、必ず揃えておきたい道具を整理してみましょう。
道具が不十分なまま作業すると、ケガのリスクが高まり、木が予期しない方向へ倒れてしまう可能性もあります。まずは、必ず揃えておきたい道具を整理してみましょう。
切断に使う道具はノコギリかチェーンソー
伐採の要となるのが、切断用の道具です。木の太さや種類に応じて、ノコギリかチェーンソーを使い分けます。
切断道具の比較は以下の通りです。
切断道具の比較は以下の通りです。
| 道具 | 特徴 | 適した木の太さ |
| 手ノコギリ | 安価で扱いやすい/静かな作業が可能 | 直径10〜15cm程度 |
| 小型チェーンソー | DIY向け/軽量で家庭用に最適 | 直径15〜20cm |
| 中型チェーンソー | パワーが強く早く切れる/扱いには注意が必要 | 直径20cm以上 |
ノコギリは操作が簡単な一方、太い木を切るには時間がかかる点を覚えておきましょう。そのため直径15cm以下の細い庭木に向いています。
チェーンソーはパワーがあるため効率よく作業できますが、振動や反動(キックバック)が強く、正しい持ち方を知らないと危険です。特に直径20cm以上の木を切る場合は、刃の長さやエンジンのパワーが十分なチェーンソーが必要になるケースも。
切断道具の選び方を誤ると、途中で刃が詰まったり、切断中に木が折れて想定外の方向へ倒れる危険があります。
またチェーンソーを使用する際は、事前点検が必須です。チェーンの張り具合やオイルの量・スイッチの反応などを確認してから作業に入ることで、事故の防止につながります。
切断時は常に両手でしっかり支え、足元が安定しているか確認しながら進めるのもポイントです。切断道具は、木の大きさ・作業する人のスキル・周囲の状況を考慮して選びましょう。
チェーンソーはパワーがあるため効率よく作業できますが、振動や反動(キックバック)が強く、正しい持ち方を知らないと危険です。特に直径20cm以上の木を切る場合は、刃の長さやエンジンのパワーが十分なチェーンソーが必要になるケースも。
切断道具の選び方を誤ると、途中で刃が詰まったり、切断中に木が折れて想定外の方向へ倒れる危険があります。
またチェーンソーを使用する際は、事前点検が必須です。チェーンの張り具合やオイルの量・スイッチの反応などを確認してから作業に入ることで、事故の防止につながります。
切断時は常に両手でしっかり支え、足元が安定しているか確認しながら進めるのもポイントです。切断道具は、木の大きさ・作業する人のスキル・周囲の状況を考慮して選びましょう。
安全を守るための装備を忘れずに
伐採作業で最も重要なのが、安全装備です。切断中の木の破片飛散、チェーンソーの反動、枝の落下など、作業中は危険が常に存在します。十分な装備を整えることで、ケガのリスクを大幅に減らせるでしょう。
最低限の安全装備として、以下を用意してください。
⚫︎防護メガネ(飛散物から目を保護)
⚫︎耐切創手袋(チェーンソー対応が望ましい)
⚫︎安全靴(滑りにくく足を守る)
⚫︎ヘルメット(枝落下の危険に備える)
⚫︎厚手の作業着(皮膚の保護)
⚫︎耳栓(チェーンソーの騒音対策)
チェーンソーは非常に音が大きく、長時間作業していると聴覚に影響が出る恐れがあります。そのため耳栓や、イヤーマフは忘れずに準備し、作業を短時間で区切るなど疲労対策も必要です。
また破片が飛んで視界を遮られると判断を誤る原因になるため、防護メガネの着用は必須。作業服は肌をしっかり覆う厚手のものを選び、枝やチェーンソーが直接当たるリスクを減らしましょう。
さらに、伐採作業は見通しが悪い状態で危険が重なりやすいため、一人で行うのは避けるべきです。補助員をつけ、周囲を見守ってもらうだけで事故リスクは大きく低下しますよ。安全装備に、備えすぎはありません。
プロの伐採業者が完全な安全装備をしているのは、それだけリスクが多い作業だからです。道具を揃える段階で安全第一を徹底しましょう。
最低限の安全装備として、以下を用意してください。
⚫︎防護メガネ(飛散物から目を保護)
⚫︎耐切創手袋(チェーンソー対応が望ましい)
⚫︎安全靴(滑りにくく足を守る)
⚫︎ヘルメット(枝落下の危険に備える)
⚫︎厚手の作業着(皮膚の保護)
⚫︎耳栓(チェーンソーの騒音対策)
チェーンソーは非常に音が大きく、長時間作業していると聴覚に影響が出る恐れがあります。そのため耳栓や、イヤーマフは忘れずに準備し、作業を短時間で区切るなど疲労対策も必要です。
また破片が飛んで視界を遮られると判断を誤る原因になるため、防護メガネの着用は必須。作業服は肌をしっかり覆う厚手のものを選び、枝やチェーンソーが直接当たるリスクを減らしましょう。
さらに、伐採作業は見通しが悪い状態で危険が重なりやすいため、一人で行うのは避けるべきです。補助員をつけ、周囲を見守ってもらうだけで事故リスクは大きく低下しますよ。安全装備に、備えすぎはありません。
プロの伐採業者が完全な安全装備をしているのは、それだけリスクが多い作業だからです。道具を揃える段階で安全第一を徹底しましょう。
ロープや脚立など補助的な道具も準備しよう
切断道具だけでなく、木を安全な方向へ倒したり、高所の枝を落としたりする補助道具も必要です。
| 道具 | 役割 |
| ロープ | 木を倒す方向を調整・固定 |
| 脚立 | 高い位置の枝切りに必要 |
| くさび |
受け口・追い口のずれ防止 |
| ガイド棒 | チェーンソー切断時の安定補助 |
| ブルーシート | 茂った枝を集めやすくする |
| 掃除道具 | 切り落とした枝の処分用 |
ロープは木を倒す方向を調整する際に欠かせません。事前に倒したい方向とは反対側にロープをかけ、補助員が一定のテンションで引けば、安全に木を誘導できます。脚立は枝の高さに合わせて選び、転倒しにくい設計のものを優先すると安心です。
また切断中にチェーンソーが木に挟まれるケースがあります。くさびを挟んで隙間を支えれば、刃が動かなくなるのを防げるでしょう。
伐採後の処理も意外と大変で、枝葉が大量に出るため、ブルーシートで広い範囲を覆っておくと後片付けが楽になりますよ。
補助道具を準備せずに作業を始めると、木が思わぬ方向へ倒れる・高い枝が切れないなどのトラブルが起こりやすくなります。安全でスムーズな作業のためにも、補助道具の準備は軽視できません。
また切断中にチェーンソーが木に挟まれるケースがあります。くさびを挟んで隙間を支えれば、刃が動かなくなるのを防げるでしょう。
伐採後の処理も意外と大変で、枝葉が大量に出るため、ブルーシートで広い範囲を覆っておくと後片付けが楽になりますよ。
補助道具を準備せずに作業を始めると、木が思わぬ方向へ倒れる・高い枝が切れないなどのトラブルが起こりやすくなります。安全でスムーズな作業のためにも、補助道具の準備は軽視できません。
倒す方向を決めてロープで固定する
伐採作業で最も重要なのが、倒す方向の決定です。木は重量があり、一度倒れ始めると方向の調整が難しくなるため、倒す方向を誤ると建物やフェンスを損傷する危険があります。
また電線や道路が近い場合は重大事故につながるため、慎重に判断しなければなりません。
倒す方向を決める際に見るべきポイントは以下の通りです。
⚫︎木の傾き
⚫︎枝の重さが偏っている方向
⚫︎周囲の建物・フェンスの位置
⚫︎風向きや風の強さ
⚫︎電線の位置
⚫︎作業スペースの広さ
木は見た目では直立しているように見えても、幹がわずかに傾いていたり、枝が片側に重く伸びています。
この偏りが伐採時の倒れる方向に影響するため、事前観察は欠かせません。風が強い日や不規則な風向きの日は、伐採作業を避けるのが安全です。
倒す方向を決めたら、ロープを幹の高い位置に結び、補助員が一定の力で引きつつ倒れる方向をサポートします。ロープを使えば木の倒れる勢いをコントロールしやすくなり、方向ブレを防げるためです。
さらに倒す方向に十分なスペースがあるか確認し、近隣への影響も考慮する必要があります。
作業中に木が道路側へ倒れると交通事故を招く恐れがあり、電線にかかると停電トラブルの原因になります。倒す方向の判断は、伐採作業の成功率を左右する大切な作業です。
また電線や道路が近い場合は重大事故につながるため、慎重に判断しなければなりません。
倒す方向を決める際に見るべきポイントは以下の通りです。
⚫︎木の傾き
⚫︎枝の重さが偏っている方向
⚫︎周囲の建物・フェンスの位置
⚫︎風向きや風の強さ
⚫︎電線の位置
⚫︎作業スペースの広さ
木は見た目では直立しているように見えても、幹がわずかに傾いていたり、枝が片側に重く伸びています。
この偏りが伐採時の倒れる方向に影響するため、事前観察は欠かせません。風が強い日や不規則な風向きの日は、伐採作業を避けるのが安全です。
倒す方向を決めたら、ロープを幹の高い位置に結び、補助員が一定の力で引きつつ倒れる方向をサポートします。ロープを使えば木の倒れる勢いをコントロールしやすくなり、方向ブレを防げるためです。
さらに倒す方向に十分なスペースがあるか確認し、近隣への影響も考慮する必要があります。
作業中に木が道路側へ倒れると交通事故を招く恐れがあり、電線にかかると停電トラブルの原因になります。倒す方向の判断は、伐採作業の成功率を左右する大切な作業です。
邪魔な枝を事前に切り落としておく
幹を切り倒す前に、枝を先に落としておくことで安全性と作業効率が大幅に向上します。枝が多いまま伐採すると、倒れる方向に引っかかるものが増え、思わぬ方向へ倒れる原因になるため注意しましょう。
事前の枝落としが必要な理由は以下の通りです。
事前の枝落としが必要な理由は以下の通りです。
| 理由 | 説明 |
| 倒れる方向を制御しやすい |
重心が整うため正確な方向へ倒れる |
| 近隣の建物への接触を防ぐ | 枝が引っかかる事故を防ぐ |
| 作業スペースが広くなる |
足場の確保が容易 |
| チェーンソーの作業性向上 | 幹が見やすく安全に切断できる |
枝落としでは、軽い枝から順に落としていくと安全です。下から切ると枝が頭上に落ちるリスクがあるため、基本は上から順に切り落としましょう。
ただし高所の枝を自力で切るのは危険が伴うため、脚立を使う場合は転倒に注意し、必ず補助員を配置してください。
枝を落とすことで木の重心が中心に戻り、倒れる方向をコントロールしやすくなります。特に庭木は片側の光を求めて成長するため、枝の偏りが大きくなりがち。偏りを解消しないまま伐採すると、想定外の方向へ倒れる原因になります。
さらに枝落としは作業スペースを確保する意味でも重要です。広いスペースがあると、チェーンソーを使う際に姿勢が安定し、安全な作業ができます。枝落としは伐採前の“準備として最も重要な工程”と言っても過言ではありません。
ただし高所の枝を自力で切るのは危険が伴うため、脚立を使う場合は転倒に注意し、必ず補助員を配置してください。
枝を落とすことで木の重心が中心に戻り、倒れる方向をコントロールしやすくなります。特に庭木は片側の光を求めて成長するため、枝の偏りが大きくなりがち。偏りを解消しないまま伐採すると、想定外の方向へ倒れる原因になります。
さらに枝落としは作業スペースを確保する意味でも重要です。広いスペースがあると、チェーンソーを使う際に姿勢が安定し、安全な作業ができます。枝落としは伐採前の“準備として最も重要な工程”と言っても過言ではありません。
受け口と追い口を正しく入れて安全に倒す
伐採の核心となるのが受け口と、追い口の作り方です。この2つの切り込みが正しく入っていないと、木が意図しない方向へ倒れて危険が増します。
受け口は、木が倒れる方向のガイドとなる部分です。受け口の角度が狭すぎると木が途中でひっかかり、倒れにくくなります。
広すぎても木の支えが弱くなるため、45度前後が最も安定する点を覚えておきましょう。
追い口はその反対側から入れる切り込みで、受け口よりやや高い位置から切るのが安全です。段差があることで倒れる方向が一定になり、均等に力が逃げていきます。
追い口を入れる際は、チェーンソーが木に挟まれないよう注意します。角度が悪かったり、受け口が浅かったりすると、途中でチェーンソーが動かなくなり作業が止まるケースも。
この場合、くさびを挟んで隙間を広げながら慎重に切り進めると安全です。
木が傾き始めたら、チェーンソーはすぐに止め、倒れる方向から速やかに離れましょう。木が完全に倒れるまで近づかないようにする点も重要です。
受け口と追い口は伐採手順の中で最も事故が起こりやすい工程であり、慎重に行いたい作業といえます。
受け口は、木が倒れる方向のガイドとなる部分です。受け口の角度が狭すぎると木が途中でひっかかり、倒れにくくなります。
広すぎても木の支えが弱くなるため、45度前後が最も安定する点を覚えておきましょう。
追い口はその反対側から入れる切り込みで、受け口よりやや高い位置から切るのが安全です。段差があることで倒れる方向が一定になり、均等に力が逃げていきます。
追い口を入れる際は、チェーンソーが木に挟まれないよう注意します。角度が悪かったり、受け口が浅かったりすると、途中でチェーンソーが動かなくなり作業が止まるケースも。
この場合、くさびを挟んで隙間を広げながら慎重に切り進めると安全です。
木が傾き始めたら、チェーンソーはすぐに止め、倒れる方向から速やかに離れましょう。木が完全に倒れるまで近づかないようにする点も重要です。
受け口と追い口は伐採手順の中で最も事故が起こりやすい工程であり、慎重に行いたい作業といえます。
倒した後は適切なサイズに切り分ける
木を倒した後は、適切なサイズに切り分けて処分しやすくします。伐採後の木は重量があり、運ぶだけでも大きな負担になるため、扱いやすい大きさに整理しましょう。
切り分け作業のポイントは以下の通りです。
切り分け作業のポイントは以下の通りです。
| 作業内容 | 目的 |
| 幹を50〜80cmごとに切る | 持ち運びしやすくする |
| 枝葉を細かく切る | ゴミ袋に入れやすくする |
| 根元の整形 | 切り株の高さ調整 |
| ブルーシートでまとめる | 掃除が簡単になる |
倒した木は意外と重く、太い幹であれば1本だけでも持ち上げるのが難しいケースがあります。そのため、持ち運びやすいサイズに切り分けておくとよいでしょう。
チェーンソーで切る際は、木が転がらないよう固定し、安定した姿勢で作業するのがポイントです。
枝葉は自治体によって処分ルールが異なるため、事前に確認しておきましょう。多くの地域では、指定袋に入るサイズや長さの上限が決められています。
ブルーシートの上に枝葉を落とせば、掃除がスムーズになり、作業時間の短縮につながりますよ。
太い幹は処分費用が別途発生する場合があり、軽トラックなどの運搬手段が必要になるケースもあります。
様々な手間や費用を考えると、自分で伐採するメリットが小さく感じられるかもしれません。倒した後の処理や処分作業まで含めると、業者に任せたほうが効率的な場合も多いです。
チェーンソーで切る際は、木が転がらないよう固定し、安定した姿勢で作業するのがポイントです。
枝葉は自治体によって処分ルールが異なるため、事前に確認しておきましょう。多くの地域では、指定袋に入るサイズや長さの上限が決められています。
ブルーシートの上に枝葉を落とせば、掃除がスムーズになり、作業時間の短縮につながりますよ。
太い幹は処分費用が別途発生する場合があり、軽トラックなどの運搬手段が必要になるケースもあります。
様々な手間や費用を考えると、自分で伐採するメリットが小さく感じられるかもしれません。倒した後の処理や処分作業まで含めると、業者に任せたほうが効率的な場合も多いです。
木の伐採に適した時期はいつ?季節ごとの違い
木の伐採は行うタイミングによって作業の難易度や費用、安全性が大きく変わります。木の状態は季節によって水分量や重さが異なり、切り倒した後の処分のしやすさも変化する点を覚えておきましょう。
また木が育つ成長期や、雨が続く梅雨は作業リスクが高くなるため、伐採時期を慎重に選ぶのがコツ。
ここでは季節ごとの特徴や最適な伐採時期、避けたほうがよい時期についてわかりやすく解説します。
また木が育つ成長期や、雨が続く梅雨は作業リスクが高くなるため、伐採時期を慎重に選ぶのがコツ。
ここでは季節ごとの特徴や最適な伐採時期、避けたほうがよい時期についてわかりやすく解説します。
冬が最適な理由は木が軽くて扱いやすいから
木の伐採に最も適した季節は冬です。落葉樹の葉が落ちて軽くなり、木全体の水分量が減るため、伐採作業がしやすくなります。
枝葉の量が減ることで倒れる方向を見極めやすく、チェーンソーの刃の進みもスムーズになります。
冬に伐採が適している理由は以下の通りです。
枝葉の量が減ることで倒れる方向を見極めやすく、チェーンソーの刃の進みもスムーズになります。
冬に伐採が適している理由は以下の通りです。
| 理由 | 説明 |
| 木の水分量が少ない | 軽くなるため切断しやすい |
| 枝葉が少ない | 倒れる方向が安定しやすい |
| 虫が少ない | 作業中のトラブルが少ない |
| 成長が止まっている | ダメージが最小限で庭木にやさしい |
| 作業日程が組みやすい | 業者の繁忙期を避けられることも |
冬は木が休眠期に入り、成長が止まることで樹液の流れが緩やかになります。樹液が少ない状態の木は軽いため、伐採時の倒れるスピードや安定性を読みやすくなる点がメリット。
特に高さがある木や太い幹の庭木では、重さの違いが作業の安全性に関係します。
また落葉樹の場合は枝葉がほとんど落ちているため、伐採時の視界が広がり、枝が他の樹木や建物に引っかかるリスクが低くなります。虫が少なく、害虫対策をする必要がないのも冬のメリットです。
他にも業者に依頼する場合も冬はメリットがあります。外構工事の繁忙期が過ぎて比較的スケジュールが取りやすく、費用の交渉がしやすい場合も。
作業員の安全面から見ても、夏のように熱中症のリスクがなく、安定した作業が可能でしょう。伐採の条件を考えると、冬はメリットが最も多い季節と言えます。
特に高さがある木や太い幹の庭木では、重さの違いが作業の安全性に関係します。
また落葉樹の場合は枝葉がほとんど落ちているため、伐採時の視界が広がり、枝が他の樹木や建物に引っかかるリスクが低くなります。虫が少なく、害虫対策をする必要がないのも冬のメリットです。
他にも業者に依頼する場合も冬はメリットがあります。外構工事の繁忙期が過ぎて比較的スケジュールが取りやすく、費用の交渉がしやすい場合も。
作業員の安全面から見ても、夏のように熱中症のリスクがなく、安定した作業が可能でしょう。伐採の条件を考えると、冬はメリットが最も多い季節と言えます。
避けたい時期は梅雨と成長期
伐採に適さない時期として、梅雨と木の成長期(春〜初夏)が挙げられます。梅雨と木の成長期(春〜初夏)の時期は木の水分量が多く、雨による作業リスクも高いため、可能であれば避けたほうがよいでしょう。
避けたい時期と理由は以下の通りです。
⚫︎梅雨は地面が滑りやすい
⚫︎雨による視界不良でチェーンソー作業が危険
⚫︎湿気で木が重くなり倒れる方向が読みにくい
⚫︎春〜初夏は木が成長期で水分量が多い
⚫︎枝葉が大きく広がり作業性が低下
⚫︎害虫が増えるため危険が増す
梅雨時期は地面がぬかるんでおり、脚立が安定しにくく、作業員が滑る危険性があります。チェーンソーの扱いは少しのバランスの崩れが重大事故につながるため、雨天の伐採は避けるべきです。
雨で木が重くなることで倒れる方向の予測も難しくなり、ロープでの調整も不安定になるでしょう。
その後、春から初夏にかけては木が成長期に入り、水分を多く吸い上げています。樹液が多い状態の木は重く、切断時の抵抗が増えるため、作業に時間がかかるだけでなく倒れる際の勢いが強くなる点に注意しましょう。
また枝葉が茂っていると伐採時の視界が狭くなり、周囲の建物や電線に接触しやすくなるため危険性が増します。
さらに暖かい季節は害虫や蜂などの発生も多く、伐採中に刺されたり巣を刺激するリスクも。作業者の安全だけでなく、近隣トラブルの観点からも、春〜初夏の伐採は十分注意が必要です。
避けたい時期と理由は以下の通りです。
⚫︎梅雨は地面が滑りやすい
⚫︎雨による視界不良でチェーンソー作業が危険
⚫︎湿気で木が重くなり倒れる方向が読みにくい
⚫︎春〜初夏は木が成長期で水分量が多い
⚫︎枝葉が大きく広がり作業性が低下
⚫︎害虫が増えるため危険が増す
梅雨時期は地面がぬかるんでおり、脚立が安定しにくく、作業員が滑る危険性があります。チェーンソーの扱いは少しのバランスの崩れが重大事故につながるため、雨天の伐採は避けるべきです。
雨で木が重くなることで倒れる方向の予測も難しくなり、ロープでの調整も不安定になるでしょう。
その後、春から初夏にかけては木が成長期に入り、水分を多く吸い上げています。樹液が多い状態の木は重く、切断時の抵抗が増えるため、作業に時間がかかるだけでなく倒れる際の勢いが強くなる点に注意しましょう。
また枝葉が茂っていると伐採時の視界が狭くなり、周囲の建物や電線に接触しやすくなるため危険性が増します。
さらに暖かい季節は害虫や蜂などの発生も多く、伐採中に刺されたり巣を刺激するリスクも。作業者の安全だけでなく、近隣トラブルの観点からも、春〜初夏の伐採は十分注意が必要です。
縁起を担ぐなら土用の日を避ける人もいる
昔から、伐採は縁起に関わる作業と考えられてきました。特に日本では、土用の期間(立春・立夏・立秋・立冬の前18日間)は土を動かすのを避けるといった風習があります。
伐採と縁起の関係には諸説ありますが、おおむね以下の通りです。
伐採と縁起の関係には諸説ありますが、おおむね以下の通りです。
| 風習内容 | 説明 |
| 土用に伐採を避ける | 土の神が怒るとされている |
| 大木は特に慎重に扱う | “家の守り木”と捉える地域もある |
| 引っ越しや工事も避けることが多い | 土を傷つける行為と考えられてきた |
土用に伐採を避ける風習は地域や家庭によって大きく異なります。現代では必ず守らなければならないものではありませんが、家族の考え方や地域の風習によっては重視されるケースも。
特に大きな木や長年庭にあった木は守り木とされていたり、家族の思い出と結びついていることが多く、心理的な抵抗が生まれるケースがあります。
業者に依頼する場合も、土用期間を避けたいという希望を伝えると柔軟に対応してくれるでしょう。縁起面を配慮することで、家族が納得しやすくなり、伐採後の後悔を減らせる点も◎。
伐採は物理的な作業にとどまらず、心理面や地域の慣習も関係する作業です。作業の安全性だけでなく、縁起を重視したい場合は日程調整を行うと安心できるでしょう。
特に大きな木や長年庭にあった木は守り木とされていたり、家族の思い出と結びついていることが多く、心理的な抵抗が生まれるケースがあります。
業者に依頼する場合も、土用期間を避けたいという希望を伝えると柔軟に対応してくれるでしょう。縁起面を配慮することで、家族が納得しやすくなり、伐採後の後悔を減らせる点も◎。
伐採は物理的な作業にとどまらず、心理面や地域の慣習も関係する作業です。作業の安全性だけでなく、縁起を重視したい場合は日程調整を行うと安心できるでしょう。
業者に木の伐採を依頼した場合の費用相場
伐採を業者に依頼する場合、最も気になるポイントが費用です。木の高さや幹の太さ・作業場所の環境によって金額が大きく変わります。
また伐採だけでなく抜根や処分費用が別途かかるため、全体の費用を把握しておくとよいでしょう。ここでは一般的な費用相場をわかりやすくまとめます。
また伐採だけでなく抜根や処分費用が別途かかるため、全体の費用を把握しておくとよいでしょう。ここでは一般的な費用相場をわかりやすくまとめます。
木の高さ別に見る費用の目安
木の伐採費用は高さで大きく変わります。おおよその相場は以下を参考にしてください。
| 木の高さ | 費用相場 |
| 〜3m | 5000〜20000円 |
| 3〜5m | 15000〜40000円 |
| 5〜7m | 30000〜80000円 |
| 7〜10m | 50000〜150000円 |
| 10m以上 | 要見積もり(高所作業車が必要) |
高さが増すほど作業の難易度が上がり、費用も高くなります。5m以上の木は自力で伐採するには非常に危険で、専門技術が必要。
高所作業車やロープワークを使用しながら、枝を少しずつ切り落としていく吊り切り作業が行われるため、通常の伐採よりも時間と人員が必要です。
また木が傾いていたり、建物や電線の近くにある場合は追加料金が発生しやすい点に注意。業者によって料金体系が異なるため複数見積もりを取り、作業内容まで確認しましょう。
高所作業車やロープワークを使用しながら、枝を少しずつ切り落としていく吊り切り作業が行われるため、通常の伐採よりも時間と人員が必要です。
また木が傾いていたり、建物や電線の近くにある場合は追加料金が発生しやすい点に注意。業者によって料金体系が異なるため複数見積もりを取り、作業内容まで確認しましょう。
抜根まで依頼すると追加費用
ただし伐採した木の根っこを完全に取り除く「抜根」は、伐採よりも費用がかかります。相場は以下を参考にしてください。
| 木のサイズ | 抜根費用 |
| 小サイズ(〜3m) | 5,000〜15,000円 |
| 中サイズ(3〜5m) | 10,000〜30,000円 |
| 大サイズ(5m以上) | 30,000〜100,000円 |
抜根は地中の根を掘り起こす作業であるため、伐採以上に体力と技術を必要とします。根は複雑に張り巡らされており、水道管やブロック塀に近い場合は慎重な作業が必要です。大きな木の場合は重機を使うことも多く、その分費用が上がります。
また庭をそのまま整地したい、外構工事を予定している場合などは抜根が欠かせません。伐採だけでは再び芽が出ることがあるため、完全に処理したい場合は抜根まで依頼するのが安全です。
また庭をそのまま整地したい、外構工事を予定している場合などは抜根が欠かせません。伐採だけでは再び芽が出ることがあるため、完全に処理したい場合は抜根まで依頼するのが安全です。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
| 作業費 | 人件費・時間単価など | 約5,000〜20,000円 |
| 重機費 | クレーン車・高所作業車など | 約10,000〜30,000円 |
| 処分費 | 切った枝・幹の運搬と廃棄 |
約5,000〜20,000円/人 |
| 抜根費 | 根を掘り出す作業 |
約10,000〜50,000円 |
| 安全対策費 | ロープ作業・交通誘導員など | 約5,000〜15,000円 |
伐採した木の処分方法と費用について
伐採後の木は想像以上に量が多く、処分にも費用がかかります。処分費用の目安は以下の通りです。
⚫︎枝葉の処分…3,000〜10,000円
⚫︎幹の処分…5,000〜20,000円
⚫︎大量の場合…軽トラ1台分で10,000〜30,000円
枝葉は軽いもののかさばるため、袋に入れて出せない量が一度に発生します。自治体のルールによっては「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの規制があり、超える場合は粗大ごみ扱いになる点に注意しましょう。幹は重量があるため、運搬にはトラックが必要です。
業者に依頼すると、その場で粉砕処理(チッパー作業)を行ってくれる場合もあり、処分費用が抑えられることがあります。処分方法を含めて見積もりを比較することで、最終的な費用を抑えられるでしょう。
⚫︎枝葉の処分…3,000〜10,000円
⚫︎幹の処分…5,000〜20,000円
⚫︎大量の場合…軽トラ1台分で10,000〜30,000円
枝葉は軽いもののかさばるため、袋に入れて出せない量が一度に発生します。自治体のルールによっては「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの規制があり、超える場合は粗大ごみ扱いになる点に注意しましょう。幹は重量があるため、運搬にはトラックが必要です。
業者に依頼すると、その場で粉砕処理(チッパー作業)を行ってくれる場合もあり、処分費用が抑えられることがあります。処分方法を含めて見積もりを比較することで、最終的な費用を抑えられるでしょう。
木の伐採についてよくある質問
ここでは木の伐採に関して特に寄せられる質問に回答します。
高さ何メートルまでなら自分で伐採できますか?
伐採を自分で行えるかどうかは、木の「高さ」と「幹の直径」で判断するのが一般的です。安全に作業できる基準を超える木は、素人では対応が難しく、業者に依頼するのが最も安全な方法になります。
自分で伐採可能な木の基準は以下の通りです。
自分で伐採可能な木の基準は以下の通りです。
| 項目 | 基準 |
| 高さ | 3m以下 |
| 幹の太さ | 直径20cm以下 |
| 枝の広がり | 建物・電線から離れている |
| 必要道具 | ノコギリor小型チェーンソー |
| 作業人数 | 2名以上(補助員必須) |
高さ3m以下・直径20cm以下の木は比較的扱いやすく、自分で伐採しても大きな危険が生まれにくいサイズです。
小型のチェーンソーやノコギリでも切断しやすく、倒れる際の勢いも弱いため、倒す方向をコントロールしやすいでしょう。
ただし「安全にできる」といった意味ではなく、準備と技術があれば可能レベルである点には注意が必要です。
一方で高さ4〜5mを超える木は、素人では非常に危険です。倒れる勢いが大きくなり、方向がわずかにズレただけで塀や窓を破損する可能性があります。
特に住宅密集地では、倒すスペースが足りず、木登り伐採(アーボリスト技術)が必要になるケースも。
また風の強さや木の傾き・枝の量・周囲の安全確保など、判断すべきポイントが多く、見た目だけで「簡単に切れそう」と判断するのは非常に危険です。
大きな木ほどプロの技術が必要となるため、無理に自分で作業せず、業者への依頼を検討しましょう。
小型のチェーンソーやノコギリでも切断しやすく、倒れる際の勢いも弱いため、倒す方向をコントロールしやすいでしょう。
ただし「安全にできる」といった意味ではなく、準備と技術があれば可能レベルである点には注意が必要です。
一方で高さ4〜5mを超える木は、素人では非常に危険です。倒れる勢いが大きくなり、方向がわずかにズレただけで塀や窓を破損する可能性があります。
特に住宅密集地では、倒すスペースが足りず、木登り伐採(アーボリスト技術)が必要になるケースも。
また風の強さや木の傾き・枝の量・周囲の安全確保など、判断すべきポイントが多く、見た目だけで「簡単に切れそう」と判断するのは非常に危険です。
大きな木ほどプロの技術が必要となるため、無理に自分で作業せず、業者への依頼を検討しましょう。
大きな木を伐採する際の注意点や危険なことは?
大きな木の伐採は、危険が非常に多く潜んでいます。木の重さ・高さ・倒れる勢いが素人の予想を大きく超えることがあり、毎年多くの事故が報告されています。
大きな木の伐採で起こりやすい危険には以下が挙げられます。
⚫︎倒れる方向のズレによる事故
⚫︎チェーンソーのキックバック
⚫︎枝の落下による怪我
⚫︎隣家や車の破損
⚫︎電線に接触して停電事故
⚫︎根の張り具合による倒木の予測不能
⚫︎高所作業中の転落
大きな木は重心が高く、少しの角度の誤差や風の影響でも倒れる方向が変わります。幹が倒れる力は数百キロにも達し、素人がロープで調整するだけでは制御しきれません。
特に住宅街では建物や駐車場が近いため、一方向に倒せないケースがほとんどです。
またチェーンソーを扱い慣れていない場合、刃が跳ね返るキックバックが発生しやすく、非常に危険です。高所での枝落としは滑落事故につながるため素人が対応するのは大変危険です。
プロの伐採業者は、木登り技術やロープワークを駆使し、木を少しずつ切り分けて下ろす吊り切り作業を行います。この技術は専門訓練を受けた作業員でなければできません。
さらに電線に近い場合は停電や感電事故のリスクがあり、電気会社への連絡が必要なケースも。危険なリスクを正しく判断するには専門知識が必須です。
大きな木を安全に伐採するには、経験・道具・人員が揃ったプロに依頼することが唯一の安全策と言えます。
大きな木の伐採で起こりやすい危険には以下が挙げられます。
⚫︎倒れる方向のズレによる事故
⚫︎チェーンソーのキックバック
⚫︎枝の落下による怪我
⚫︎隣家や車の破損
⚫︎電線に接触して停電事故
⚫︎根の張り具合による倒木の予測不能
⚫︎高所作業中の転落
大きな木は重心が高く、少しの角度の誤差や風の影響でも倒れる方向が変わります。幹が倒れる力は数百キロにも達し、素人がロープで調整するだけでは制御しきれません。
特に住宅街では建物や駐車場が近いため、一方向に倒せないケースがほとんどです。
またチェーンソーを扱い慣れていない場合、刃が跳ね返るキックバックが発生しやすく、非常に危険です。高所での枝落としは滑落事故につながるため素人が対応するのは大変危険です。
プロの伐採業者は、木登り技術やロープワークを駆使し、木を少しずつ切り分けて下ろす吊り切り作業を行います。この技術は専門訓練を受けた作業員でなければできません。
さらに電線に近い場合は停電や感電事故のリスクがあり、電気会社への連絡が必要なケースも。危険なリスクを正しく判断するには専門知識が必須です。
大きな木を安全に伐採するには、経験・道具・人員が揃ったプロに依頼することが唯一の安全策と言えます。
木の伐採後の処分方法は?
伐採後の木は想像以上に量があり、処分方法が分からないという相談が非常に多いです。処分には自治体ルールが関係しており、事前確認が必須となります。伐採後の処分方法としては、以下の方法を参考にしてください。
| 処分方法 | 特徴 |
| 自治体のゴミ回収 | 長さ・太さの規定がある場合が多い |
| 粗大ごみとして回収 |
追加料金が必要 |
| 自分で清掃センターへ持ち込み | 手間はかかるが安価 |
| 業者に処分まで依頼 |
最も楽・安全で確実 |
| 薪として再利用 |
小さな庭木に向く |
伐採した木は太さや量によって処分の手間が大きく変わります。自治体の一般ごみとして出すには、「長さ◯cm以下」「太さ◯cm以内」などの細かい規定があり、規定を超える場合は粗大ごみ扱いになります。
幹が太い木は重量があるため、持ち運ぶだけでも大変です。
自分で清掃センターへ持ち込む方法もありますが、軽トラックが必要だったり、量によっては手数料が発生したりします。庭木の量が多い場合は作業負担が大きくなりがちです。
業者はその場で木を粉砕する専用機械(チッパー)を使用する場合もあり、大量の枝や幹でもスムーズに処分できます。
費用はかかるものの、時間・労力・リスクを考えると最もおすすめの方法です。
幹が太い木は重量があるため、持ち運ぶだけでも大変です。
自分で清掃センターへ持ち込む方法もありますが、軽トラックが必要だったり、量によっては手数料が発生したりします。庭木の量が多い場合は作業負担が大きくなりがちです。
業者はその場で木を粉砕する専用機械(チッパー)を使用する場合もあり、大量の枝や幹でもスムーズに処分できます。
費用はかかるものの、時間・労力・リスクを考えると最もおすすめの方法です。